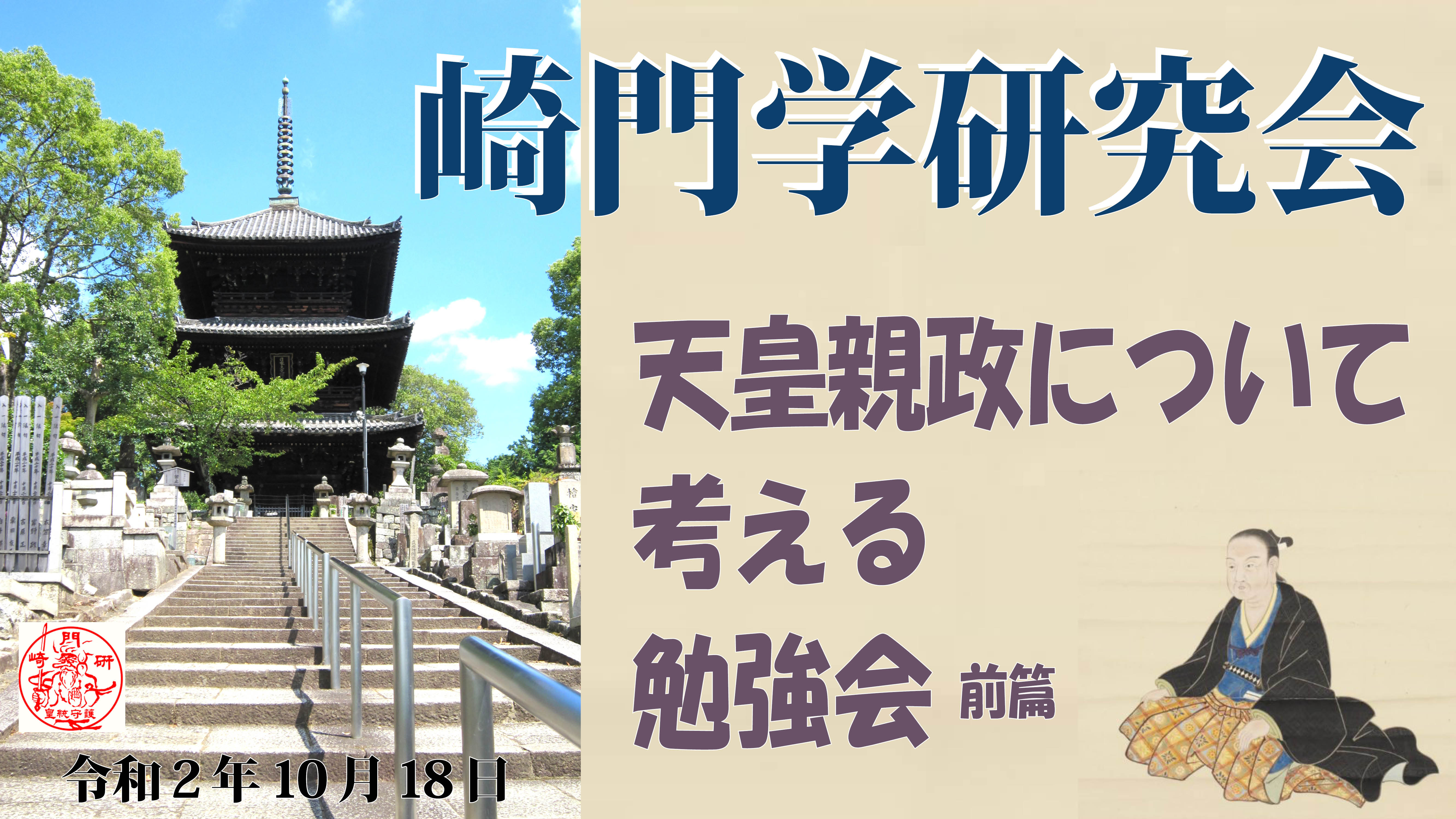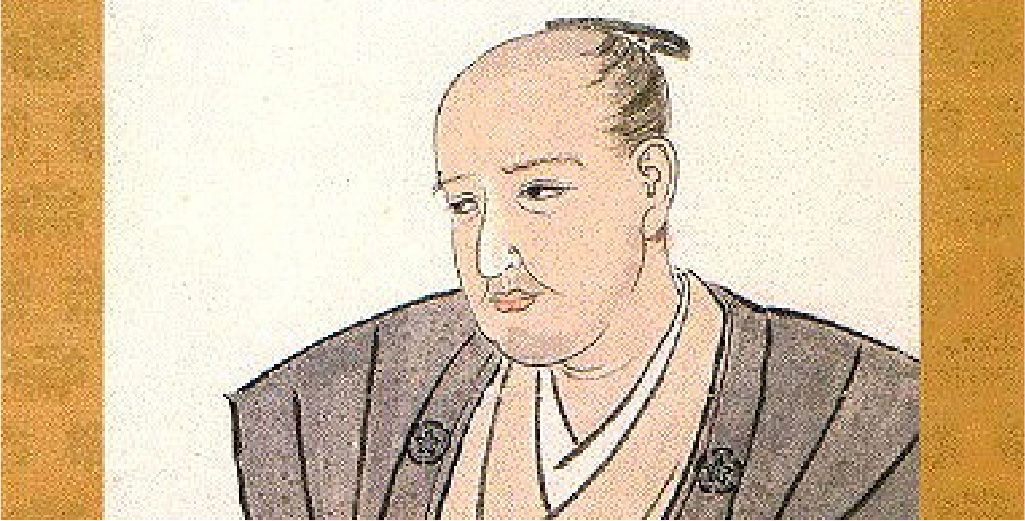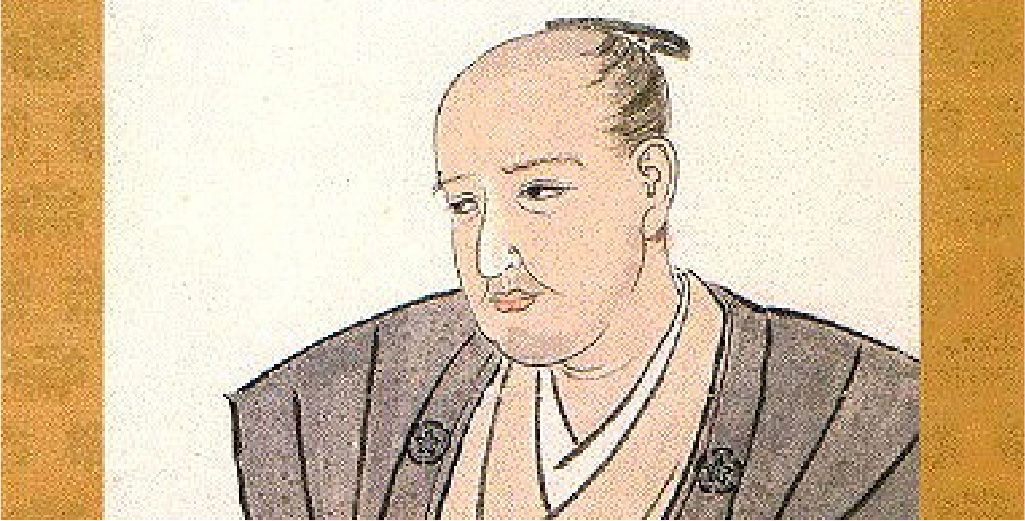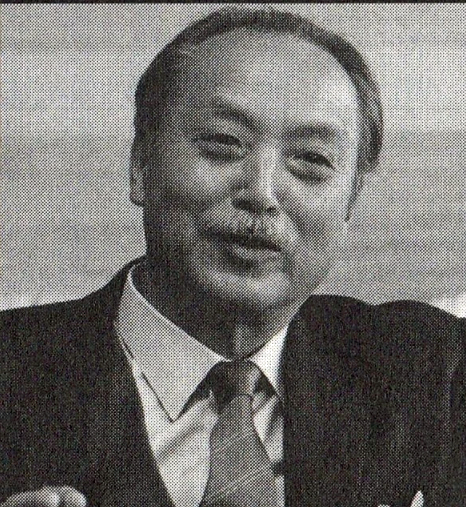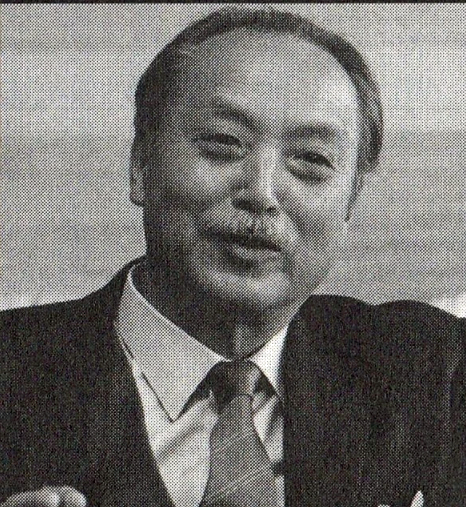令和2年12月6日、崎門学研究会主催の「高須藩ゆかりの地をめぐる─尾張藩尊皇思想の継承者」が開催されました。まず、山県大弐の墓参のため全勝寺(新宿区舟町11-6)を訪れました。
大弐は、徳川幕府全盛時代に国体思想を鼓舞して死罪になった明治維新の先覚者の一人です。明治25年にジャーナリストとして活躍した福地桜痴は「御一新(明治維新)の功は其源を何処に発するかと云うと此先生達(山県大弐・藤井右門・竹内式部の三名)の功労に帰せなければなりますまい」と述べています。
大弐が著した『柳子新論』は、幕末の志士に強い影響を与えました。例えば吉田松陰の考え方を討幕論に転換させたのは、勤皇僧・宇都宮黙霖ですが、その際黙霖が松陰に薦めたのが『柳子新論』でした。大弐の思想は久坂玄瑞にも強い影響を与えています。久坂は『俟采擇録』において、「山県嘗て柳子新論十三篇を著す。……徒を集めて兵を講じ、天朝を尊みて覇者を抑ふ。其志寔にあわれむべし。竟に幕府之を判じ、不敬の至り斬に処す。ああ高山仲縄(彦九郎)・蒲生君平よりさきに既にこの人あり」と書いています。
ただ、『柳子新論』には、放伐論を容認した箇所があるという重大な問題もありました。「利害(第十二)」において、大弐は「湯王や武王の放伐は、無道の世においても有道のことをすることができたので、これらの人は天子と為り、相手の紂王や討王は賊になった。たとい臣民の地位にいる者でも、この革命の原理を善用して人民の害を除いて、人民の利益を興すことを志すならば、放伐することさえも仁と認めることができる」と書いていたのです。それでも、天皇親政の回復を説いた大弐の思想が明治維新の原動力となったことは否定できないところです。
さて、全勝寺には山県大弐記念碑も建っています。明治維新から100年、大弐没後200年に当たる昭和42(1967)年に建立されたものです。興味深いことに、建立したのは『思想の科学』グループの市井三郎・竹内好・鶴見俊輔らでした。碑の表面には近藤鎰郎による円型のレリーフ肖像が彫られ、『柳子新論』の一節が刻まれています。そして裏面には、「明治維新ノ思想的・実践的先駆者デアッタ山縣大弐ノ没後二百年ヲ記念シテ明治百年ノ年 大弐ノ命日ニコレヲ建ツ 日本人民有志」とあります。
【巻頭言】いまこそ神政維新の理想に立ち返れ
権藤成卿の思想について~権藤成卿生誕百五十周年記念祭講演要旨②~(浦辺登)
「日本の覇道」と向き合った男・口田康信─権藤成卿の思想の継承(坪内隆彦)
内なる東洋の覚醒③龜井勝一郎と村上一郎の東洋的ユートピア(山本直人)
李容九生誕百五十年―日韓合邦に殉じた志士の悲劇②(折本龍則)
戦後ナショナリズム批判①丸山眞男(小野耕資)
金子彌平―興亜の先駆者①(金子宗德)
蒲生君平『不恤緯』における対露政策提言②(小野寺崇良)
菅原兵治先生『農士道』を読む②(三浦夏南)
人類の歴史的宿命と日本・アジアの活路(原嘉陽)
【活動報告】
【巻頭言】東洋王道の大義を胸に抱け
玄洋社員・小野隆助のこと(上)(浦辺登)
高嶋辰彦『日本百年戦争宣言』─世界史の転換を目指して①(坪内隆彦)
『「親日派」朝鮮人 消された歴史』(拳骨拓史)
金子彌平―興亜の先駆者②(金子宗德)
内なる東洋の覚醒 (完)絶望からの出発(山本直人)
蒲生君平と「共に戦った」先学(小野寺崇良)
明治維新発祥地記念碑と天忠組顕彰運動(仲原和孝)
菅原兵治先生『農士道』を読む③(三浦夏南)
日本は対米自立を成し遂げよ(山口祐二郎)
これからの「民族独立」―リベラル「安保体制」批判を乗り越える(野尻誠斗)
戦後ナショナリズム批判 ② 司馬遼太郎(小野耕資)
歴史教育によって、自由と平等の価値を再構築せよ(折本龍則)
大嘗祭の深義と世界史的意義(原嘉陽)
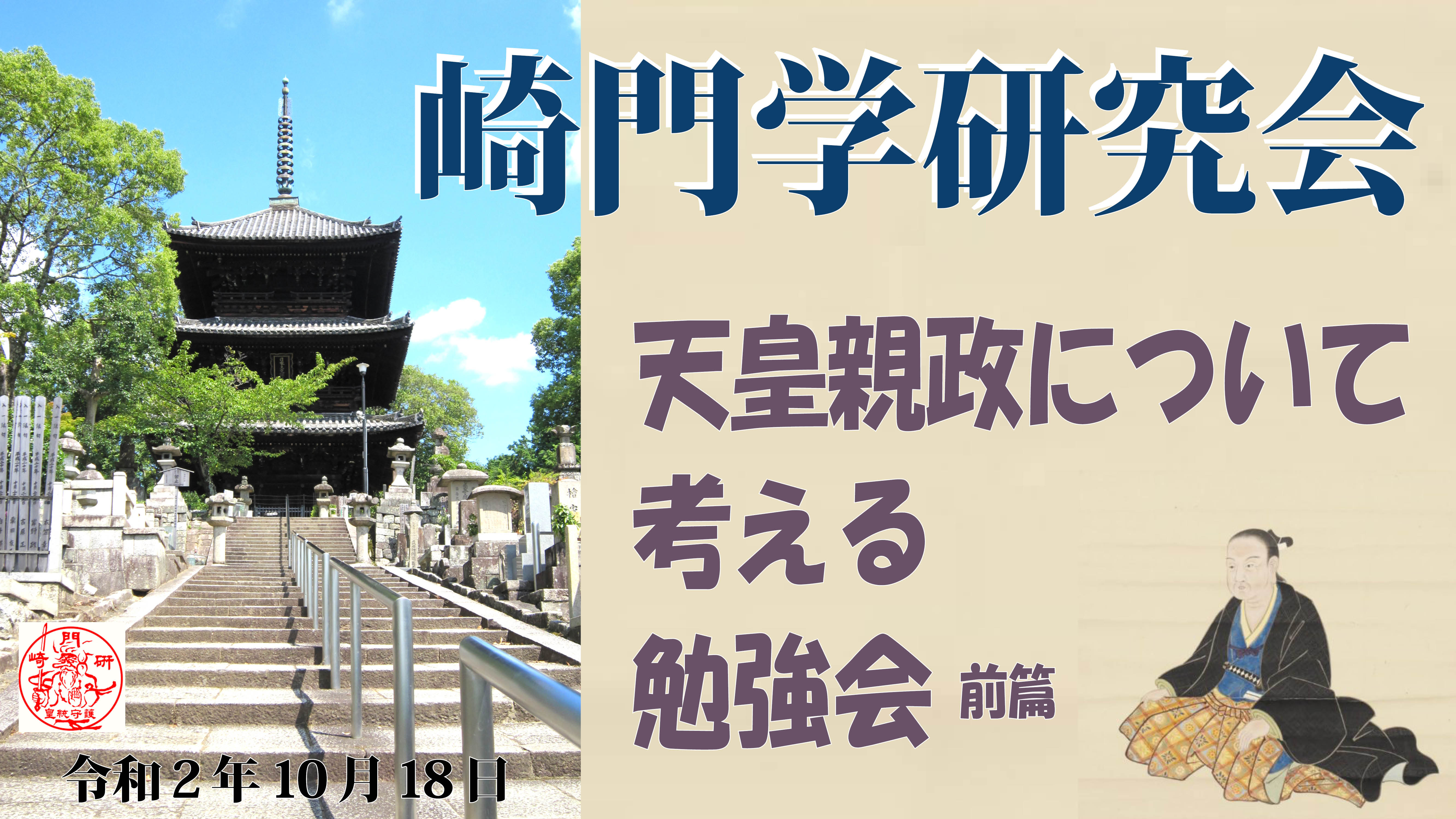
令和2年10月18日、崎門学研究会主催の「第一回天皇親政について考える勉強会」が開催されました。
動画前篇です。

皇學館大学教授の松本丘先生に、『国体文化』令和2年12月号で坪内隆彦著『徳川幕府が恐れた尾張藩』をご紹介いただきました。各章ごとに丁寧な紹介をしていただいた上、次のようにお書きいただきました。
〈本書は、尾張藩における勤皇思想を支へてゐたのは、崎門学・垂加神道を始め、国学・君山学派などの学問思想であり、「王命に依って催さるる事」といふ尊い精神は、「魂のリレー」によつて力強く継承されたと著者は述べる。これまで、同じ御三家において醸成された水戸学が、尊皇攘夷思想の発信源であつたことは語り尽くされてきたが、本書によつて、尾張学も大きな役割を果たしてゐたことが明らかになつた。
そして著者は、明治維新を薩長による権力奪取とする歴史観が近年横行してゐることに対しても、「尊皇排覇の思想は突然幕末になつて生まれたわけではない。江戸初期から思想家たちが命がけで築いた学問の発展と継承の上に、幕末の尊攘思想は花開いた。こうした精神的、思想的連続性を視野に置いた明治維新史を取り戻すべきではないのか。」と慨嘆されてゐるが、今後も著者によつて、維新に至る真の思想史が描き出されてゆくことを期待したい。〉

身の引き締まる思いです。誠に有難うございました。

令和2年11月、崎門学研究会が継続している連載「現代日本人のための垂加神道入門」(『宗教問題』)の第2回「なぜ垂加神道なのか」(折本龍則執筆)が、同誌32号に連載されました。


わが国の近代化を再検証すべき
今から八十三年前の昭和八年四月、大亜細亜建設協会(後に大亜細亜建設社)の機関誌として『大亜細亜』が発刊された。それを主導したのが、満州に王道楽土の理想を掲げた笠木良明である。
笠木の理想が、欧米列強の帝国主義に象徴される西洋覇道に対する東洋王道の理想の堅持であったことが最も重要である。私たちはいま、アジアと向き合うに当たり、西郷南州の精神敗北後の近代化路線、その路線によっ
て推進された日清戦争にまで遡って、わが国の近代史を再検証する必要があるのではなか
ろうか。

笠木は、明治二十五(一八九二)年七月二十二日、栃木県足尾町松原で生まれた。栃木県立宇都宮中学校、仙台第二高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学、大正八年七月に卒業すると、満鉄に入社、在東京東亜経済調査局に配属された。当時調査局にいた大川周明らとの出会いによって興亜思想に目覚めた笠木は、猶存社に参加する。ここで笠木は、大川のみならず、北一輝、満川亀太郎らから強い影響を受けたと考えられる。
笠木の普遍的思想の萌芽を確認する上で、大正十四年八月『日本』に発表された「愛国の唯一路」は格好の材料である。ここで笠木は頑迷な愛国者を批判し、「我等の愛国心は厳正雄渾なると共に聡明なるを要す。我等の愛国心は栄螺固陋ではなく、祖国より始めて全世界を真正調和裡に導く所の一切を包括し解決する魂」だと書いている。満川と同様に、彼は興亜の前提としての日本改造を重く見て、日本は「まづ第一に道義的に資格ある自国自身の正義化を大眼目として活動すべき」と説いていた。
さて、笠木は昭和四年四月に東亜経済調査局から大連の満鉄本社に転勤することになった。笠木は満州情勢が動き出す中で、大連を中心とする同志を集めて議論を開始した。
一方、笠木と盟友関係を築くことになる中野琥逸は、京大時代に猶存社に参加し、行地社時代には関西行地社を結成、さらに猶興学会を結成して同志の輪を広げていた。昭和二年に奉天で弁護士を開業、やがてここは満州を志す青年たちの拠点となった。中野は、同志の庭川辰雄、江藤夏雄らとともに、満蒙に道義国家を建設する構想を抱き、奉天特務機関や関東軍と連絡をとるようになっていた。
もともと中野と面識のあった笠木は両グループの交流を進め、昭和五年秋一大結集へと向かう。十一月のある日、大連の笠木仮寓の床の間に飾ってあった書幅「独座大雄峯」に注目が集まった。「独座大雄峯」は、唐代の禅師百丈壊海が、「有り難いこととはどういうことですか」と問われた際に発した言葉で、「自分が一人、この山に座っている事ほどありがたい事はない」ほどの意味である。この書に因んで、笠木・中野連合は「大雄峯会」と名付けられた。
昭和六年九月十八日に満州事変が勃発すると、大雄峯会周辺は緊迫度を増していく。事変からちょうど一カ月後の十月十八日、大雄峯会は奉天の妙心寺で総会を開き、板垣征四郎、石原莞爾ら関東軍幕僚らと対面する。石原は「満蒙問題の解決はもはや言論や外交では不可能であるから、満鉄沿線を対象として理想境域を建設することによって実績で証明するよりほかにとるべき方法はない」と語り、大雄峯会に協力を求めてきた。笠木らは石原の提案に賛同し、自治指導部設置に向けた方針策定を急いだ。そして、大雄峯会と満州青年連盟の案を統合した「地方自治指導部設置要項」が決定され、十一月一日自治指導部が発足した。大雄峯会、満州青年連盟からそれぞれ七名ずつが参加し、笠木は連絡課長に、中野は顧問に就任した。 続きを読む 坪内隆彦「笠木良明と『大亜細亜』」(『大亜細亜』創刊号、平成28年6月30日) →

令和2年8月、崎門学研究会は『宗教問題』で「現代日本人のための垂加神道入門」と題する連載を開始させて頂きました。

・初回(第31号、令和2年8月)
小野耕資「垂加神道とは何か」
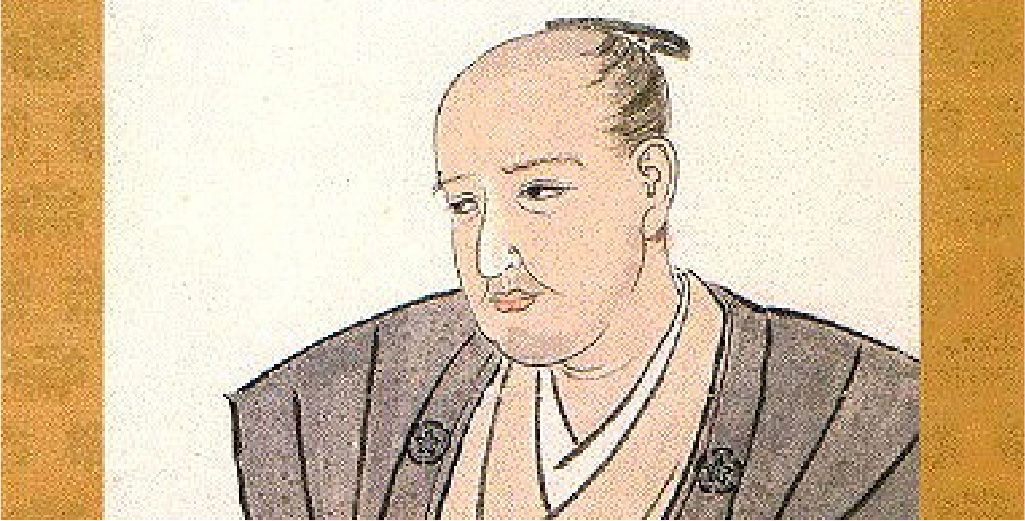
「蒲生君平を研究している」と話すと、相手の顔には疑問符が浮かぶ様子が、ありありとみてとれる…。そうした機会に出くわすことが多い。その際の紹介文言として用いる「前方後円墳の名付け親」は、思ったより有効である。昨年は、生誕二百五十年を迎えた蒲生君平の記念事業として、栃木県の助成を受けた様々な行事が開催されていた。事業内容に、「古墳を巡るウォーキング大会」「埴輪づくり体験」などが並ぶ様子に、その肩書が便利に使いまわされていることがわかる。
かたや、「寛政の三奇人」として、相手が日本史履修者であることを祈りつつ話をすると、「三奇人」としての肩書の君平の印象は、「天皇陵関連の尊王論者」になるかもしれない。それでも、他の二人よりは知名度が低いことは否めない。
寛政の三奇人は「対外的危機、天皇という江戸時代後期のキーワードを一歩早すぎて唱えた人物」(藤田覚『幕末の天皇』)との評価があるが、対外的危機に敏感に反応した人物としての側面で評価すれば、君平は三奇人の中でも目立つ立ち位置に再び位置づけられるのではないだろうか。
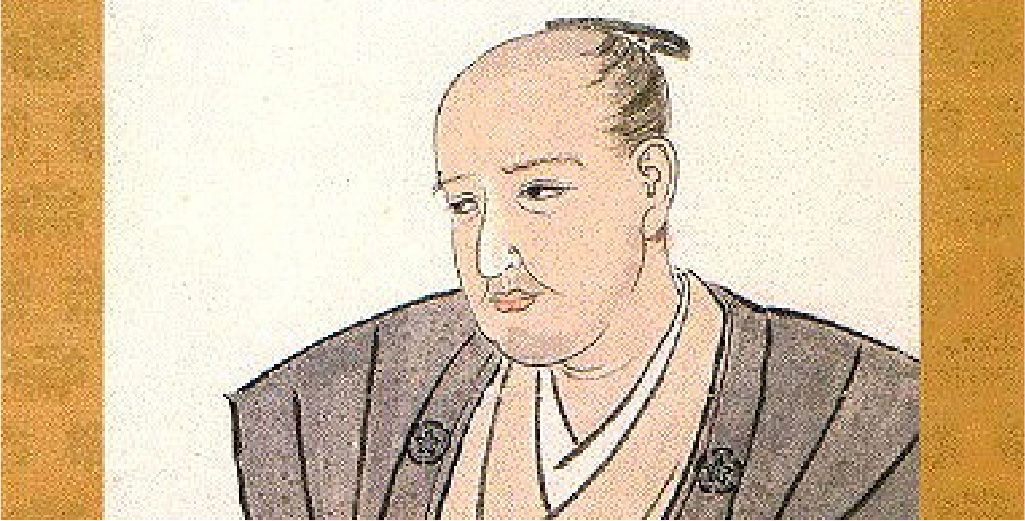
君平の著作「形勢論」
文化四年(一八〇七)六月の文化露寇(フヴォストフ事件)が発生すると、君平がその際に『不恤緯』を記したことは知られるところだろう。
井野辺茂雄氏は、「君平は、対外策を完備するには、尊王の実を挙げるのが急務であると論じた」、「尊王思想と対外思想との結合を示したのは、実に君平を以て嚆矢とする」と指摘する(『維新前史の研究』)。
彼の対外思想をどのようにとらえるべきか。彼の対外論を直接に知る手立ては、三奇人の他の二人よりも少ない。
前述の『不恤緯』の内容紹介は既出が多いであろうから、また別な著作を見てみたい。「形勢論(中興策第五)」を参考にしたい。「形勢論」は約千五百字の短文で、「中興策」という書物の一篇であるとされるが、成立年も不明で、その他の篇は現存が確認できない。「 『不恤緯』では国防に触れてはいるが、具体的な説はない(中略)本論には『不恤緯』では触れていない、具体策が論ぜられている」との雨宮義人氏の解説(『蒲生君平』)の通りで、こちらではさらに具体的な政策を述べている。管見の限りにおいて、現在「形勢論」を取り上げているのは雨宮氏以外に池田泰信氏、野口武彦氏らが見受けられる。しかし、雨宮氏の著作では一部を引用し、紹介しているにすぎない。
主題として君平の対外観を取り上げたものとしては唯一と思われる池田氏の論文(「対外政策に対する蒲生君平の意見」)では、『不恤緯』と「形勢論」をもとにして、君平の対外論を「外交方針確立のための国内政治の改良」と「相手国たる外国の歴史地理は勿論政治風習に至るまでの状況をよく理解すること」と二つの方向性があることを紹介している。池田氏は君平の主張をもって「換言すれば外でもない国家総動員体制の編成がそれである」など、昭和十四年当時の時局に合わせた論理を展開している点も見受けられる。
次に野口氏は『江戸の兵学思想』にて、「君平の兵学思考がいちばん要点的にまとめられている」ものとして「形勢論」を挙げ、全体的に解説を加えている。
興味深い点は、「君平は、兵学上のみごとな一家言を残して」おり、「いわば地政学的なヴィジョンを構成している」と、地政学的な観点を持ったものと評している点だろう。「形勢論」は元は漢文であり、野口氏の書き下しと解説を元にこれを見ていきたいと思う。
まず、全体は三つに分けられる。
一つ目は「海国形勢論」。「天下を治むるは、先づ其の形勢を知るより要なるは莫し」より始まるこの文章では、
神州、環るに巨海を以てし、西東に長く、南北に短し。海に西南に裨し、東北に山たり。(略)夫れ東西南北、海に岸す。而して千里の地、以て旦に発して夕臻るべし。百万の軍、其の数多しと雖ども、未だ始め隻牛・匹馬を汗せしめず。
と、国家の地形や特徴を知る重要性と、島国日本の特徴を述べる。ここには、林子平からの影響を感じさせていることは言うまでもない。
第二に「大艦建造論」。
夫れ海国の用は何をか貴ぶ。曰く、艦を先と為す。今、宇内の大艦製、北慮精と為す。而して、吾邦の製尤も麁悪。(中略)然れば則ち、方今の急務は、宜しく四方の瀕海枢要の地を巡覧し、以て都督府を四辺に置き、天下の諸侯に命じて、法を彼の最も精なる者に取り、以て大いに戦艦を製すべし。
大船建造禁止の日本の現状は残念ながら「麁悪」であった。だからこそ、対外防衛のための戦艦建設が急務だと言いたかったのだろう。
ほかに、その国々の大小に合わせて定数を定め、各都督府に所属させることも加えている。また、有事に各戦艦を軍事力として用いるだけでなく、平時の参勤交代や年貢米輸送なども全て海運を用いて、その利益も防衛費に充てるという事も提示している。
これを野口氏は「諸大名がすべて船会社、回漕業者兼海軍の保有者になるプランにひとし」く、諸大名に権利を集中するため、「一面から言えば、重商主義国家論」でもあるとしている。
第三に「対露防衛論」。この段階ではロシア来寇の危険性を述べている点からも、文化露寇以前であると考えられる。また、大陸国家ロシアを「水戦に長ず」と評している点での間違いが指摘されるが、
今や、東南尽く諸蕃を呑み、以て境を 神州に接し、余を以て其の兵勢を度せば、則ち強大、元寇に減ぜざらん。(中略)是れ、其の復た伊勢の神風を怙むべからざること、智者を竢たずして知るべし
と、かなりの強大な軍事力を持つ相手として、現状では「伊勢の神風」に頼むほかない…とも言う。だからこそ、彼の理想は海軍国家として、整備を進めることだった。
さらに、君平は地政学的な観点からも、対ロシアの利点を考察している。
地曠く、人稀なり。殻を生ずること固より少し。西南な諸夷に界して、戦艦用ふべからず。且つ、其の東北隅、率ね是れ曠莫不毛の郷。其の精兵独だ西南の間に在りて、其の地諸夷と接す。則ち、其の守禦に徹して、以て力を吾が神州に専らにすべからず
ここで、ロシア極東部の人口の少なさや食料が多く取れない事情を述べ、こちら側の軍事力整備が整うことでの防禦を唱えていた。
君平の評価
これら、君平の対外危機への敏感な反応は、どのように受け止められたか。
『不恤緯』提出に関して、文化四年七月三日付の書簡にて木村謙次から会沢正志斎へと「蒲生君蔵には御出合被成候事可有之候、此節御なだめ、妄りに諷諫の語をなし、罪せられぬやうにいたし候様、何分致声候様御申聞、御なだめ被下候」と書簡が送られている通り、こうした行動が「犯萬死不暇自顧」(『不恤緯』上書)との言葉に相応しい、危険を伴うものであったということが言えるのだろう。
君平には数名の門人がいたことが知られるが、その一人である大友直枝は、『不恤緯』に関して、「実に慷概之士ニ御座候、北狄の騒ニも上書して志しを述候、御取揚なく差返され候得共、大ニ流布仕候而其名高く候」と記している。大友は秋田藩の波宇志別神社社家であり、本居大平門の後、君平門人、さらに平田篤胤にも入門している国学者である。彼と君平、篤胤の関係性には未だ考察の余地があろう。
本題に戻すと、君平の生前に出版された『山陵志』、『職官志』(第一巻のみ)と違い、『不恤緯』は少なくとも君平の歿後五十年は活字化されていない。それでも「大ニ流布」したとの文言を見るにつけ、文化露寇に対しての対外強硬論は、その影響力と君平の知名度向上に大きく貢献したのではないかと考えるところである。その考察を支える一つに、全国各地に写本が伝播している事実がある。現在の筆者の調査では、宇都宮から遠く離れた久留米藩士松岡家、椛島家(久留米市立図書館蔵)など全国に約二十の写本があることが確認できている。中でも注目されるべき写本として、高知城歴史博物館蔵の写本奥書には書写者である徳永千規による天保期の一文が記されている。
秀實ナンスレモノソ一布衣ノミ其所レ論患ノ大ナルモノニシテ就中羯奴 吾皇国ヲ窺フニイタリテハカゝル所最大ナリ而其取術実ニ千載愉快ノ策トイフヘクシテ所謂先二天下之患一覇府ヲ警ス其才人ニ超越シ其王室ヲ尊ヒ名実ヲ正クシ不虞ノ謀ヲ備フ実ニ忠誼傑出ノ壮士ト可謂矣
この文章を記している徳永は、文化元年に生まれ鹿持雅澄らに学び、藩校致道館教授を務めた人物である。彼の『靖献遺言』講義は優れていた、と今に伝わるほどであるから、彼の思想は言うまでもない。これまで表に出ていなかった資料だが、土佐藩へも影響を広めていたことを示す点でも、また、対外危機がより一層強まる以前の段階での評価としても貴重である。
君平の著作が幕末でも読まれ、そのうち『不恤緯』は安政五年の写本を元に、明治元年に松下村塾版で出版がなされる。だが、幕末までの影響力という範囲だけではなく、近代以降の影響力も今後検討してゆくべきだろう。
例えば、先に挙げた『不恤緯』(松下村塾版)と『今書』が収録された明治四十四年の叢書には、その掲載にあたって「是れ、乃木大将の推奨に依る所多し」(『国民道徳叢書』)との有馬祐政氏による一文がある。松下村塾版の『不恤緯』が乃木大将へも繋がってゆくと考えると、彼の影響力のさらにその壮大さを感じさせる。もう少し時間をかけて調べてゆきたい。
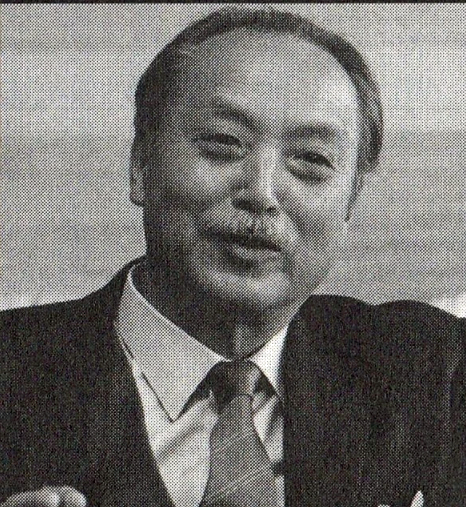
■津久井龍雄の敗戦と再起
昭和二十年八月十五日、わが国は戦争に敗れた。戦前から国家社会主義者として活動していた津久井龍雄は、終戦の詔勅を疎開先の群馬県で聞いた。
「聴いているうちに涙がでてきたが、それはどういう種類の涙だったのだろうか。一緒にそれを聴いて涙ぐんでいる妻や、その家の人たちの姿をみて、私はひどくみじめな気持ちになり、つとその場を去って外へ出てしまった」(『私の昭和史』)。
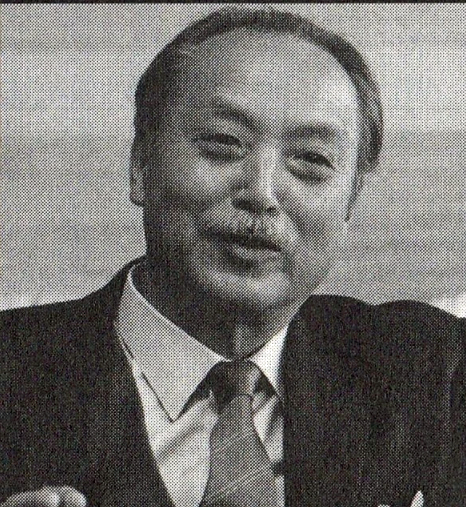
その後も津久井の元には大東塾の自刃や尊攘同志会の愛宕山事件、蓑田胸喜の縊死などさまざまなニュースが飛び込んでくる。それらにハッと胸をつかれる思いがして、再び運動に取り組むこととなった。
「敗戦を食い物にしてきた一部の政治家や役人や資本家や言論人に対して大いに化物退治の一戦を挑みたいと思っている。戦争を喰いものにした奴も憎いが、敗戦を喰いものにした奴はなおさら憎い」(「我が再発足の弁」)。
そんな津久井が昭和二十一年に刊行した三十ページほどの小冊子がある。『救国自治の提唱』と名付けられたこの冊子は、敗戦を「新たな建国」と捉え、社会主義の考え方を一部取り入れた一君万民の道義国家建設を訴えたものであった。それは搾取なき新日本の建設でなくてはならず、日本の国体精神による維新でなくてはならなかった。権力と官治の誘惑を断ち切り、民族の共同団結を目指した農本小国家を訴えた。天皇を中心とした家族国家であるだけでなく、工業大国でないいわば小日本主義に経った共存共栄の実現であった。
■「魂なき繁栄」を続ける戦後社会と津久井の絶望
しかし戦後のわが国はこうした津久井の思いとは裏腹に、対米従属のもとでの反共前線基地として工業化、経済大国化していく。復興と言えば聞こえはいいが、それは「魂なき繁栄」でしかなかった。生活は便利になったが、津久井の理想とする国家とは程遠くなっていく祖国の姿がそこにはあった。そんな中で津久井は中共に注目していく。中国もソ連も「官治」的な強権国家でしかないことを津久井は見抜いており、冷静な分析もしているが、それでも昭和三十年の中国訪問は津久井に刺激を与えた。
「新中国では、総理大臣でも洋車の車夫でも、お互に同志と呼び合っている。考えてみればそれが本当である。同じ国民どころか、同じ東京に住み、同じ区や町に住みながら、相視ること全く路傍の人の如くであるというのは、考えてみれば随分と天理にも背いたことである。そういう人間が、世界国家だの人類愛だのといっても、ちょっとまじめにはうけとりかねる。
日本には同胞という言葉があり、これをはらからと呼ぶとなお意味深長になる。同じ腹から生まれたもの、すなわち兄弟姉妹の意であるが、全国民は同胞であり、同胞は愛し励まし扶け合わなければならないものにきまっている。しかし事実はまったく反対である。新中国の人たちが、互いに同志と呼び合うように、われわれ日本国民が、お互にはらからと呼び合う日は果していつの日に来るのだろうか」(『右翼開眼―中共と日本』)。
津久井が中国に見たものは、素朴で温かい人間関係、相互扶助の共同国家であった。それは中国のようになりたいというよりは、かつての日本が持っていたにも関わらず戦後日本が失ってしまった何かを、中国に行くことで改めて実感したのであろう。津久井に限らず、いわゆる右翼が理想としてきた農本的世界観には、こうした側面が濃厚に潜んでいる。
津久井は高齢になっても衰えず言論活動を展開していくが、最晩年は右翼にすら絶望し、「敗戦で右翼は終わった」と口にするようになっていった。あまりにも目指すべき国と現状の祖国とが食い違っているためについていけなかったのかもしれない。
■敗戦に潜む欺瞞
本稿は津久井論ではない。津久井に関しては折本龍則氏の原稿をご参照いただきたい。わたしが述べたかったことは、戦後社会にはある欺瞞がひそんでいるということだ。それは明治時代から始まったものであるが、戦後より一層加速された。一言で言えば古き良きものを切り捨て、近代化していくことに対する痛みを失ってしまったのである。自らの文化や伝統に対する自信や頑なさを失い、ただ便利になっていくことをよかったよかったと喜んでいるだけなのである。反左翼はあっても理想がない。世界観がないのである。
いまの日本では「同胞」と呼び合うことができない。そんな中で唱えられる愛国心とは何だろうか。「愛政府心」と見分けのつかない、権力者や既得権益者に都合の良いだけの何かではないだろうか。
■同胞と呼び合える国家へ
石川三四郎『農本主義と土民思想』には次のような一節がある。
「土民は土の子だ。併しそれは必ずしも農民ではない。鍛冶屋も土民なら、大工も左官も土民だ。地球を耕し――単に農に非ず――天地の大芸術に参加する労働者はみな土民だ。土民とは土着の民衆といふことだ。鍬を持つ農民でも、政治的野心を持つたり、他人を利用して自己の利慾や虚栄心を満足するものは土民ではない。土民の最大の理想は所謂立身出世的成功ではなくて、自分と同胞との自由である。平等の自由である。」
土着を重んじる石川三四郎の考えはいろいろな意味で興味深い。そもそも日本は豊蘆原瑞穂国と言い、葦も稲も泥の中で育つ植物だ。古き日本は泥の国であり、泥は生命が萌え出ずる温床となるものだ。そして日本神話からも明らかなように、その蓄積した泥からは八百万の神々も生まれてくるのである。日本の泥の文化はエネルギーが内に堆積していくところに強みがある。こうした世界観はアジア地域にある程度共有されているものだ。津久井が中国で思い起こしたものは、決してソ連的共産主義ではない。むしろそうした近代文明的表皮をはぎ取った中にあるアジア的共同性、土着性を見て取ったのである。それは津久井の敗戦後の決意とも重なってくる。
いまの日本人は関係が希薄化し、カネでしか結びつけない関係が世を支配している。しかしそこに生き甲斐はあるか。人々の居場所はあるのだろうか。同胞と呼び合える国家へ。地に足をつけた土着的国家へ。新時代の目指すべき先はここにあるのではないか。
(小野耕資)
道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)