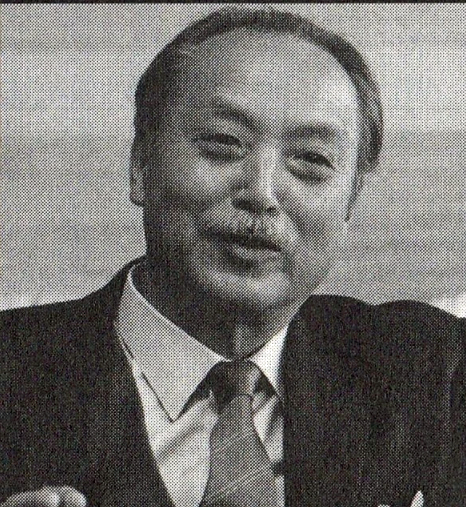■津久井龍雄の敗戦と再起
昭和二十年八月十五日、わが国は戦争に敗れた。戦前から国家社会主義者として活動していた津久井龍雄は、終戦の詔勅を疎開先の群馬県で聞いた。
「聴いているうちに涙がでてきたが、それはどういう種類の涙だったのだろうか。一緒にそれを聴いて涙ぐんでいる妻や、その家の人たちの姿をみて、私はひどくみじめな気持ちになり、つとその場を去って外へ出てしまった」(『私の昭和史』)。
その後も津久井の元には大東塾の自刃や尊攘同志会の愛宕山事件、蓑田胸喜の縊死などさまざまなニュースが飛び込んでくる。それらにハッと胸をつかれる思いがして、再び運動に取り組むこととなった。
「敗戦を食い物にしてきた一部の政治家や役人や資本家や言論人に対して大いに化物退治の一戦を挑みたいと思っている。戦争を喰いものにした奴も憎いが、敗戦を喰いものにした奴はなおさら憎い」(「我が再発足の弁」)。
そんな津久井が昭和二十一年に刊行した三十ページほどの小冊子がある。『救国自治の提唱』と名付けられたこの冊子は、敗戦を「新たな建国」と捉え、社会主義の考え方を一部取り入れた一君万民の道義国家建設を訴えたものであった。それは搾取なき新日本の建設でなくてはならず、日本の国体精神による維新でなくてはならなかった。権力と官治の誘惑を断ち切り、民族の共同団結を目指した農本小国家を訴えた。天皇を中心とした家族国家であるだけでなく、工業大国でないいわば小日本主義に経った共存共栄の実現であった。
■「魂なき繁栄」を続ける戦後社会と津久井の絶望
しかし戦後のわが国はこうした津久井の思いとは裏腹に、対米従属のもとでの反共前線基地として工業化、経済大国化していく。復興と言えば聞こえはいいが、それは「魂なき繁栄」でしかなかった。生活は便利になったが、津久井の理想とする国家とは程遠くなっていく祖国の姿がそこにはあった。そんな中で津久井は中共に注目していく。中国もソ連も「官治」的な強権国家でしかないことを津久井は見抜いており、冷静な分析もしているが、それでも昭和三十年の中国訪問は津久井に刺激を与えた。
「新中国では、総理大臣でも洋車の車夫でも、お互に同志と呼び合っている。考えてみればそれが本当である。同じ国民どころか、同じ東京に住み、同じ区や町に住みながら、相視ること全く路傍の人の如くであるというのは、考えてみれば随分と天理にも背いたことである。そういう人間が、世界国家だの人類愛だのといっても、ちょっとまじめにはうけとりかねる。
日本には同胞という言葉があり、これをはらからと呼ぶとなお意味深長になる。同じ腹から生まれたもの、すなわち兄弟姉妹の意であるが、全国民は同胞であり、同胞は愛し励まし扶け合わなければならないものにきまっている。しかし事実はまったく反対である。新中国の人たちが、互いに同志と呼び合うように、われわれ日本国民が、お互にはらからと呼び合う日は果していつの日に来るのだろうか」(『右翼開眼―中共と日本』)。
津久井が中国に見たものは、素朴で温かい人間関係、相互扶助の共同国家であった。それは中国のようになりたいというよりは、かつての日本が持っていたにも関わらず戦後日本が失ってしまった何かを、中国に行くことで改めて実感したのであろう。津久井に限らず、いわゆる右翼が理想としてきた農本的世界観には、こうした側面が濃厚に潜んでいる。
津久井は高齢になっても衰えず言論活動を展開していくが、最晩年は右翼にすら絶望し、「敗戦で右翼は終わった」と口にするようになっていった。あまりにも目指すべき国と現状の祖国とが食い違っているためについていけなかったのかもしれない。
■敗戦に潜む欺瞞
本稿は津久井論ではない。津久井に関しては折本龍則氏の原稿をご参照いただきたい。わたしが述べたかったことは、戦後社会にはある欺瞞がひそんでいるということだ。それは明治時代から始まったものであるが、戦後より一層加速された。一言で言えば古き良きものを切り捨て、近代化していくことに対する痛みを失ってしまったのである。自らの文化や伝統に対する自信や頑なさを失い、ただ便利になっていくことをよかったよかったと喜んでいるだけなのである。反左翼はあっても理想がない。世界観がないのである。
いまの日本では「同胞」と呼び合うことができない。そんな中で唱えられる愛国心とは何だろうか。「愛政府心」と見分けのつかない、権力者や既得権益者に都合の良いだけの何かではないだろうか。
■同胞と呼び合える国家へ
石川三四郎『農本主義と土民思想』には次のような一節がある。
「土民は土の子だ。併しそれは必ずしも農民ではない。鍛冶屋も土民なら、大工も左官も土民だ。地球を耕し――単に農に非ず――天地の大芸術に参加する労働者はみな土民だ。土民とは土着の民衆といふことだ。鍬を持つ農民でも、政治的野心を持つたり、他人を利用して自己の利慾や虚栄心を満足するものは土民ではない。土民の最大の理想は所謂立身出世的成功ではなくて、自分と同胞との自由である。平等の自由である。」
土着を重んじる石川三四郎の考えはいろいろな意味で興味深い。そもそも日本は豊蘆原瑞穂国と言い、葦も稲も泥の中で育つ植物だ。古き日本は泥の国であり、泥は生命が萌え出ずる温床となるものだ。そして日本神話からも明らかなように、その蓄積した泥からは八百万の神々も生まれてくるのである。日本の泥の文化はエネルギーが内に堆積していくところに強みがある。こうした世界観はアジア地域にある程度共有されているものだ。津久井が中国で思い起こしたものは、決してソ連的共産主義ではない。むしろそうした近代文明的表皮をはぎ取った中にあるアジア的共同性、土着性を見て取ったのである。それは津久井の敗戦後の決意とも重なってくる。
いまの日本人は関係が希薄化し、カネでしか結びつけない関係が世を支配している。しかしそこに生き甲斐はあるか。人々の居場所はあるのだろうか。同胞と呼び合える国家へ。地に足をつけた土着的国家へ。新時代の目指すべき先はここにあるのではないか。
(小野耕資)