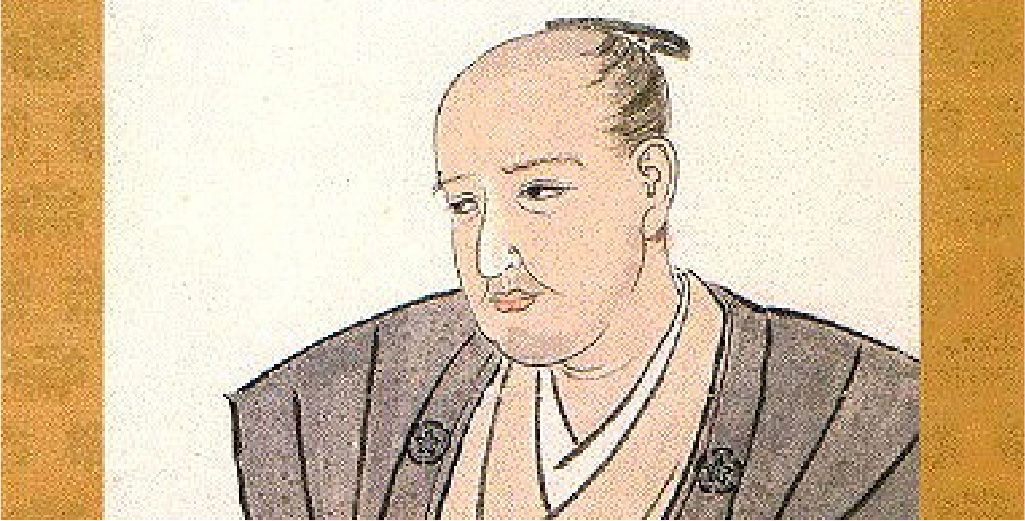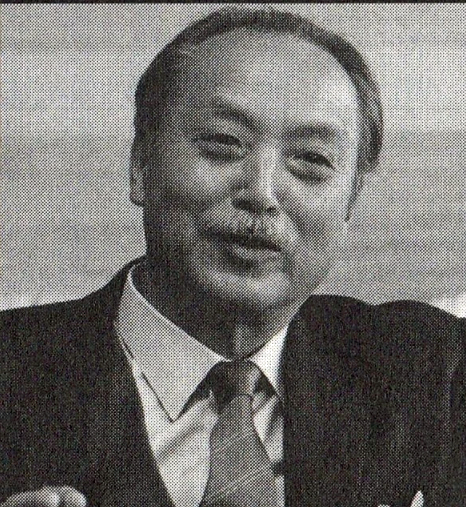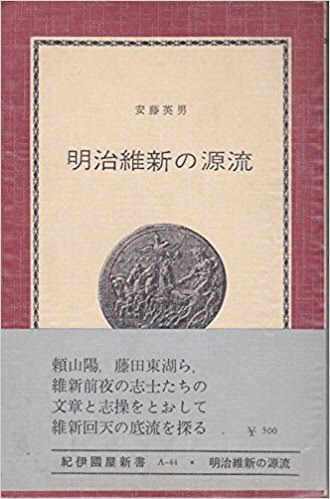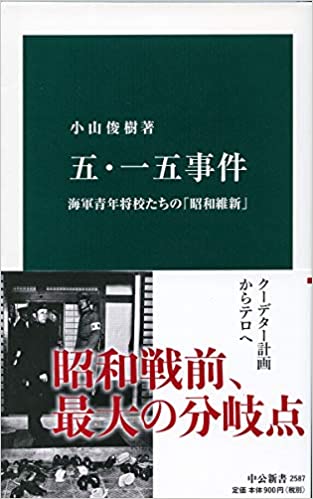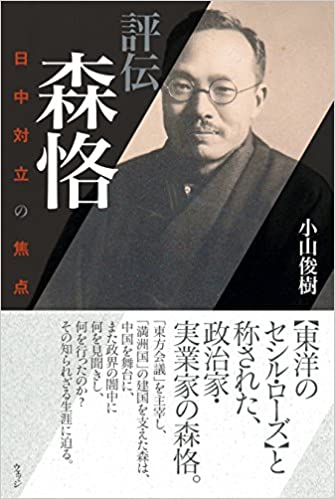わが国の近代化を再検証すべき
今から八十三年前の昭和八年四月、大亜細亜建設協会(後に大亜細亜建設社)の機関誌として『大亜細亜』が発刊された。それを主導したのが、満州に王道楽土の理想を掲げた笠木良明である。
笠木の理想が、欧米列強の帝国主義に象徴される西洋覇道に対する東洋王道の理想の堅持であったことが最も重要である。私たちはいま、アジアと向き合うに当たり、西郷南州の精神敗北後の近代化路線、その路線によっ
て推進された日清戦争にまで遡って、わが国の近代史を再検証する必要があるのではなか
ろうか。

笠木は、明治二十五(一八九二)年七月二十二日、栃木県足尾町松原で生まれた。栃木県立宇都宮中学校、仙台第二高等学校を経て東京帝国大学法学部に入学、大正八年七月に卒業すると、満鉄に入社、在東京東亜経済調査局に配属された。当時調査局にいた大川周明らとの出会いによって興亜思想に目覚めた笠木は、猶存社に参加する。ここで笠木は、大川のみならず、北一輝、満川亀太郎らから強い影響を受けたと考えられる。
笠木の普遍的思想の萌芽を確認する上で、大正十四年八月『日本』に発表された「愛国の唯一路」は格好の材料である。ここで笠木は頑迷な愛国者を批判し、「我等の愛国心は厳正雄渾なると共に聡明なるを要す。我等の愛国心は栄螺固陋ではなく、祖国より始めて全世界を真正調和裡に導く所の一切を包括し解決する魂」だと書いている。満川と同様に、彼は興亜の前提としての日本改造を重く見て、日本は「まづ第一に道義的に資格ある自国自身の正義化を大眼目として活動すべき」と説いていた。
さて、笠木は昭和四年四月に東亜経済調査局から大連の満鉄本社に転勤することになった。笠木は満州情勢が動き出す中で、大連を中心とする同志を集めて議論を開始した。
一方、笠木と盟友関係を築くことになる中野琥逸は、京大時代に猶存社に参加し、行地社時代には関西行地社を結成、さらに猶興学会を結成して同志の輪を広げていた。昭和二年に奉天で弁護士を開業、やがてここは満州を志す青年たちの拠点となった。中野は、同志の庭川辰雄、江藤夏雄らとともに、満蒙に道義国家を建設する構想を抱き、奉天特務機関や関東軍と連絡をとるようになっていた。
もともと中野と面識のあった笠木は両グループの交流を進め、昭和五年秋一大結集へと向かう。十一月のある日、大連の笠木仮寓の床の間に飾ってあった書幅「独座大雄峯」に注目が集まった。「独座大雄峯」は、唐代の禅師百丈壊海が、「有り難いこととはどういうことですか」と問われた際に発した言葉で、「自分が一人、この山に座っている事ほどありがたい事はない」ほどの意味である。この書に因んで、笠木・中野連合は「大雄峯会」と名付けられた。
昭和六年九月十八日に満州事変が勃発すると、大雄峯会周辺は緊迫度を増していく。事変からちょうど一カ月後の十月十八日、大雄峯会は奉天の妙心寺で総会を開き、板垣征四郎、石原莞爾ら関東軍幕僚らと対面する。石原は「満蒙問題の解決はもはや言論や外交では不可能であるから、満鉄沿線を対象として理想境域を建設することによって実績で証明するよりほかにとるべき方法はない」と語り、大雄峯会に協力を求めてきた。笠木らは石原の提案に賛同し、自治指導部設置に向けた方針策定を急いだ。そして、大雄峯会と満州青年連盟の案を統合した「地方自治指導部設置要項」が決定され、十一月一日自治指導部が発足した。大雄峯会、満州青年連盟からそれぞれ七名ずつが参加し、笠木は連絡課長に、中野は顧問に就任した。 続きを読む 坪内隆彦「笠木良明と『大亜細亜』」(『大亜細亜』創刊号、平成28年6月30日) →

「蒲生君平を研究している」と話すと、相手の顔には疑問符が浮かぶ様子が、ありありとみてとれる…。そうした機会に出くわすことが多い。その際の紹介文言として用いる「前方後円墳の名付け親」は、思ったより有効である。昨年は、生誕二百五十年を迎えた蒲生君平の記念事業として、栃木県の助成を受けた様々な行事が開催されていた。事業内容に、「古墳を巡るウォーキング大会」「埴輪づくり体験」などが並ぶ様子に、その肩書が便利に使いまわされていることがわかる。
かたや、「寛政の三奇人」として、相手が日本史履修者であることを祈りつつ話をすると、「三奇人」としての肩書の君平の印象は、「天皇陵関連の尊王論者」になるかもしれない。それでも、他の二人よりは知名度が低いことは否めない。
寛政の三奇人は「対外的危機、天皇という江戸時代後期のキーワードを一歩早すぎて唱えた人物」(藤田覚『幕末の天皇』)との評価があるが、対外的危機に敏感に反応した人物としての側面で評価すれば、君平は三奇人の中でも目立つ立ち位置に再び位置づけられるのではないだろうか。
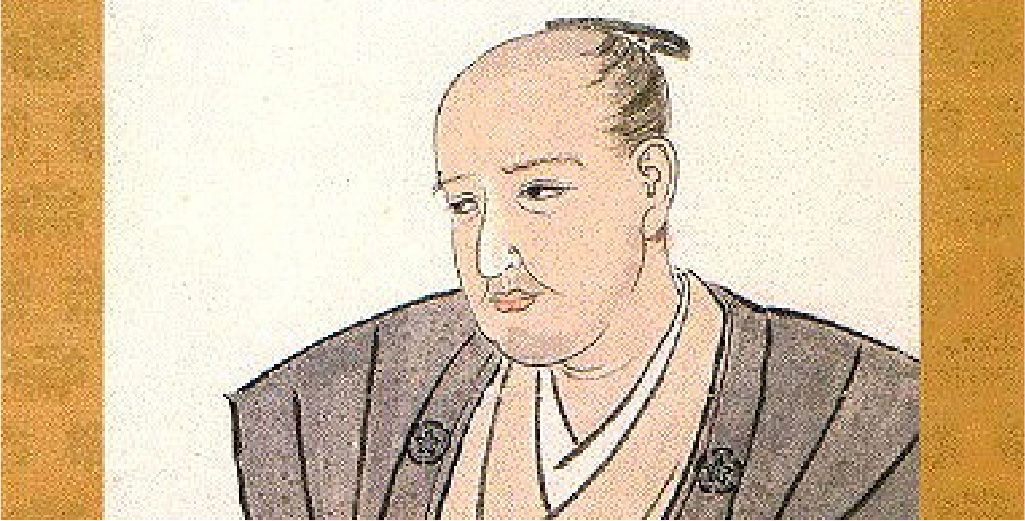
君平の著作「形勢論」
文化四年(一八〇七)六月の文化露寇(フヴォストフ事件)が発生すると、君平がその際に『不恤緯』を記したことは知られるところだろう。
井野辺茂雄氏は、「君平は、対外策を完備するには、尊王の実を挙げるのが急務であると論じた」、「尊王思想と対外思想との結合を示したのは、実に君平を以て嚆矢とする」と指摘する(『維新前史の研究』)。
彼の対外思想をどのようにとらえるべきか。彼の対外論を直接に知る手立ては、三奇人の他の二人よりも少ない。
前述の『不恤緯』の内容紹介は既出が多いであろうから、また別な著作を見てみたい。「形勢論(中興策第五)」を参考にしたい。「形勢論」は約千五百字の短文で、「中興策」という書物の一篇であるとされるが、成立年も不明で、その他の篇は現存が確認できない。「 『不恤緯』では国防に触れてはいるが、具体的な説はない(中略)本論には『不恤緯』では触れていない、具体策が論ぜられている」との雨宮義人氏の解説(『蒲生君平』)の通りで、こちらではさらに具体的な政策を述べている。管見の限りにおいて、現在「形勢論」を取り上げているのは雨宮氏以外に池田泰信氏、野口武彦氏らが見受けられる。しかし、雨宮氏の著作では一部を引用し、紹介しているにすぎない。
主題として君平の対外観を取り上げたものとしては唯一と思われる池田氏の論文(「対外政策に対する蒲生君平の意見」)では、『不恤緯』と「形勢論」をもとにして、君平の対外論を「外交方針確立のための国内政治の改良」と「相手国たる外国の歴史地理は勿論政治風習に至るまでの状況をよく理解すること」と二つの方向性があることを紹介している。池田氏は君平の主張をもって「換言すれば外でもない国家総動員体制の編成がそれである」など、昭和十四年当時の時局に合わせた論理を展開している点も見受けられる。
次に野口氏は『江戸の兵学思想』にて、「君平の兵学思考がいちばん要点的にまとめられている」ものとして「形勢論」を挙げ、全体的に解説を加えている。
興味深い点は、「君平は、兵学上のみごとな一家言を残して」おり、「いわば地政学的なヴィジョンを構成している」と、地政学的な観点を持ったものと評している点だろう。「形勢論」は元は漢文であり、野口氏の書き下しと解説を元にこれを見ていきたいと思う。
まず、全体は三つに分けられる。
一つ目は「海国形勢論」。「天下を治むるは、先づ其の形勢を知るより要なるは莫し」より始まるこの文章では、
神州、環るに巨海を以てし、西東に長く、南北に短し。海に西南に裨し、東北に山たり。(略)夫れ東西南北、海に岸す。而して千里の地、以て旦に発して夕臻るべし。百万の軍、其の数多しと雖ども、未だ始め隻牛・匹馬を汗せしめず。
と、国家の地形や特徴を知る重要性と、島国日本の特徴を述べる。ここには、林子平からの影響を感じさせていることは言うまでもない。
第二に「大艦建造論」。
夫れ海国の用は何をか貴ぶ。曰く、艦を先と為す。今、宇内の大艦製、北慮精と為す。而して、吾邦の製尤も麁悪。(中略)然れば則ち、方今の急務は、宜しく四方の瀕海枢要の地を巡覧し、以て都督府を四辺に置き、天下の諸侯に命じて、法を彼の最も精なる者に取り、以て大いに戦艦を製すべし。
大船建造禁止の日本の現状は残念ながら「麁悪」であった。だからこそ、対外防衛のための戦艦建設が急務だと言いたかったのだろう。
ほかに、その国々の大小に合わせて定数を定め、各都督府に所属させることも加えている。また、有事に各戦艦を軍事力として用いるだけでなく、平時の参勤交代や年貢米輸送なども全て海運を用いて、その利益も防衛費に充てるという事も提示している。
これを野口氏は「諸大名がすべて船会社、回漕業者兼海軍の保有者になるプランにひとし」く、諸大名に権利を集中するため、「一面から言えば、重商主義国家論」でもあるとしている。
第三に「対露防衛論」。この段階ではロシア来寇の危険性を述べている点からも、文化露寇以前であると考えられる。また、大陸国家ロシアを「水戦に長ず」と評している点での間違いが指摘されるが、
今や、東南尽く諸蕃を呑み、以て境を 神州に接し、余を以て其の兵勢を度せば、則ち強大、元寇に減ぜざらん。(中略)是れ、其の復た伊勢の神風を怙むべからざること、智者を竢たずして知るべし
と、かなりの強大な軍事力を持つ相手として、現状では「伊勢の神風」に頼むほかない…とも言う。だからこそ、彼の理想は海軍国家として、整備を進めることだった。
さらに、君平は地政学的な観点からも、対ロシアの利点を考察している。
地曠く、人稀なり。殻を生ずること固より少し。西南な諸夷に界して、戦艦用ふべからず。且つ、其の東北隅、率ね是れ曠莫不毛の郷。其の精兵独だ西南の間に在りて、其の地諸夷と接す。則ち、其の守禦に徹して、以て力を吾が神州に専らにすべからず
ここで、ロシア極東部の人口の少なさや食料が多く取れない事情を述べ、こちら側の軍事力整備が整うことでの防禦を唱えていた。
君平の評価
これら、君平の対外危機への敏感な反応は、どのように受け止められたか。
『不恤緯』提出に関して、文化四年七月三日付の書簡にて木村謙次から会沢正志斎へと「蒲生君蔵には御出合被成候事可有之候、此節御なだめ、妄りに諷諫の語をなし、罪せられぬやうにいたし候様、何分致声候様御申聞、御なだめ被下候」と書簡が送られている通り、こうした行動が「犯萬死不暇自顧」(『不恤緯』上書)との言葉に相応しい、危険を伴うものであったということが言えるのだろう。
君平には数名の門人がいたことが知られるが、その一人である大友直枝は、『不恤緯』に関して、「実に慷概之士ニ御座候、北狄の騒ニも上書して志しを述候、御取揚なく差返され候得共、大ニ流布仕候而其名高く候」と記している。大友は秋田藩の波宇志別神社社家であり、本居大平門の後、君平門人、さらに平田篤胤にも入門している国学者である。彼と君平、篤胤の関係性には未だ考察の余地があろう。
本題に戻すと、君平の生前に出版された『山陵志』、『職官志』(第一巻のみ)と違い、『不恤緯』は少なくとも君平の歿後五十年は活字化されていない。それでも「大ニ流布」したとの文言を見るにつけ、文化露寇に対しての対外強硬論は、その影響力と君平の知名度向上に大きく貢献したのではないかと考えるところである。その考察を支える一つに、全国各地に写本が伝播している事実がある。現在の筆者の調査では、宇都宮から遠く離れた久留米藩士松岡家、椛島家(久留米市立図書館蔵)など全国に約二十の写本があることが確認できている。中でも注目されるべき写本として、高知城歴史博物館蔵の写本奥書には書写者である徳永千規による天保期の一文が記されている。
秀實ナンスレモノソ一布衣ノミ其所レ論患ノ大ナルモノニシテ就中羯奴 吾皇国ヲ窺フニイタリテハカゝル所最大ナリ而其取術実ニ千載愉快ノ策トイフヘクシテ所謂先二天下之患一覇府ヲ警ス其才人ニ超越シ其王室ヲ尊ヒ名実ヲ正クシ不虞ノ謀ヲ備フ実ニ忠誼傑出ノ壮士ト可謂矣
この文章を記している徳永は、文化元年に生まれ鹿持雅澄らに学び、藩校致道館教授を務めた人物である。彼の『靖献遺言』講義は優れていた、と今に伝わるほどであるから、彼の思想は言うまでもない。これまで表に出ていなかった資料だが、土佐藩へも影響を広めていたことを示す点でも、また、対外危機がより一層強まる以前の段階での評価としても貴重である。
君平の著作が幕末でも読まれ、そのうち『不恤緯』は安政五年の写本を元に、明治元年に松下村塾版で出版がなされる。だが、幕末までの影響力という範囲だけではなく、近代以降の影響力も今後検討してゆくべきだろう。
例えば、先に挙げた『不恤緯』(松下村塾版)と『今書』が収録された明治四十四年の叢書には、その掲載にあたって「是れ、乃木大将の推奨に依る所多し」(『国民道徳叢書』)との有馬祐政氏による一文がある。松下村塾版の『不恤緯』が乃木大将へも繋がってゆくと考えると、彼の影響力のさらにその壮大さを感じさせる。もう少し時間をかけて調べてゆきたい。

■津久井龍雄の敗戦と再起
昭和二十年八月十五日、わが国は戦争に敗れた。戦前から国家社会主義者として活動していた津久井龍雄は、終戦の詔勅を疎開先の群馬県で聞いた。
「聴いているうちに涙がでてきたが、それはどういう種類の涙だったのだろうか。一緒にそれを聴いて涙ぐんでいる妻や、その家の人たちの姿をみて、私はひどくみじめな気持ちになり、つとその場を去って外へ出てしまった」(『私の昭和史』)。
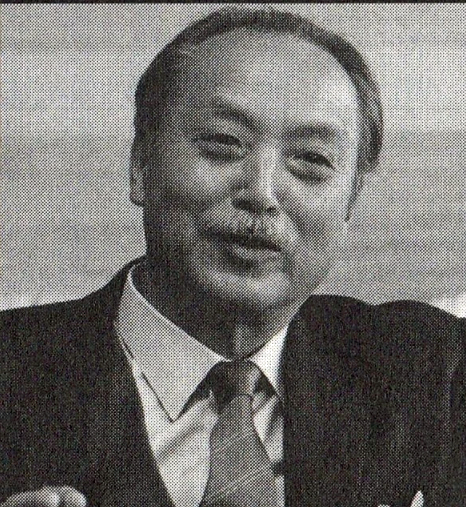
その後も津久井の元には大東塾の自刃や尊攘同志会の愛宕山事件、蓑田胸喜の縊死などさまざまなニュースが飛び込んでくる。それらにハッと胸をつかれる思いがして、再び運動に取り組むこととなった。
「敗戦を食い物にしてきた一部の政治家や役人や資本家や言論人に対して大いに化物退治の一戦を挑みたいと思っている。戦争を喰いものにした奴も憎いが、敗戦を喰いものにした奴はなおさら憎い」(「我が再発足の弁」)。
そんな津久井が昭和二十一年に刊行した三十ページほどの小冊子がある。『救国自治の提唱』と名付けられたこの冊子は、敗戦を「新たな建国」と捉え、社会主義の考え方を一部取り入れた一君万民の道義国家建設を訴えたものであった。それは搾取なき新日本の建設でなくてはならず、日本の国体精神による維新でなくてはならなかった。権力と官治の誘惑を断ち切り、民族の共同団結を目指した農本小国家を訴えた。天皇を中心とした家族国家であるだけでなく、工業大国でないいわば小日本主義に経った共存共栄の実現であった。
■「魂なき繁栄」を続ける戦後社会と津久井の絶望
しかし戦後のわが国はこうした津久井の思いとは裏腹に、対米従属のもとでの反共前線基地として工業化、経済大国化していく。復興と言えば聞こえはいいが、それは「魂なき繁栄」でしかなかった。生活は便利になったが、津久井の理想とする国家とは程遠くなっていく祖国の姿がそこにはあった。そんな中で津久井は中共に注目していく。中国もソ連も「官治」的な強権国家でしかないことを津久井は見抜いており、冷静な分析もしているが、それでも昭和三十年の中国訪問は津久井に刺激を与えた。
「新中国では、総理大臣でも洋車の車夫でも、お互に同志と呼び合っている。考えてみればそれが本当である。同じ国民どころか、同じ東京に住み、同じ区や町に住みながら、相視ること全く路傍の人の如くであるというのは、考えてみれば随分と天理にも背いたことである。そういう人間が、世界国家だの人類愛だのといっても、ちょっとまじめにはうけとりかねる。
日本には同胞という言葉があり、これをはらからと呼ぶとなお意味深長になる。同じ腹から生まれたもの、すなわち兄弟姉妹の意であるが、全国民は同胞であり、同胞は愛し励まし扶け合わなければならないものにきまっている。しかし事実はまったく反対である。新中国の人たちが、互いに同志と呼び合うように、われわれ日本国民が、お互にはらからと呼び合う日は果していつの日に来るのだろうか」(『右翼開眼―中共と日本』)。
津久井が中国に見たものは、素朴で温かい人間関係、相互扶助の共同国家であった。それは中国のようになりたいというよりは、かつての日本が持っていたにも関わらず戦後日本が失ってしまった何かを、中国に行くことで改めて実感したのであろう。津久井に限らず、いわゆる右翼が理想としてきた農本的世界観には、こうした側面が濃厚に潜んでいる。
津久井は高齢になっても衰えず言論活動を展開していくが、最晩年は右翼にすら絶望し、「敗戦で右翼は終わった」と口にするようになっていった。あまりにも目指すべき国と現状の祖国とが食い違っているためについていけなかったのかもしれない。
■敗戦に潜む欺瞞
本稿は津久井論ではない。津久井に関しては折本龍則氏の原稿をご参照いただきたい。わたしが述べたかったことは、戦後社会にはある欺瞞がひそんでいるということだ。それは明治時代から始まったものであるが、戦後より一層加速された。一言で言えば古き良きものを切り捨て、近代化していくことに対する痛みを失ってしまったのである。自らの文化や伝統に対する自信や頑なさを失い、ただ便利になっていくことをよかったよかったと喜んでいるだけなのである。反左翼はあっても理想がない。世界観がないのである。
いまの日本では「同胞」と呼び合うことができない。そんな中で唱えられる愛国心とは何だろうか。「愛政府心」と見分けのつかない、権力者や既得権益者に都合の良いだけの何かではないだろうか。
■同胞と呼び合える国家へ
石川三四郎『農本主義と土民思想』には次のような一節がある。
「土民は土の子だ。併しそれは必ずしも農民ではない。鍛冶屋も土民なら、大工も左官も土民だ。地球を耕し――単に農に非ず――天地の大芸術に参加する労働者はみな土民だ。土民とは土着の民衆といふことだ。鍬を持つ農民でも、政治的野心を持つたり、他人を利用して自己の利慾や虚栄心を満足するものは土民ではない。土民の最大の理想は所謂立身出世的成功ではなくて、自分と同胞との自由である。平等の自由である。」
土着を重んじる石川三四郎の考えはいろいろな意味で興味深い。そもそも日本は豊蘆原瑞穂国と言い、葦も稲も泥の中で育つ植物だ。古き日本は泥の国であり、泥は生命が萌え出ずる温床となるものだ。そして日本神話からも明らかなように、その蓄積した泥からは八百万の神々も生まれてくるのである。日本の泥の文化はエネルギーが内に堆積していくところに強みがある。こうした世界観はアジア地域にある程度共有されているものだ。津久井が中国で思い起こしたものは、決してソ連的共産主義ではない。むしろそうした近代文明的表皮をはぎ取った中にあるアジア的共同性、土着性を見て取ったのである。それは津久井の敗戦後の決意とも重なってくる。
いまの日本人は関係が希薄化し、カネでしか結びつけない関係が世を支配している。しかしそこに生き甲斐はあるか。人々の居場所はあるのだろうか。同胞と呼び合える国家へ。地に足をつけた土着的国家へ。新時代の目指すべき先はここにあるのではないか。
(小野耕資)

象徴天皇?
「象徴天皇」なる奇妙な語がいわゆる「日本国憲法」に盛り込まれて以降、日本人の天皇観はおかしくなってしまった。天皇は独裁せず、臣下に実権をゆだね、権力よりも権威の存在であること。それが日本本来の姿であると説かれたのである。このことにより、天皇親政の大理想は忘れ去られ、幕府政治や摂関政治への批判意識が捨てされたのである。
この傾向は「象徴天皇」で決定的となったが、既に明治維新以降の「英国王室風への憧れ」の中で徐々に始まっていた。福沢諭吉の『帝室論』に始まって、津田左右吉や坂本多加雄なども「君臨すれども統治せず」的な皇室論を展開している。男女平等で、(臣下であるはずの)皇后は天皇と対等とされ、宮中では和装は禁止でタキシードでなければならず、国民に向かって手を振られる愛くるしい皇室でなければならない…。余談ながら王室が国民に向かって手を振る慣習は、英国国民にあまりに人気がなく、王室廃絶論まで噴出したので、廃絶派を抑え込むために王室のマスコット化を進めたため登場した風習と言われている。このような風習をそのまま習ってしまった日本人の皇室観のゆがみは深刻である。
もちろん天皇への独裁権力の付与などは論外である。だが天皇親政論を天皇独裁論と同一視するのは軽率ではないだろうか。天皇親政論を天皇独裁論とはき違える議論は世にあふれているが、それは親政派の議論をきちんと参照していない不誠実な議論ではないだろうか。
國體派の天皇観
例えば天皇主権説論者である穂積八束は「大権政治は大権専制の政治には非ず。専制ならんには、之を憲法の下に行うことを許さざるなり。君主の大権を以て独り専らに立法行政司法を行うことあらば、即ち専制なり。同一君主の権を以てするも、立法するには議会の協賛を要し、行政するには国務大臣の輔弼に依り、司法は裁判所をして行わしむることあらば、分権の主義は則ち全たし。権力の分立は、意思の分立を意味す。国家意思の絶対の分立は、国家の分裂なり。唯主幹たる意思の全体全体を貫くあり、而して之に副えて、其の或種の行動には、更に或種の機関意思之に加味せらるることあらば、統一を損することなくして専制を防ぐに足らん。之を立憲の本旨とす。大権政治とは大権を以て此の主幹たる意思とする者の謂なり。」(『憲政大意』244頁)即ち穂積は国家意思の分裂を防ぎ、権力の分立を図るためにも天皇大権の確立が必要だと説いているのである。それに対して美濃部は「穂積さんは主権を以って絶対無制限の権力であると言い、その意味においての主権が我が憲法上天皇に属するのであって、即ち天皇の主権は絶対無制限の権力であり、主権を制限する如何なるものも存在しない」と考えていると、全くの無理解を示している(高見勝利編『美濃部達吉著作集』113頁)。もちろん穂積は天皇独裁を主張したのではない。国家意思が天皇にあると述べたのである。主権説における(天皇が持つと考えた)国家意思とは、「これからは立憲制を採用する」という類の国家の大方針であって、当然細部は輔弼者が上奏し責任を負うものだと考えていた。

上杉愼吉は「国体に関する異説」で「仮令心に君主々義を持すると雖も、天皇を排し人民の団体を以て統治権の主体なりと為すは、我が帝国を以て民主国なりと為すものにして、事物の真を語るものに非ずと為すのみ」(『近代日本思想体系33大正思想集Ⅰ』6頁)と言う。あるいは蓑田胸喜は「帝国憲法第十条に曰く『天皇ハ行政各部ノ官制及文武官の俸給ヲ定メ及文武官を任免ス』と。(中略)行政法を講ずるもの、その直接の第一依拠を本条に求めざるもの一人としてなきにも拘らず、美濃部氏を始め従来殆どすべての行政法学者は異口同音に『行政権の主体は本来国家である。』の語を以てその論理を進むるのである。これいふまでもなく憲法論上に於ける『国家主体・天皇機関説』の行政法論へのそのままの適用である。即ち、『統治権の主体』を以て国家となすの結果、その統治権の一成素たる『行政権の主体』も亦国家なりとするのである」(「行政法の天皇機関説」『蓑田胸喜全集 第六巻』230~231頁)という。

続きを読む 小野耕資「天皇親政論」(『崎門学報』第14号、平成30年12月1日) →

平成三十年は「明治百五十年」といふことで、各地で様々な催しや出版物が企画される模様だ。その中で、山崎闇斎の学派が王政復古に果たした役割については充分な見直しがされたとはいへない。
管見の限り、明治維新の再検討については、昭和初期に「講座派対労農派」の日本資本主義の解釈をめぐる論争のほか、戦時下における幕末維新史の再評価、そして今から半世紀前の「明治百年」の際の出版企画など、これまでも数十年置きに繰り返されてきたと見られる。しかし時を経るにつれ、明治そのものが本当に遙かに遠くなるにつれ、一部の識者の働きかけに反し、国民一般への浸透については低迷の感が否めない。
改めていふまでもなく、明治期の歴史や思想を扱つた書物は、現在刊行されてゐるものだけでも汗牛充棟の勢ひで、その書誌を整理するだけでも容易なものではない。その中で、これまでの筆者の貧しい読書体験から、国学や水戸学、そして闇斎学派について言及があるものをいくつか紹介していきたい。
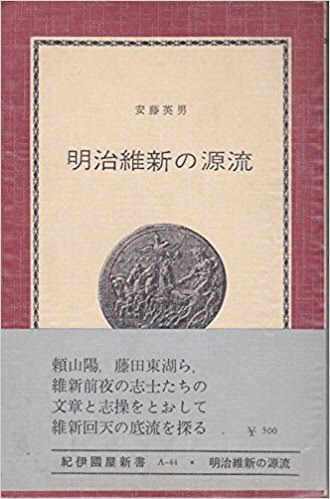
『明治維新の源流』は「明治百年」と呼ばれた翌年の昭和四十四年、紀伊國屋新書の一冊として刊行された。紀伊國屋新書は、当時同店出版部で嘱託をしてゐた評論家の村上一郎の企画によるもので、桶谷秀昭の初期評論『ジェイムス・ジョイス』や橋川文三の『ナ
ショナリズム』、宮川透の『日本精神史への序論』もこのシリーズから刊行されてゐる。
昭和五十六年に復刊された新装版の序文によると、当初は「漢詩鑑賞」といつたテーマで依頼されたさうだが、唯物史観全盛期だつた当時、「思想の力を軽視してはならない」といふ著者の意志により、人物の力を重視した記伝の体による近世日本史を上梓する運びになつたといふ。その辺り、昭和三十年代に龜井勝一郎が提起した「昭和史論争」との接点も感じられるが、当時の歴史学界で、人物の活躍よりも、如何に抽象的な「発展的法則」に比重が置かれてゐたかが窺へる。
著者の安藤英男は昭和二年生まれ。法政大学の経済学部卒業後、銀行に勤めながら、蒲生君平や頼山陽、雲井竜雄、河井継之助といつた江戸後期から幕末にかけての人物伝を著し、学位を取得。後に国士舘大学教授になる。平成四年に六十半ばで亡くなり、その存在は忘れ去られつつあるが、今でも寛政の三奇人や幕末志士の評伝などで、その著書が参考文献として掲げられることは少なくない。
はしがきにもある様に、とりわけ「維新変革の基本的精神が、国体論・名分論によって培われ、激成されたものであること」に、中国やフランスの〝革命〟や、室町幕府成立後の体制変換と大きく異なる所以が強調されてゐる。 続きを読む 山本直人「維新の源流を繙く①安藤英男著『明治維新の源流』」(『崎門学報』第12号、平成30年5月1日) →
山本七平『現人神の創作者たち』が描こうとしたもの
巷間に知れ渡っている書物の中で、崎門について触れているものに山本七平『現人神の創作者たち』がある。この本は「尊皇思想の発端」として崎門学を指摘し、浅見絅斎『靖献遺言』、栗山潜鋒『保建大記』、三宅観瀾『中興鑑言』についてはその内容まで紹介している。
ただし本書は崎門学を戦時中の「呪縛」の発端とみなし「徹底的解明」と「克服」を目論んだものであると宣言していることから、崎門学徒はあまり取り上げて来なかった。
しかし山本は「現人神」の創作者を二十年以上の歳月を費やして探してきたと述べている。単に忌むだけではこれほど長い期間関心が続くものだろうか。また、後述するように、山本七平という一人の人間のルーツを考えたとき、単純に崎門の思想を全否定するためだけに書かれたとは言い切れない所がある。本稿では『現人神の創作者たち』の細かい論旨を紹介しないが、わたしが気になった個所に触れつつ、崎門学について論じてみたい。
幕府正統論の「まやかし」
山本が単純な崎門の全否定ではなく、もう一段深いところで考察しようとしていることは、『現人神の創作者たち』の最初に既に示されている。即ち山本は吉田満を引用しながら、戦中派は自らを戦争に駆り立てた一切のものを抹殺したいと願ったが、一方で戦後の自由、平和、人権、民主主義、友好外交の背後にも「まやかし」があると直感していたと述べたうえで、戦後社会は敗戦の結果「出来てしまった社会」であり、一定の思想のもとに構築した社会ではなく、更にこの「出来てしまった」秩序をそのまま認め、統治権にいかなる正統性があるか問題にしない「まやかし」があるという。そしてそれは承久の変の結果「出来てしまった」幕府体制ときわめて似ているという。北条泰時は承久の変で後鳥羽上皇らを配流しておきながら「天皇尊崇家」である「不思議な存在」であり、「貞永式目(御成敗式目)」には「統治権を幕府が持つ」とは一切書いていない。更に貞永式目はそれまで朝廷で制定された「天皇法」を否定するものではなく、「あたりまえのこと」を取りまとめただけだ、と考えていたことを紹介する。
ここで留意すべきことは山本七平という作家は『日本人とユダヤ人』『空気の研究』などの著作にも共通しているが、こうした曖昧模糊とした体制を、その外にいる者として批判的に見ることを大きな特徴とした作家であるということだ。即ち結論を先取りすることになるが、『現人神の創作者たち』は戦時下を経験したものとして、そこで唱えられた「現人神」の「徹底的解明」と「克服」をせねばすまない自己(=崎門否定)と戦後的、幕藩体制的曖昧模糊とした正統性の不明瞭な社会になじめない自己(=崎門的)の両面が矛盾しながら存在しているのである。
続きを読む 小野耕資「山本七平『現人神の創作者たち』を通して崎門学を考える」(『崎門学報』第11号、平成30年1月31日) →
北朝鮮の核武装が意味するもの
去る平成二八年二月七日、北朝鮮が事実上の弾道ミサイルを発射した。このミサイルは射程一万から一万三千キロのICBM(大陸間弾頭ミサイル)であり、アメリカ本土を射程におさめる。すでに北朝鮮は二〇〇六年以来、これまで四回の核実験を行っており、金正恩は核弾頭の小型化にも成功したと主張している。よってそれが事実ならば、小型化した弾頭を弾道ミサイルに搭載すれば、アメリカ本土を核攻撃出来ることになる。 これは北朝鮮が、朝鮮有事に際するアメリカの介入を排除する抑止力を手に入れたことを意味し、戦後の米韓同盟にクサビを打ち込むものだ。というのも、朝鮮有事にアメリカが韓国を支援すれば、北朝鮮はアメリカ本土への核攻撃を示唆し、米韓同盟を無能化することが出来るからだ。この可能性が韓国側にもアメリカへの不信感を生じさせ、早くも韓国世論では核武装論が噴出しているという。
しかし同様の問題は、米韓のみならず北朝鮮の脅威を共有している我国とアメリカとの関係についても同様である。
MDは無用の長物だ
北朝鮮からのミサイル攻撃に対して、我が国は同盟国であるアメリカからMD(ミサイル防衛)を導入し配備している。MDは、敵国から発射された弾道ミサイルを、自国の迎撃ミサイルで撃ち落すシステムであり、我が国はアメリカに一兆円以上を払って、イージス艦など海上配備型の迎撃ミサイルであるSM3と地対空誘導弾パトリオットのPAC3を配備している。
しかし、実はこのMD、導入元のアメリカですら、これまでに行った迎撃実験は一度も成功しておらず、カネがかかる割りに実用性が乏しいシステムであることが指摘されている。アメリカは北朝鮮の脅威を喧伝し、自国の軍産複合体を儲けさせるために、法外に高く信頼性の低い兵器を我が国に売りつけているふしがある。
またMDが機能するためには、わが国政府はアメリカの軍事衛星から送られるミサイル発射情報に依存せざるを得ず、仮に北朝鮮がアメリカに対する核恫喝を行った場合は、前述した米韓同盟のように日米同盟も無力化されかねない。
揺らぐアメリカの信頼
とはいっても、北朝鮮の核・ミサイル実験はもはや年中行事と化しおり、たしかに脅威ではあるが、所詮は周辺国から外交的な譲歩を引き出し、経済援助を手に入れるための空脅しに過ぎないという見方もあるだろう。
しかし、北朝鮮の後ろ盾となっている中国の脅威ははるかに現実的だ。周知のように、中国は近年における経済成長の鈍化にもかかわらず、軍事費は相変わらずの二桁増を続け、積極的な海洋進出を進めている。こうした軍事的拡張の結果、仮に中国が尖閣諸島に侵攻しわが国と交戦状態に突入した場合、我が国がアメリカから導入したF15戦闘機やオスプレイによって迅速に対応し、尖閣を死守ないしは奪還することが出来たとしても、中国は軍事行動のレベルをエスカレートして我が国に核恫喝を仕掛ける可能性がある。
また日米安保に基づいて日本を援護するアメリカに対しても、在日米軍ないしはアメリカ本土への核攻撃を示唆して中国が核恫喝を行えば、アメリカは対日防衛を躊躇し、我が国民が期待するアメリカの核の傘は機能せず、核戦力を持たない我が国は中国への軍事的屈服を強いられる他ない。それでなくても近年、中東政策に膨大なコストを浪費し、財政的な制約を抱えるアメリカは嫌が応にも孤立主義的な性格を強め、中国の台頭を抑止する意思も能力もない。つまり日米同盟論者が信仰するアメリカによる核の傘は破れる以前に被さってもいないのである。 続きを読む 折本龍則「時論 自主防衛への道 いまこそ核武装による恒久平和の確立を!」(『崎門学報』第7号、平成28年4月30日) →
栗山潜鋒の『保建大記』を読了した。潜鋒は山崎闇斎の高弟である鵜飼錬斎と桑名松雲に師事し、第百十一代後西天皇の皇子である八條宮尚仁親王の学友として近侍した。潜鋒が親王に近侍したのは14歳の時であり、両者は同年齢であった。以来、潜鋒は、親王に錬斎、松雲から受け継いだ闇斎の学を伝え、彼が元禄元年、18歳のときに親王に献上した書が『保平反正録』である。その後、この書名に含まれる「反正」は反正天皇の諡号であるため、書名を『保平綱史』と改めた。何れにしても「保平」とあるのは保元平治の両兵乱のことである。
ところが、本書を献上した翌年、親王は俄かに早世し給い、潜鋒は悲歎に暮れたが、彼の卓越した学識を認めた水戸光圀は、『大日本史』編纂の史局である彰考館に彼を登用し、かくして潜鋒は光圀に仕えることになった。この水戸出仕中に、彼が先輩同僚との議論を経る中で前出の『保平綱史』に大幅な改訂を加えたのが『保建大記』である。今度の書名が「保平」ではなく「保建」となったのは、潜鋒が朝威失墜の根本原因を、保元平治の兵乱による武家の簒奪ではなく、むしろそれを出来した朝廷内部、なかんづく後白河天皇の失徳に求め、平治とこの天皇が崩御し給うた建久の年号を以って書名に冠したからである。
近藤先生によると、潜鋒が光圀に仕えた意義は重大である。というのも、『大日本史』は、光圀の意向によって、以下の三大特筆を有するとされる。すなわち第一に、神功皇后を帝紀より除いて后妃伝に入れること。第二に、大友皇子を帝紀に入れること、そして第三に南朝を正統とすることである。しかしその内第三の点は、今上天皇が北朝の御血筋であることから彰考館の内部でも反対意見が強かった。その際、潜鋒が水戸での出仕中に到達した独自の神器論は、『保建大記』のなかに盛り込まれ、光圀の素志を道義と史実の両面において論証したのである。
ここでいう潜鋒の神器論は「躬に三器を擁するを以て正と為すべし」というをその眼目としていた。これに対して、彼の同僚である三宅観瀾は『保建大記』に寄せた序文において「神器の存否を以てして、人臣の後背を卜する者とは、議竟に合はず」と記し、皇位にとって重要なのは神器ではなくて天皇の君徳であると反論したが、この考えは、同書の跋文を書いた安積澹泊といった彰考館の他の同僚についても同様であった。

近藤先生のいわく、「思うに土地といひ家屋といひ、その所有を主張するものが複数であって互ひに所有の権利を争ふ時には、その土地や家屋の権利書を所持してゐるものを正しい所有者と判断せざるを得ない。されば人はみな権利書を大事にして失はぬやう盗まれぬやう、だまし取られぬやう、その保管に心を用ひるのである。神器もその性格、ある意味では権利書に似てをり、皇統分立していづれが正しい天子であるか知りがたく、人々帰趨に苦しむ時は、神器を有してをられる御方を真天子としてこの御方に忠節を尽くさねばならない。いはんや神器は権利書と異なり、その由緒からいへば大神が天孫に皇位の御印として賜与せられし神宝であり、大神の神霊の宿らるるところとして歴代天皇が奉守継承して来られた宝器であり、極言すれば、天祖・神器・今上の三者は一体にして、神器を奉持せられるところ、そこに天祖がましますのである。」(近藤啓吾先生『続々山崎闇斎の研究』所収「三種神器説の展開―後継者栗山潜鋒」)
続きを読む 折本龍則「『保建大記』における神器論の問題」(『崎門学報』第2号、平成27年1月1日) →
帝京大学の小山俊樹教授が、『五・一五事件 海軍青年将校たちの「昭和維新」』(中公新書)で、第42回サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を見事に受賞された。
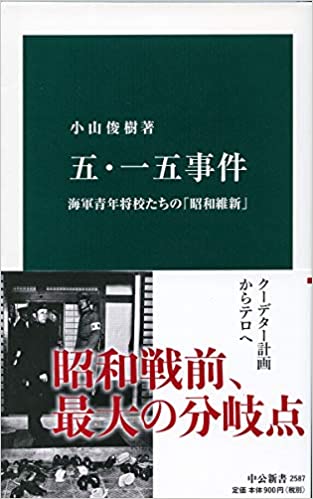
『大亜細亜』は、平成29年に小山教授が上梓された前作『評伝 森恪 日中対立の焦点』(ウェッジ)に関して、インタビューをさせていただいた(インタビュー・構成 小野耕資)。そこで「一九二〇~三〇年代に起きたことは、世代を超えて語り継がれていきます。とくにほとんどが刑死した二・二六事件と異なり、五・一五事件の主要な関係者は、戦中戦後も生きています。彼らにとって戦後とはどういう時代だったか。このことを考えながら、五・一五事件を描ければと思っています」と述べられていたことが印象深い。
以下、『大亜細亜』第6号(平成30年7月)に掲載した小山教授のインタビュー記事「西洋列強との協調と相克の近現代史」全文を紹介します。
帝京大学文学部史学科教授の小山俊樹先生は日本近現代史専攻で、昨年(平成二十九年)、『評伝 森恪 日中対立の焦点』を上梓された。森恪は戦前日本の大陸政策に関与した人物で、小山教授は森とアジア主義者との関わりにも言及している。そこで同書の内容を中心に、戦前のアジア主義運動史について、平成三十年六月六日にインタビューを行った。
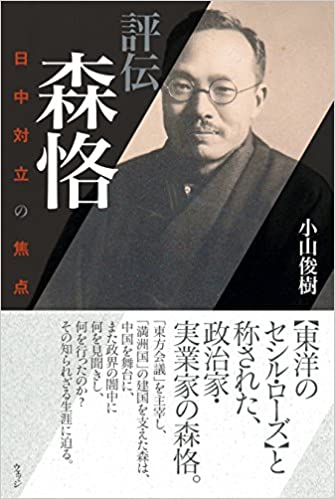
―─ 森恪に興味を持ったきっかけは、どういったものでしたか。
博士論文(『憲政常道と政党政治 戦前二大政党制の構想と挫折』)を執筆した際に、二大政党時代の政党政治研究がまだまだ薄いと感じました。そして論文では、森恪が当時の政界のキーマンとして度々登場するので、いずれは本腰を入れてまとめなければと考えていました。そこに、ウエッジ社編集部から中国関係の人物伝を依頼されたので、それではと挑戦することにした訳です。
一般には森の知名度も高くはなく、編集部にも意外な人選だったようです。森の本格的研究は乏しく、一般には松本清張などの影響で、大陸侵略の陰謀を練った怪しい人物というイメージが先行している状況でしょうか。また、四十九歳という短命で亡くなりますが、その劇的で濃密な生涯に、興味を持ったことも理由の一つです。
続きを読む 小山俊樹教授インタビュー「西洋列強との協調と相克の近現代史」(『大亜細亜』第6号、平成30年7月) →
沖繩を訪ねたのはもう六年も前の話だ。首里城については那覇空港に着いた後、ゆいレールに乘つて眞つ先に足を運んだ場所である。本州から滅多に出る機會のなかつた自分にとつて、まるで海外にでも出向いてゐるやうな昂揚感があつた。
首里驛から城のある首里城公園までは、最寄り驛と云ふにはそれなりに距離がある。しかし二十分近く歩いた末に、遠方から見渡せる城郭の遠望は壯觀である。
そこからまた暫く城内を散策すると、二千圓札でお馴染みの守禮門が迎へてくれる。その創建は明確ではないが、中國がまだ明の時代だつた十六世紀半ばの第四代の尚清王の時代には既に存在してゐたとされる。
當初は「待賢門」とよばれ、「首里」の額が掲げられてゐた。その後、第六代尚永王の時代に明から册封使が派遣される際には「守禮之邦」の額が掲げられるやうになるが、十七世紀半ばの第十代の尚質王の時代にそれが常掲となり、現在の「守禮門」として定着するやうになつたといふ。沖繩戰の首里城燒失後、昭和三十三年に眞つ先に再建されたのが、この守禮門だつた。以來、沖繩觀光の象徴的存在となつた。
そこから城壁を拔け、首里城正殿に向かふわけだが、國内で目にすることができる通常の城郭建築とは大きく異なるその壯大な姿から、映畫『ラストエンペラー』で大冩しにされた紫禁城を想ひ起こす人も少なくあるまい。しかしながら、實際はその中心部には、唐破風とよばれる日本の城郭建築特有の意匠が施され、この正殿だけでも東アジアの傳統建築の樣々な要素がふんだんに織り込まれてゐることに氣づく。
廣場の南殿は主に薩摩の使節を受け容れ、疉敷きの和風樣式となつてゐる。一見、大陸風の外観に、日本國民にとつて馴染み深い畳敷きの部屋があるのには、何とも親近感を覺えずにはゐられない。一方、明朝以來、清國とも外交儀礼上、朝貢關係を結んでをり、册封使を迎へ入れる北殿は、南殿とはおよそ対照的な中華風の建物となつてゐる。
正殿内部は博物館となつてをり、元は「京の内」とよばれる古神道の樣な祈祷場の他、政治外交を司る「表」、更には江戸城大奧のやうな「御内原」とよばれる施設もあつた。中世から近世の城郭建築のみならず、京都御所で云へば政廳の場だつた紫宸殿、日常生活の間の清涼殿を併せ持つ施設でもあつたやうだ。 続きを読む 山本直人「首里城の夢の跡」(『維新と興亜』第2号) →
道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)