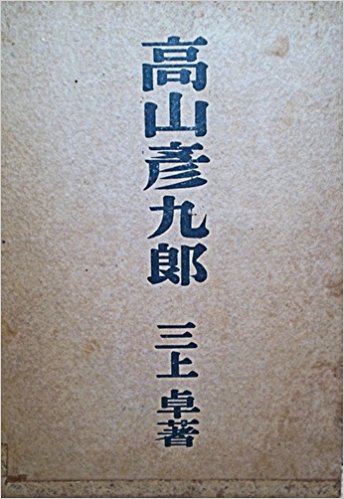北畠親房には三兄弟の子供がありました。顕家(あきいえ)、顕信、顕能であります。皆よく王家の為に尽し、公卿の出でありながら軍事に従事し、いずれも戦功を挙げたのは、その忠誠の志を示すものでありましょう。
元弘元年(1331年)、長子顕家は参議に任じ、同三年(1333年)には勅を奉じて陸奥守となりました。義良親王を奉じ、陸奥・出羽に赴き、両国を帰順せしめ、その功によって、建武元年(1334年)には従二位に叙せられ、二年(1335年)には鎮守府将軍を兼ねました。顕家の躍進は此の如きでありました。
足利高氏が反逆するや、義良(のりなが)親王(後醍醐天皇の第七皇子、後の後村上天皇)を奉じ、新田義貞と共に、高氏を鎌倉に攻めました。ところが、この時高氏は大兵を率いて京師の方へと進みましたので、顕家、義貞と共にこれを追いました。高氏と各所に戦いて一勝一敗あり、遂にこれを破りましたので、高氏は九州へと敗走しました。それによって車駕京師に還り、顕家は再び陸奥を鎮めることとなったのです。
然るに再び、高氏が九州で兵を挙げ、京師に攻め来りました。また、陸奥の将士の多くも高氏に応じ、顕家を攻めました。顕家は義良親王を奉じて霊山城に向かい、そこで籠り時を待ちました。折しもその時、詔書来り、京師に出でて足利直義を討てと仰せられたので、顕家は霊山を出ました。白川関を経て宇都宮に至り、足利義詮と利根川を隔てて対陣し、これを破って相模に入り、直ちに北条時行、新田義興と共に鎌倉を攻めて足利義詮を敗走せしめました。その後、兵を率いて京師に赴かんとしましたが、沿道の賊軍に阻まれたので、顕家は陣を青野原に留めました。時に高氏、高師泰を遣わして顕家を攻めさせました。このために、顕家は前後から敵に挟まれ、窮地に立たされました。各所にて戦い、漸く河内に逃れて男山に陣し、高師直と戦って破りました。然るに、師直さらに大兵を挙げて男山を囲みましたので、顕家は出でて戦いましたが大いに敗れ、接戦して遂に陣没したのであります。
時に顕家は僅かに二十一の青年でありました。後に功を以て従一位右大臣を贈られたのであります。

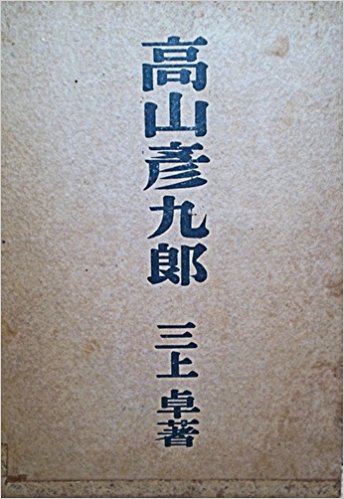
●即似庵継承の精神
『高山彦九郎』(三上卓先生)は、久留米藩国老・有馬主膳の茶室「即似庵」を「九州の望楠軒」と称した。同書には、即似庵遺跡の写真を掲載し、以下のような説明を付している。
「高山、唐崎両先生が久留米の同志と密談した即似庵遺跡は久留米市東櫛原町久留米商業学校裏手にある。附近一帯の老樟欝蒼たる地は国老有馬主膳の別邸跡にして、即似庵なる茶室は左端の家屋(現住者は久留米新勤王党の同志の一人たる林田瀬兵衛守隆の子息峰次氏)の位置にありしも、維新後市内篠山町中学明善校裏門附近に移され、稲次亥三郎翁居住さる。翁は真木和泉守門下の高足たる稲次因幡の後嗣、因幡は佐幕派の弾圧に逢ひて憤死せし勤王家なり」
林田守隆は、慶応4(1868)年正月、小河真文ら勤皇派の同志とともに、親幕派の参政不破美作暗殺に参加。久留米藩で組織された「応変隊」の小隊長として戊辰戦争に従軍し、箱館戦争で功を立てた人物である。
明治4(1871)年の久留米藩難に際しては、藩知事有馬頼咸の命を受け、本庄一行とともに東京から久留米に派遣され、水野正名や小河真文らと交渉し、事態の収拾にあたった。晩年は真木保臣先生顕彰会会長などに推戴された。
☞[続く]
平成二十九年八月六日、浦安で崎門研第六回保建大記の勉強会を開催した。当日は折本代表をはじめ有志四人が参集した。前回に引き続き栗山潜鋒「保建大記」を理解するため、谷秦山の「保建大記打聞」(テキストは杉崎仁編注『保建大記打聞編注』を使用)を読み進めた。今回は、同書六十五ページから七十七ページまで輪読した。
今回の主な内容は、以下の通り。
シナが王朝ごとに国璽が違っていたのはわが国の神器が皇祖から伝わっているのと全く異なる。故に神器を持っている君主が正統なのは疑いない。保元の乱でいえば後白河天皇方が正統である。平清盛は母が重仁親王の乳母でもあったことから、上皇方か天皇方かどちらに付くのか微妙であるとみられていたが、鳥羽法皇の違勅と称した美福門院の招きに応じ、天皇方として立った。これは清盛の勲功であって、後の振る舞いが良くないからと言ってこれをほめることをためらうべきではない。これは源為義が、自分は老いているし悪い夢も見たからと固辞しようとしたものの、ついに上皇方に説得されたのと好対照である。崇徳上皇も重祚の夢を…見ておられたようだが、神武天皇が八咫烏を夢に見て得られたのとは異なる結果となった。夢はみだりに信じてはならないが、夢の霊験が全くないとも言い切れない。
なお、今回も終了後懇親会を行った。次回は八月二十八日新橋で開催の予定。
(記:事務局 小野)
今年もまもなく終戦記念日を迎える。「終戦記念日」というと聞こえはいいが、実際は「敗戦記念日」であり、我が国にとっては白村江の戦い以来の大敗北を喫した国辱的な記念日である。周知の様に我が国は国体を護持しうるという条件の下でポツダム宣言を受諾したのであるから決して「無条件降伏」ではなかった。しかるに戦後アメリカによる対日占領政策では、神道指令や天皇の「人間宣言」、主権在民の憲法等、我が国の国体を根本から否定する改革が行われ、我々は戦後から七十年以上を経た現在に於いても、その後遺症に苦しめられているのである。特に、戦後GHQや日教組によって植え付けられた自虐的な進歩史観が我が民族の弱体化に与えた影響は計り知れない。そこでは、先の戦争を引き起こした原因が、明治憲法下における民主主義の不徹底や内閣から独立した軍部の暴走によるものとされ、民主主義や軍の文民統制を正当化する根拠とされたのである。確かに明治憲法では、天皇が統治権を総攬し、軍を統帥するとされた一方で、その存在は神聖不可侵であるから政治的に不問責であると規定されたことから、一面では皇威を傘に着た薩長藩閥の政治的な隠れ蓑にされた嫌いはある。また、明治の元勲亡き後、内閣と軍が割拠し、政軍の意思統一が測り辛くなったのも事実である。しかしその事は、毫も天皇をイギリスの立憲君主の様に、政治権力の埒外に置き、文民統制の名の下に軍を民主主義に従属させる根拠にはならない。むしろ、それらの事実は、本来、建武新政以来の王政復古、天皇親政を実現した明治維新の精神が英国流の立憲君主制の影響によって後退した結果を示すものに他ならない。即ち、「君臨すれども統治せず」とする消極的君主像が理想化されたことが、天皇大権の発動による断固たる政治意思を不在にし、責任の所在を曖昧にし、政軍の割拠を招いた根本の原因なのである。天皇は神聖不可侵であるが、統治権の総攬者である以上、政治的に不問責ではあり得ない。しかしその責任は、国民やその子孫に対してではなく、皇祖皇宗に対するものであり、それなくしてキリスト教的な個人主義道徳に基づかない我が国の政治体制は、茫漠たる「無責任の構造」(丸山)に陥らざるを得ない。戦後民主主義は、軍(自衛隊)は内閣に対して責任を負い、内閣は国会に対して責任を負い、国会は国民に対して責任を負うことになっているが、では国民は何に対して責任を負うのか定かではない。天皇は、皇祖皇宗に対して責任を負い給うのに対して、国民は将来の何者にも責任を負うことはない、いな誰も責任を負うことなど出来ないのである。これこそ、巨大な「無責任の構造」である。この様に、我々が先の敗戦と明治憲法体制の挫折から学ぶべき教訓は、天皇親政ではなくして立憲君主制、責任なき民主主義、議会政治の弊害である。
徳富蘇峰翁は、終戦直後の日記の中で、先の敗戦の原因について考察し、次の様に述べている。「今上陛下に於かせられては、むしろ御自身を戦争の外に超然として、戦争そのものは、その当局者に一任遊ばされることが、立憲君主の本務であると、思し召されたのであろう。しかしこれが全く敗北を招く一大要因となったということについては、恐らくは今日に於てさえも、御気付きないことと思う」と。我が国に於ける天皇の本来的な御姿は、英国流の立憲君主の様な消極的君主ではなく、万機をみそなわし、皇軍を統帥し給う能動的君主としての御姿である。またそのご親政を輔弼し奉ることが臣下たる我々国民の責任であり、この君臣の本然たる姿を取り戻すことが国体の護持にとって何より肝要であって、それなくして我々が先の「敗戦」の教訓に学んで有史以来の国辱を雪ぎ、真の「終戦」を遂げることは出来ないと断じる。
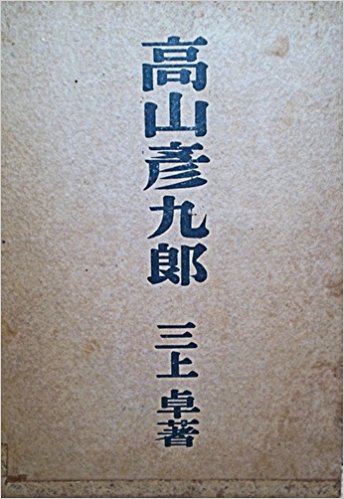
●垂加神道の伝書を伝えた唐崎常陸介
久留米への崎門学の浸透において、高山彦九郎の盟友・唐崎常陸介は極めて重要な役割を果たした。
唐崎は、寛政二(一七九〇)年末頃、久留米に入り、櫛原村(現久留米市南薫町)の「即似庵」を訪れた。即似庵は、国老・有馬主膳の茶室である。主膳は崎門派の不破守直の門人である。不破は、久留米に崎門学を広げた合原窓南門下の岸正知のほか、崎門学正統派の西依成斎にも師事していた。
即似庵は、表千家中興の祖と言われる如心斎天然宗左の高弟・川上不白の設計により、寛政元年に起工し、寛政二年秋に落成した。三上卓先生の『高山彦九郎』には、次のように描かれている。
「主膳此地に雅客を延いて会談の場所とし、隠然として筑後闇斎学派の頭梁たるの観あり、一大老楠の下大義名分の講明に務め、後半世紀に及んでは其孫主膳(守善)遂に真木和泉等を庇護し、此別墅(べっ しょ)を中心として尊攘の大義を首唱せしめるに至つたのである。此庵も亦、九州の望楠軒と称するに足り、主人守居も亦これ筑後初期勤王党の首領と称すべきであらう。
唐崎、此地に滞留すること五十余日、主人守居を中心とせる闇斎学派の諸士、不破(実通)、尾関(守義)、吉田(清次郎)、田代(常綱)等及国老有馬泰寛、高良山蓮台院座主伝雄、樺島石梁、権藤涼月子、森嘉善等と締盟し、筑後の学風に更に一段の精采を付与した。…唐崎より有馬主膳に伝へた垂加神道の伝書其他の関係文献は今尚後裔有馬秀雄氏の家に秘蔵されて居る…」
有馬秀雄は、明治二年に久留米藩重臣・有馬重固の長男として生まれ、帝国大学農科大学実科卒後、久留米六十一銀行の頭取などを務めた。その後、衆議院議員を四期務めた。
唐崎から有馬主膳に伝えられた文献のうち、特に注目されるのが、伝書の末尾に「永ク斯道ニ矢ツテ忽焉タルコト勿レ」とある文言と、楠公父子決別の図に賛した五言律の詩である。
百年物を弄するに堪へたり。惟れ大夫の家珍。孝を達勤王の志。忠に至る報国の臣。生前一死を軽んじ。身後三仁を許す。画出す赤心の色。図を披いて感慨新なり
さらに、唐崎は垂加流兵学の伝書も伝授したらしい。
☞[続く]
我国が南北両朝に分れて互いに雌雄を争った時に、『神皇正統記』を著して南朝が正統であることを論じ、いわゆる大義名分を明らかにしたのは、北畠親房(きたばたけちかふさ)であります。親房は第六十二代村上天皇の第七皇子、具平(ともひら)親王の後裔で、権大納言師重(もろしげ)の子、顕家の父であります。北畠家は、村上源氏の嫡流として代々朝廷に仕えた名門です。
元亨三年(1323年)には大納言に進み、世良親王の傅(輔佐役)となりました。しかるに元徳二年(1330年)に親王が薨じ給うたので、親房は大いにこれを悲しみ、髪を剃って宗玄と号しました。ところが、元弘元年(1331年)に後醍醐天皇が隠岐の島より還幸されて、政を親(みずか)らせらるるに至り、親房は再び仕えることになりました。
時に足利高氏が反乱を起こし、延元元年には京師を犯し攻めましたから、親房は天皇の車駕に従って、延暦寺に赴きました。間もなく天皇が高氏の言を聞きて京師に帰られましたが、親房は高氏に従うことを欲せず、伊勢に向かいました。
延元三年(1338年)、親房の子、顕信(あきのぶ)が陸奥介鎮守府将軍となり、陸奥に赴くや、親房はこれを助けんとして出発しました。途中、海上にて台風に逢い、常陸の国に漂着し、そこにもまた敵兵が来り攻めましたので、親房は小田城へと向かいました。そこに隆良親王を迎えて、これを奉じておりましたが、城主小田治久が敵将高師冬(こうのもろふゆ)に降りましたから、親房もまた逃れました。逃れること数回に渡り、親房は止むなく吉野の行宮に還ったのでした。
その後も親房、一意王家の為に尽しましたが、不幸にも諸事、意の如くならず、正平九年(1354年)に賀名生(あのう)の行宮(あんぐう)にて薨じたのでありました。紆余曲折の人生ではありましたが、生前に親房が残した『神皇正統記』は大義名分を明らかにし、その後多くの憂国の志士の触れるところとなり、尊皇精神を世に伝えていったのであります。
『保建大記』は、崎門の栗山潜鋒(一六七一~一七〇六)が元禄二年(一六八九年)に著した書であり、『打聞』は、同じく崎門の谷秦山が『保建大記』を注釈した講義の筆録です。崎門学では、この『保建大記』を北畠親房の『神皇正統記』と並ぶ必読文献に位置づけております。そこでこの度弊会では本書(『保建大記』)の読書会を開催致します。詳細は次の通りです。
○日時 平成二十九年八月六日(日曜日)午後二時開始
○場所 弊会事務所(〒二七九の〇〇〇一千葉県浦安市当代島一の三の二九アイエムビル五階)
○連絡先 〇九〇(一八四七)一六二七
○使用するテキスト 『保建大記打聞編注』(杉崎仁編注、平成二一年、勉誠出版)
道義国家日本を再建する言論誌(崎門学研究会・大アジア研究会合同編集)