真木と彦九郎の遺児
彦九郎は幕府に追い詰められ、寛政五(一七九三)年六月二十七日、森嘉膳宅で自刃した。その三年後の寛政八(一七九六)年十一月十八日には、唐崎常陸介が、彦九郎の後を追って竹原庚申堂で自刃した。
さらに、享和二(一八〇二)年五月二日には、天草の西道俊が彦九郎の墓前で割腹している。道俊は、若い時代から彦九郎と結び、尊号宣下運動でも彦九郎と行動をともにしていた。しかし、寛政五年春、彦九郎が幕吏に追われて長崎へ逃れた際も道俊は行動をともにし、海路上京しようとした。しかし、果たさず虎口を脱して天草に逃れた。
彦九郎自刃後、ともに勤皇を語るべき友もなく、医を業として十年ほど過ごしていた。しかし、彦九郎の孤忠を思う心は如何ともし難く、ついに天草を出て久留米の森嘉膳宅に向かったのである。そして、自ら墓穴を彦九郎の墓前に掘り、自刃した。辞世は
欲追故人跡 孤剣去飄然
吾志同誰語 青山一片烟 山腰雅春『五和町郷土史第一輯』(昭和四十二年)
 道俊の墓は、彦九郎と同じ遍照院にある。ひょうたん型のお墓で、墓標は玄洋社の頭山満によるものだ。
道俊の墓は、彦九郎と同じ遍照院にある。ひょうたん型のお墓で、墓標は玄洋社の頭山満によるものだ。
彦九郎の長男儀助が久留米を訪れたのは、その翌年の享和三(一八〇三)年六月であった。後藤武夫の『高山彦九郎先生伝』には次のように描写されている。
〈後年先生屠腹の後、一子儀助、久留米に来つて、遍照寺畔なる父の墓を展した時も、石梁は彼を自家に宿せしめ、種々慰撫する所があつた。将に帰らんとするや、詩と涙とを以て之に贈つた、義心感ずべきものがある。
高山儀助自上野来展其考仲縄墓
留余家一句臨帰潜然賦贈
悲哉豪傑士。化作異郷塵。山海三千里。星霜十一春。憐君来拝墓。令我重沾巾。孝道期終始。慇懃愛此身。
情懐綿々として、慇懃極まりなきものがある。十有一年前、先生の死に対してそゝいだ其の涙は、今や孝子儀助の展墓によつて、再たび巾を霑さしめた。嘗て彦九郎先生の為に、
赤城仙子在人間。明月為衣玉作顔。怪得煙霞嚢底湧。躡来三十六名山。
を謳つた其の人が、遺孤の為に此詩を賦せんとは、恐らく石梁其の人もまた宿縁の浅からざるを感じたであらう〉
石梁は、文政三(一八二〇)年五月に「宮川森嘉膳小伝」を著し、彦九郎について記している。つまり、石梁は彦九郎の志を語り継いだ重要人物だったということである。
その八年後の文政十(一八二八)年に石梁は亡くなっているが、若き真木が樺島との接点を持っていた可能性はある。あるいは、石梁の思いを継ぐ者から、真木が彦九郎のことを伝えられた可能性もある。そして、真木自身が彦九郎への関心を強めていく。木村重任の『故人物語』によると、真木は天保九(一九三八)年頃、彦九郎の話を聞くために安達近江宅を訪れている。
そして、天保十三(一八四二)年正月、真木は「高山正之伝」を筆写・熟読した。彼は感慨を欄外に記し、哀悼の和歌を捧げている。その年の六月二十七日、木村重任等とともに、高山彦九郎没五十年に当たり祭典を行った。
そして真木は、まさに彦九郎の志を継ぐべく、立ちあがるのである。三上卓先生は、「真木の巡つた足跡こそ、実に高山先生が七十余年前に辿つた足跡ではなかつたか。吾人は先生の事跡を調査し了つて、更に真木の一生を見る時、その暗合に喫驚するものである」と書いている。
「三上 卓」カテゴリーアーカイブ
久留米勤皇志士史跡巡り② 高山彦九郎の同志・樺島石梁
真木と高山を繋ぐ宮原南陸

平成三十年四月十五日、筑後市水田に向かい、真木和泉が十年近くにわたって蟄居生活を送った山梔窩(くちなしのや)を訪れた。
やがて、真木は楠公精神を体現するかのように、行動起こすが、彼の行動は高山彦九郎の志を継ぐことでもあった。
真木は、天保十三(一八四二)年六月二十七日に、彦九郎没五十年祭を執行している。では、いかにして真木は彦九郎の志を知ったのであろうか。それを考える上で、見逃すことができないのが、合原窓南門下の宮原南陸の存在である。
文政七(一八二五)年、真木が十二歳のとき、長姉駒子が嫁いだのが、南陸の孫の宮原半左衛門であった。こうした縁もあって、真木は、半左衛門の父、つまり南陸の子の桑州に師事することになった。ただし、桑州は文政十一(一八二九)年に亡くなっている。しかし、真木は長ずるに及び、南陸、桑州の蔵書を半左衛門から借りて読むことができた。これによって、真木は崎門学の真価を理解することができたのではなかろうか。
一方、彦九郎の死後まもなく、薩摩の赤崎貞幹らとともに、彦九郎に対する追悼の詩文を著したのが、若き日に南陸に師事した樺島石梁であった。石梁こそ、彦九郎の志を最も深く理解できた人物だったのである。
石梁は、宝暦四(一七五四)年に久留米庄島石橋丁(現久留米市荘島町)に生まれた。これが、彼が石梁と号した理由である。三歳の時に母を亡くし、二十五歳の時に父を亡くしている。家は非常に貧しかったが、石梁は学を好み、風呂焚きを命じられた時でさえ、書物を手にして離さなかったほどだという(筑後史談会『筑後郷土史家小伝』)。
天明四(一七八四)年江戸に出て、天明六年に細井平洲の門に入った。やがて、石梁は平洲の高弟として知られるようになった。石梁は寛政七(一七九五)年に久留米に帰国した。藩校「修道館」が火災によって焼失したのは、この年のことである。石梁は藩校再建を命じられ、再建された藩校「明善堂」で教鞭をとった。 続きを読む 久留米勤皇志士史跡巡り② 高山彦九郎の同志・樺島石梁
久留米勤皇志士史跡巡り①
竹内式部・山県大弐の精神を引き継いだ高山彦九郎
平成30年4月15日、崎門学研究会代表の折本龍則氏、大アジア研究会代表の小野耕資氏とともに、久留米勤皇志士史跡巡りを敢行。崎門学を中心とする朝権回復の志の継承をたどるのが、主たる目的だった。
朝権回復を目指した崎門派の行動は、徳川幕府全盛時代に開始されていた。宝暦六(一七五六)年、崎門派の竹内式部は、桃園天皇の近習である徳大寺公城らに講義を開始した。式部らは、桃園天皇が皇政復古の大業を成就することに期待感を抱いていた。ところが、それを警戒した徳川幕府によって、式部は宝暦八(一七五八)年に京都から追放されてしまう。これが宝暦事件である。
続く明和四(一七六七)年には、明和事件が起きている。これは、『柳子新論』を書いた山県大弐が処刑された事件である。朝権回復の思想は、幕府にとって極めて危険な思想として警戒され、苛酷な弾圧を受けたのだ。特に、崎門の考え方が公家の間に浸透することを恐れ、一気にそうした公家に連なる人物を弾圧するという形で、安永二(一七七三)年には安永事件が起きている。
この三事件挫折に強い衝撃を受けたのが、若き高山彦九郎だった。彼は三事件の挫折を乗り越え、自ら朝権回復運動を引き継いだ。当時、朝権回復を目指していた光格天皇は実父典仁親王への尊号宣下を希望されていた。彦九郎は全国を渡り歩いて支持者を募り、なんとか尊号宣下を実現しようとした。結局、幕府の追及を受け、寛政五(一七九三)年に彦九郎は自決に追い込まれた。 続きを読む 久留米勤皇志士史跡巡り①
明治政府による「大和魂」の殺戮─『藻潭餘滴─古松簡二先生逸詩』井上農夫跋
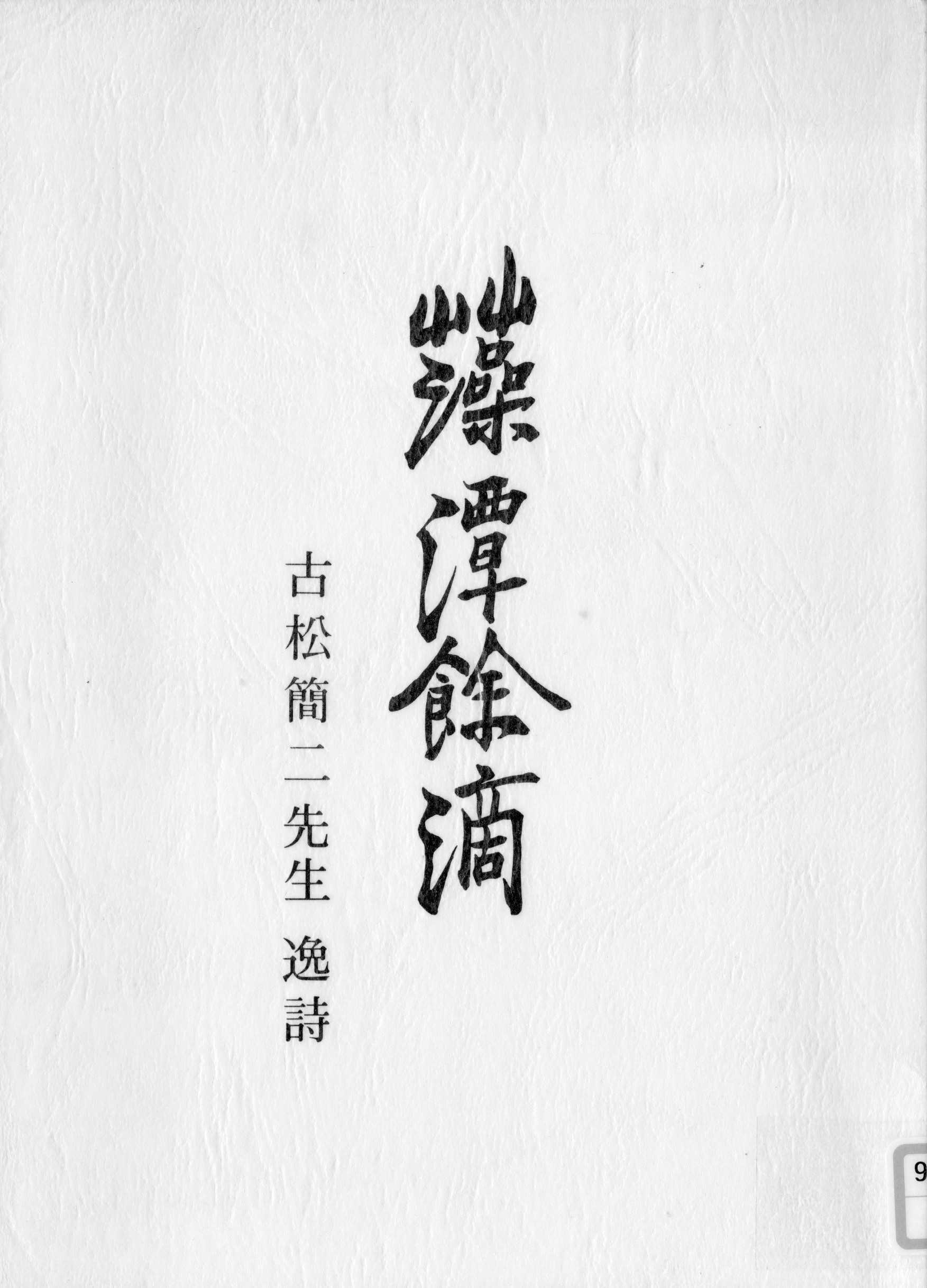 明治政府が遅くとも明治四年には維新の精神を裏切ったことは、筑後の勤皇志士・古松簡二(一八三五~一八八二年)の行動によっても知られる。
明治政府が遅くとも明治四年には維新の精神を裏切ったことは、筑後の勤皇志士・古松簡二(一八三五~一八八二年)の行動によっても知られる。
古松は筑後崎門学の先人・高山畏斎の流れをくむ会輔堂に学び、文久三(一八六三)年に脱藩上京、国事に奔走するようになった。元治元 (一八六四)年三月には水戸尊攘派 (天狗党) の挙兵に参加している。慶応二年には幕兵に捕えられ、三年間獄につながれた。
そして、維新後の明治四年、小河真文らの同志とともに維新の精神を裏切る明治政府転覆を計画して捕らえられ、終身禁獄の宣告を受け、東京石川島の獄に服役した。明治十五年(一八八二)六月十日、獄中でコレラ感染して死去した。
大東亜戦争下の昭和十九年二月、古松の逸詩に小伝などを加え『藻潭餘滴─古松簡二先生逸詩』が刊行された。藻潭とは古松の号である。同書編纂には筑後郷土史の大家・鶴久二郎と、井上農夫が協力した。井上は、三上卓先生の『高山彦九郎』(昭和十五年刊)著述に全面的に協力した人物であり、権藤成卿の流れをくむ思想家、郷土史家である。『藻潭餘滴』序には、井上が頭山満翁門下であり、宮崎来城の高弟でもあったと記されている。
同書跋文において、井上は明治政府が明治四年以来、維新の原動力となった大和魂を殺戮してきたと次のように批判している。
〈(古松)先生の物に拘泥せず洒々落々たる襟胸と真贄熱烈なる憂国の至誠にひしひしと感慨胸をうたれるものがある。先生入獄以来獄死に至る十一年間は誠に東洋的政道と西欧模倣政治思想との激烈なる闘争の時期であつた。先生がそれによつて命を殞された明治四年事件を皮切りとして十年の西南戦争を筆止めにするの幾多の国事犯事件は幕末初期勤皇家の純誠なる道統を承継いだ無数の「大和魂」の殺戮史である。
頭山翁も云はれる如く明治十年までに日本の大木が皆切り倒されて、其後の日本は宛かも神経衰弱みたいに、左によろめき右に傾むき、ふらふら腰の情無い有様になつたのである。古松先生も亦、頭山翁の所謂大木の一人であること勿論である〉(原文カタカナ)
高山彦九郎と久留米⑥─三上卓先生『高山彦九郎』より

●高山畏斎の学問を継いだ「継志堂」
高山彦九郎は、寛政三(一七九一)年十一月に、上妻郡津江村(現八女市津江)の「継志堂」を訪れている。三上卓先生は、この訪問について次のように書いている。
「飄然として此地を訪れた先生は、同塾及び(高山)畏斎の高弟の一人たる郷士牛島毅斎の家に宿つて、畏斎の高弟達と会談し、尊皇の大義を提唱し、毎夜屋上に登つた天文を観測したと伝えられる」
このとき彦九郎は、「筑後の文武は上妻にあり」と賛嘆したとも伝えられている。
継志堂は、崎門の高山畏斎(金次郎)の私塾「高山塾」を継承する形で、彼の門人たちが設立した塾である。畏斎は崎門の三宅尚斎派の留守希斎に学んだ。また、三上先生は、畏斎が「垂加学を長峡蟠龍に受けた」と書いている。
畏斎は、「人は勉強しなければだめだ。学問とは、生命の理、日常の努め、古今治乱興亡の事跡など、何もかも知り尽くしてその知識を活用することである。書物にとらわれたものでなく、生きた学問をせよ」と教えていたという。
天明七(一七八七)年に来遊した仙台の碵学志村東蔵が、畏斎に対する門人たちの追慕の情の厚さに感じ、「継志堂」と命名したという。その後、畏斎の門人達は、八幡村の会輔堂(今村竹堂)、黒木の楽山亭(古賀貞蔵)、津ノ江および忠見の三省堂(牛島毅斎のち川口省斎)を設け、崎門の学風を広めた。
ここで特に注目されるのが、今村竹堂が畏斎に学んだだけではなく、崎門正統派の西依成斎にも学んでいたことである。そして、今村竹堂の長女と上妻郡溝口村の医師清水濳龍の間に生まれたのが、明治四年の久留米藩難事件で終身禁獄の宣告を受けた古松簡二(清水真郷)(☞参照:古松簡二①─篠原正一氏『久留米人物誌』より)である。
高山彦九郎と久留米⑤─三上卓先生『高山彦九郎』より
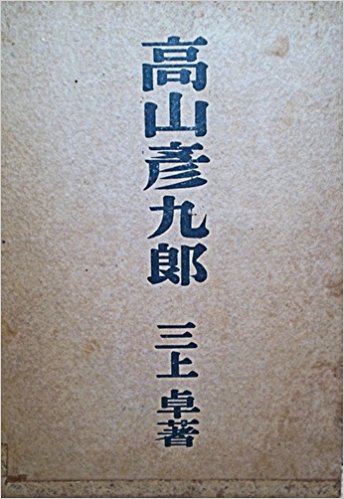
●亀井南冥の都府楼碑銘
唐崎常陸介は、寛政二(一七九〇)年末頃、久留米に入り、有馬主膳の茶室「即似庵」を訪れた。『高山彦九郎』(三上卓先生)には、当時、主膳から唐崎に宛てた書簡が引かれている(百八十二頁)。
「爾来隣国所々御経過の次第、尾関方へ御細書被下、是亦□致伝承候、筑前にては竹田、亀井等へも御出会被成候よし……此節猶更先生の大名致光輝、中津の雅会は寔に活斗於小生も不堪雀躍奉在候」とあり、さらに「大宰府碑銘等御見せ被下、思召忝在候」とある。
三上先生は、ここにある「大宰府碑銘」について、〈或は亀井南冥黜貶の理由となつた有名なる都府楼碑銘であらうか。同銘の序文の末尾に「伏シテ惟フニ当今封建ノ国邑、名器古ニ非ズ」と封建制度の我國體と相容れないのを道破した南冥の見識は、恐らく諸国に於ける 尊皇同志の間に歓迎賞賛されたことであらう〉と書いている。
☞[続く]
高山彦九郎と久留米④─三上卓先生『高山彦九郎』より
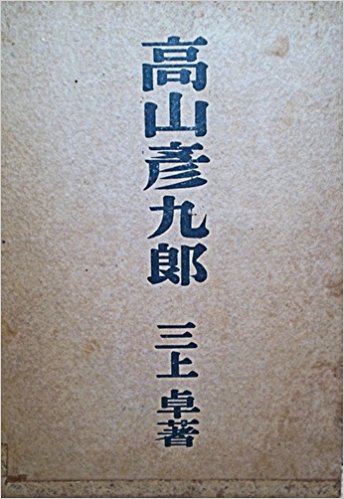
●即似庵継承の精神
『高山彦九郎』(三上卓先生)は、久留米藩国老・有馬主膳の茶室「即似庵」を「九州の望楠軒」と称した。同書には、即似庵遺跡の写真を掲載し、以下のような説明を付している。
「高山、唐崎両先生が久留米の同志と密談した即似庵遺跡は久留米市東櫛原町久留米商業学校裏手にある。附近一帯の老樟欝蒼たる地は国老有馬主膳の別邸跡にして、即似庵なる茶室は左端の家屋(現住者は久留米新勤王党の同志の一人たる林田瀬兵衛守隆の子息峰次氏)の位置にありしも、維新後市内篠山町中学明善校裏門附近に移され、稲次亥三郎翁居住さる。翁は真木和泉守門下の高足たる稲次因幡の後嗣、因幡は佐幕派の弾圧に逢ひて憤死せし勤王家なり」
林田守隆は、慶応4(1868)年正月、小河真文ら勤皇派の同志とともに、親幕派の参政不破美作暗殺に参加。久留米藩で組織された「応変隊」の小隊長として戊辰戦争に従軍し、箱館戦争で功を立てた人物である。
明治4(1871)年の久留米藩難に際しては、藩知事有馬頼咸の命を受け、本庄一行とともに東京から久留米に派遣され、水野正名や小河真文らと交渉し、事態の収拾にあたった。晩年は真木保臣先生顕彰会会長などに推戴された。
☞[続く]
高山彦九郎と久留米③─三上卓先生『高山彦九郎』より
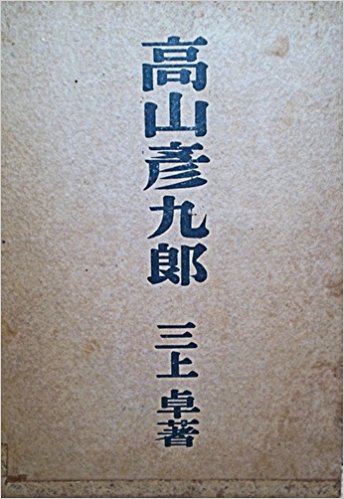
●垂加神道の伝書を伝えた唐崎常陸介
久留米への崎門学の浸透において、高山彦九郎の盟友・唐崎常陸介は極めて重要な役割を果たした。
唐崎は、寛政二(一七九〇)年末頃、久留米に入り、櫛原村(現久留米市南薫町)の「即似庵」を訪れた。即似庵は、国老・有馬主膳の茶室である。主膳は崎門派の不破守直の門人である。不破は、久留米に崎門学を広げた合原窓南門下の岸正知のほか、崎門学正統派の西依成斎にも師事していた。
即似庵は、表千家中興の祖と言われる如心斎天然宗左の高弟・川上不白の設計により、寛政元年に起工し、寛政二年秋に落成した。三上卓先生の『高山彦九郎』には、次のように描かれている。
「主膳此地に雅客を延いて会談の場所とし、隠然として筑後闇斎学派の頭梁たるの観あり、一大老楠の下大義名分の講明に務め、後半世紀に及んでは其孫主膳(守善)遂に真木和泉等を庇護し、此別墅(べっ しょ)を中心として尊攘の大義を首唱せしめるに至つたのである。此庵も亦、九州の望楠軒と称するに足り、主人守居も亦これ筑後初期勤王党の首領と称すべきであらう。
唐崎、此地に滞留すること五十余日、主人守居を中心とせる闇斎学派の諸士、不破(実通)、尾関(守義)、吉田(清次郎)、田代(常綱)等及国老有馬泰寛、高良山蓮台院座主伝雄、樺島石梁、権藤涼月子、森嘉善等と締盟し、筑後の学風に更に一段の精采を付与した。…唐崎より有馬主膳に伝へた垂加神道の伝書其他の関係文献は今尚後裔有馬秀雄氏の家に秘蔵されて居る…」
有馬秀雄は、明治二年に久留米藩重臣・有馬重固の長男として生まれ、帝国大学農科大学実科卒後、久留米六十一銀行の頭取などを務めた。その後、衆議院議員を四期務めた。
唐崎から有馬主膳に伝えられた文献のうち、特に注目されるのが、伝書の末尾に「永ク斯道ニ矢ツテ忽焉タルコト勿レ」とある文言と、楠公父子決別の図に賛した五言律の詩である。
百年物を弄するに堪へたり。惟れ大夫の家珍。孝を達勤王の志。忠に至る報国の臣。生前一死を軽んじ。身後三仁を許す。画出す赤心の色。図を披いて感慨新なり
さらに、唐崎は垂加流兵学の伝書も伝授したらしい。
☞[続く]
高山彦九郎と久留米②─三上卓先生『高山彦九郎』より
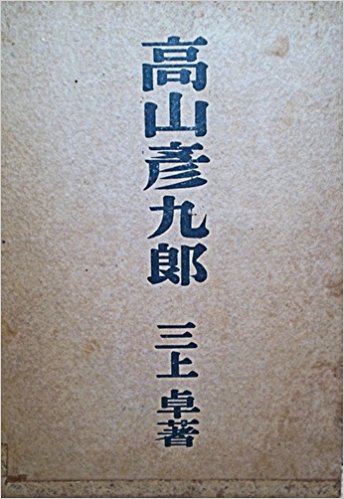 『高山彦九郎』(三上卓先生)は次のように、久留米における崎門学の浸透を描いている。
『高山彦九郎』(三上卓先生)は次のように、久留米における崎門学の浸透を描いている。
●極点に達していた久留米の唐崎熱
〈しかも彼(合原窓南)が京都に師事した人は絅斎先生浅見安正であつた。蓋し佩刀のハヾキに赤心報国の四文字を刻し、平生特に大楠公を崇拝し、生涯遂に幕府の禄を食まなかつた闇斎の大義名分の思想は、窓南の教育によつて或は久留米城下に於て、或は上妻の僻村に於て、上は士大夫より下は農村の青年に至るまで、漸々として浸潤したのである。窓南先生こそ久留米藩学祖と称すべきであらう。
すなはち藩の名門岸正知、稲次正思、教を窓南に乞ひて夙に名あり、藩士不破守直、杉山正義、宮原南陸も亦錚々の聞えあり、広津藍渓は上妻郡福島村の青年を以て馬場村退隠中の窓南門下より傑出した。そして不破守直は更に若林強斎門下の西依成斎及び松岡仲良門下の谷川士清に就いて教を受け、不破の門下に有馬主膳、尾関権平、不破州郎等あり、正義の子に杉山正仲あり、南陸は子に宮原国綸あり、弟子に樺島石梁あり、……しかも窓南の影響はこれのみには止まらなかつた。彼の退隠地馬場村の隣村津江の貧農に生れた青年高山金二郎は、夙に発奮して学に勉め、宝暦年間遂に崎門三宅尚斎の高足たる大阪の硯儒留守希斎の門に遊んで、……留学百カ日にして崎門学の大事を畢了して故郷に帰り、門下に幾多の青年を養成したのであるが、天明三年藩儒に登用され、同年不幸病歿した。享年五十八。けだし窓南歿後の窓南とも称すべきである。後世その号を以て之を敬称して高山畏斎先生と云ふは此人である。
窓南先生の遺業は斯の如く広大であつた。かくて久留米一藩の支配的学風は全く崎門学派の影響下に在り、寛政、享和の頃に至つては、崎門の学徒は士民の隔てなく尨然たる交遊圏を構成し、名を文学に仮つて陰に大義名分の講明に務めて居たのである。唐崎常陸介が来遊したのも此時、高山先生が来訪したのも此時。そして寛政二年秋の唐崎の第一回久留米来遊は、この学的傾向を決定的に灼熱化し以て高山先生の来遊を準備したのであつた〉
三上先生は、以上のように指摘した上で、尾関権平が湯浅新兵衛に宛てた書簡に基づいて、唐崎と久留米藩士との交遊は、伊勢の谷川士清を通じて、既に天明年間から十数年間の文通によって用意されていたと述べている。そして、寛政二年初秋頃、尾関権平や不破州郎らが唐崎に宛てたと思われる書簡を引いて、「久留米に於ける唐崎熱はその極点に達して居たことが窺われる」と述べている。
☞[続く]
高山彦九郎と久留米①─三上卓先生『高山彦九郎』より
●なぜ久留米が高山彦九郎終焉の地となったのか
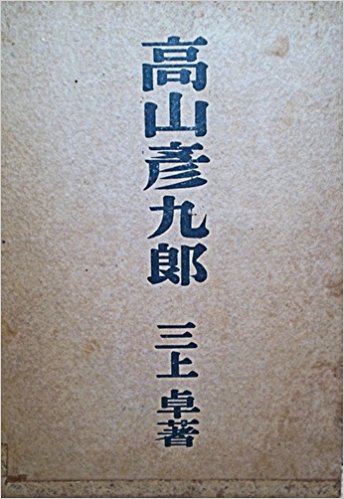 なぜ久留米が高山彦九郎終焉の地となったのか。それは、久留米における崎門学の興隆抜きには語ることができない。特に、この地の崎門学浸透を主導した合原窓南・その門人と、彦九郎の盟友・唐崎常陸介との交流は大きな意味を持っていた。
なぜ久留米が高山彦九郎終焉の地となったのか。それは、久留米における崎門学の興隆抜きには語ることができない。特に、この地の崎門学浸透を主導した合原窓南・その門人と、彦九郎の盟友・唐崎常陸介との交流は大きな意味を持っていた。
自ら昭和維新運動に挺身した三上卓先生が、『高山彦九郎』(平凡社、昭和15年)を著したのは、昭和維新運動を高山彦九郎から真木和泉に至る朝権回復運動の継承と位置付ける意識が強まったからだと考えられる。『高山彦九郎』は、権藤成卿門下で久留米史研究者の井上農夫が収集した史料に基づいて書かれており、九州における崎門学派の思想と運動の展開について独自の意義づけをしている。
同書に基づきながら、久留米が彦九郎終焉の地となった意味について考察していきたい。同書は合原窓南の役割に注目し、合原に師事した広津藍渓が書いた碑文を引いている。
「先生生れて顛悟、自ら読書を好み、年十一出家僧と為り法を四方に求む。既に壮にして自ら其非を悟り、蓄髪儒と為り、講学愈々篤く、礪行益々精しく、名一時に震ふ。吾藩宋学の盛んなる、蓋し先生先唱を為せば也。寛永六年、梅巌公(第六代藩主・有馬則維、引用者)召して俸を賜ひ、以て学を士大夫に授けしむ。生徒日に夥し、居ること十余年疾を以て隠を上妻郡馬場村に請ふ。是に於て国老以下諸士、相追随して道を問ふ者日夜絶えず、僕従衢を塡む。大悲公(第七代藩主・有馬則維)立を延いて侍講と為し、更に稟米二十口を給し、秩竹間格に班す。又其老ひたるを優し、籃輿(らんよ)に乗つて以て朝し、且つ朝に在つて帽を著し寒を禦ぐを許す、蓋し異数と云ふ。元文二年八月二十日疾をもて卒す、享年七十五。〉
☞[続く]