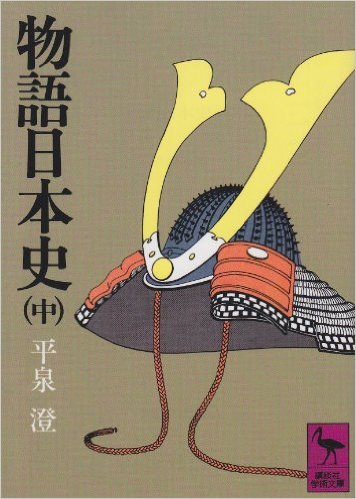 後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。
後鳥羽上皇について、平泉澄先生は『物語日本史 中』(講談社学術文庫)において、次のように書かれている。
〈……ことに朝廷の盛大であったころの儀式や故実を御研究になり、その討論や練習を御下命になり、また上皇御みずから著述をなさいました。それは世俗浅深秘抄(せぞくせんしんひしょう)という上下二巻の書物で、朝廷の儀式作法を記して、それに批判を下されたものでありますが、その批判の規準となったものは、延喜・天暦、すなわち醍醐・村上両天皇の御日記であります。してみると、後鳥羽上皇は、延喜・天暦の御代にかえそうとの御希望をおもちになり、この御理想の実現のために、文武の両道を、御自身も御研究になれば、公卿達にも研究鍛錬せしめられたのであることが分ります。朝廷が高邁なる理想をいだき、雄大なる計画を立てられて、国家の健全性を回復しようと努力せられ、公卿が文武の両道に出精してくるとなれば、幕府はもはや無用のものとなるでしょう。いや、無用であるばかりでなく、有害なものといってよいでしょう〉
「国体思想」カテゴリーアーカイブ
小野耕資氏「陸羯南の国家的社会主義」(『国体文化』平成28年5月号)
権藤宕山(栄政)と『南淵書』
権藤成卿は『自治民政理』(昭和11年)で、南淵書について次のように書いている。
〈予は先づ此に大化新政の本源を探求し、南淵先生のことを略叙し、古今を一貫せる偉人の一班を、窺看することゝしよう。
南淵先生のことは、正史の表面には、中大兄皇子、中臣鎌足を従へさせられ、南淵先生の所に至り、周孔の教を学ばんと請はせられた一節が見えて居る丈けである。併し後世学者間に於て、古文献を渉猟せし林道春、貝原益軒等の時代に至り、先生を王仁の次に置く様になつた。人名辞書に、推古朝隋に遊び、経術を以て称せられ、書百余巻を著はせリ、其書今伝はらずとあるは、道春の考索を採録したものであらう。意ふに近江朝倒覆の後、当時の事蹟が頻りに抹殺されたことは、疑ふべくもないことであつて、天智天皇の御遺著百巻余、東寺に其目録を留めてある計りで、一冊も伝はつて居らぬ。南淵先生の事歴及びその遺著の焚滅に帰したのも、此の時代に於ける、心なき官僚のなしたことゝ考へらるゝ。
但だ幸にも南淵書二巻が、制度家の秘籍として大中臣家に伝へられ、元禄中同家の家難に依り、庶長子の友安と云ふ人が、筑後の蓮台僧正の下に隠れ、帰雲翁と称し制度律令の学問を権藤宕山に伝へ、南淵書を授与したものである。
(中略) 続きを読む 権藤宕山(栄政)と『南淵書』
長野朗の制度学─仮説「制度学と崎門学の共鳴」
昭和維新のイデオローグ権藤成卿は「制度学者」と称された。筆者は、その学問がいかなるものであったかを考察する上で重要な視点が、権藤の思想と崎門学の関係ではないかという仮説を立てており、権藤と崎門学の関係について「昭和維新に引き継がれた大弐の運動」(『月刊日本』平成25年10月号)で論じたことがある。
「制度学者」としての権藤の思想の継承者として注目すべきが、長野朗である。長野について、昭和維新運動に挺身された片岡駿先生が次のような記事を書き残されている。
〈制度学者としての長野氏は南渕学説の祖述者として知られる権藤成卿氏の門下であり、而も思想的には恐らく最も忠実な後継者であるが、然し決して単なる亜流ではなく、ある意味において先師の域を超えてゐる、特に例へば権藤学説に所謂『社稷体統』をいかして現代に実現するかといふ具体的経綸や体制変革の方法論について、権藤氏自身は殆ど何一つ教へることが無かつたが、長野氏は常に必ずそれを明示して来た。権藤成卿を中心とする自治学会に自治運動が起らず、長野朗氏の自治学会が郷村自治運動の中核となり得た理由も茲に在つた。郷村運動の中心的指導者だつた長野氏は亡くなられたが、故人が世に遺したこの『自治論』が世に広まれば、民衆自治の運動は必ず拡大するに違ひないと私は信ずる。
○民衆自治の風習は神武以来不文の法であつたが、その乱れを正して道統を回復し、且つそれを制度化して「社稷の体統」たらしめたものが大化改新でありそれを契機とする律令国家だつた。所謂律令制国家は大化改新の理想をそのまま実現したものではないが、而もこのやうな国家体制の樹立によつて、一君万民の国民的自覚が高められて行つたことは疑ひ得ない。その律令制国家体系も軈て「中央」の堕落と紊乱を原因として崩壊の過程を辿り、遂に政権は武門の手に握られることになつたが、然し、そのやうな政治的・社会的混乱の中においても、大化改新において制定された土地公有の原則と、村落共同体における自治・自衛の権は(一部の例外を除いて)大方維持せられ、幕末に至るまで存続した。而も此間自治共同体は次第に増殖し、幕末・維新の時点では実に二十万体に近い自治町村と、それを守る神社が存在したのである。大化以来千二百年の間に幾度が出現した国家・国体の危機を救ふた最大の力の源泉も、このやうな社稷の体統にあつたことを見逃してはならぬ。この観点から見るとき、資本主義制度の全面的直訳的移入によつて土地の私有と兼併を認め、中央集権的官僚制度の強化のために民衆自治の伝統を破壊して、社稷の体統を衰亡せしめた藩閥政治の罪は甚大である。 続きを読む 長野朗の制度学─仮説「制度学と崎門学の共鳴」
片岡駿先生「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号)
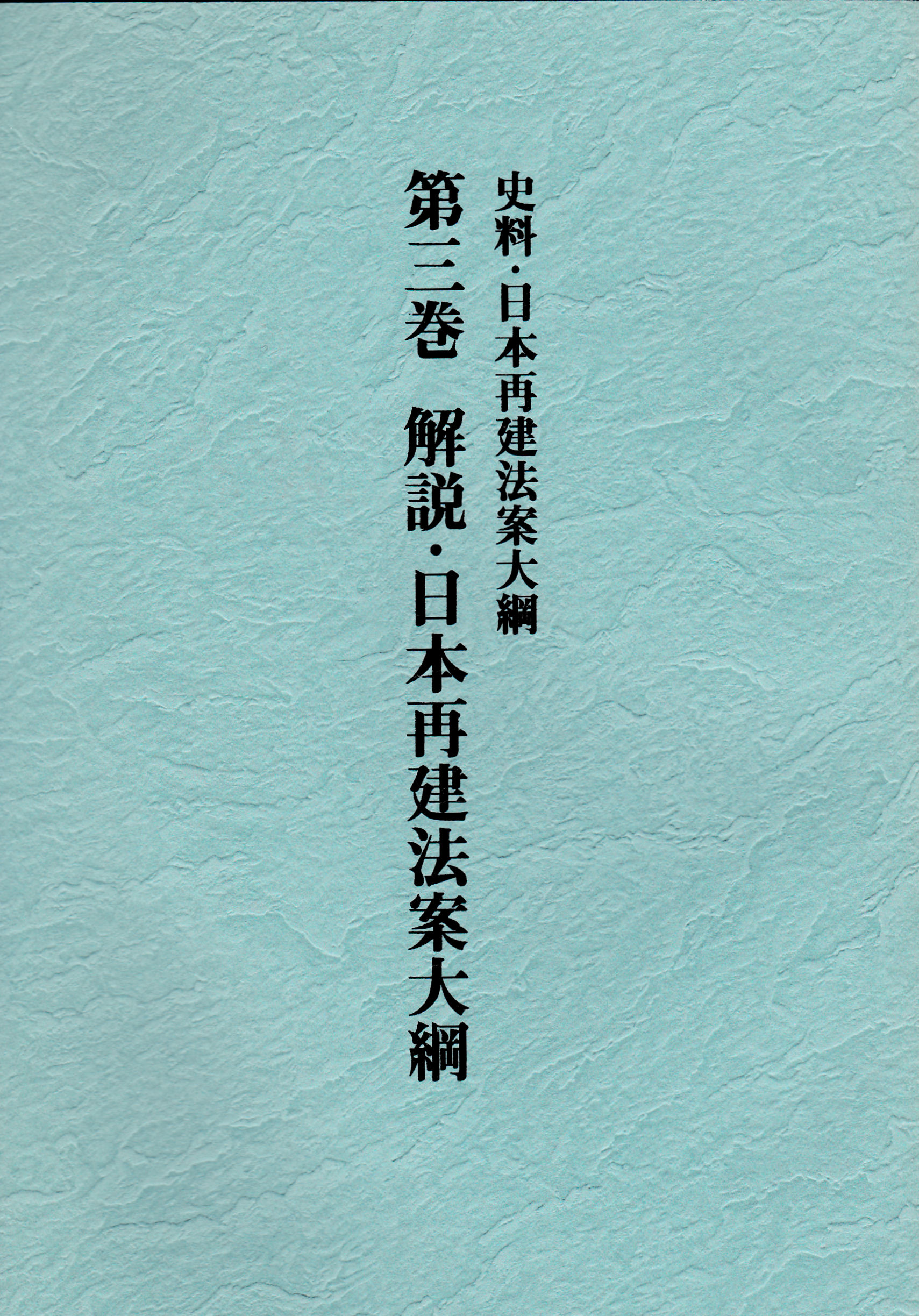 昭和維新運動に挺進された片岡駿先生は、「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号、『史料・日本再建法案大綱 第三巻収録)と題して、次のように書かれていた。
昭和維新運動に挺進された片岡駿先生は、「自民党幕府」(『新勢力』昭和51年1月号、『史料・日本再建法案大綱 第三巻収録)と題して、次のように書かれていた。
〈国際共産主義侵略の脅威は元より之を無視することはできぬ。従つてその第五列部隊たる国内革命勢力の一掃は、日本再建のための必須の要件であることは勿論であるが、その目的を達成するためには、「占領憲法」といふ化け物を先づ処分せねばならぬと云ふ自明の理と、而もこの亡国憲法を自己立脚の基盤として死守してゐるものが、外ならぬ自由民主党其者であることに思ひ至るとき、政府、自民党と結んで「反共」の戦線に立つといふごとき戦術が如何に愚劣なものであるかは自ら明かである。
時代の如何を問はず、日本に於て維新とは、現実に政権を私して国体を危くする亡国的勢力を打倒して、天皇大権の下に国政を一新することである。現実不断に天皇(天皇制)と国体を危ふくせしめつつあるポツダム体制と占領憲法の温存を図り、それを基盤とする権力の頂点に立つものが自民党政府である限り、維新陣営が打倒の目標とすべき現代幕府勢力が、そこに在ることは明々白々である。討幕の無い維新は戯論に過ぎぬ。若しこの眼前の幕府を討つことを図らずして、徒らに維新を叫ぶ者があれば、国民を愚弄し自己を冒瀆するものと云はねばならぬ〉
北条泰時の不臣(承久の悲劇)を批判した崎門学派
 明治維新を成し遂げた幕末の志士には、建武中興の挫折と、さらに遡って承久の悲劇、後鳥羽、土御門、順徳の三天皇の悲劇に対する特別な思いがあった。だからこそ、明治六年には、御沙汰により、三天皇の御神霊を奉迎することとなったのである。御生前御還幸の儀を以て、厳重なる供奉を整えて、水無瀬宮へ御迎え申し上げ、三天皇を合せて奉祀した。
明治維新を成し遂げた幕末の志士には、建武中興の挫折と、さらに遡って承久の悲劇、後鳥羽、土御門、順徳の三天皇の悲劇に対する特別な思いがあった。だからこそ、明治六年には、御沙汰により、三天皇の御神霊を奉迎することとなったのである。御生前御還幸の儀を以て、厳重なる供奉を整えて、水無瀬宮へ御迎え申し上げ、三天皇を合せて奉祀した。
北畠親房の『神皇正統記』の後、承久の悲劇に思いを寄せたのは、崎門学だった。その重大な意義を、平泉澄先生門下の鳥巣通明先生は、『恋闕』において、次のように書かれている。
〈…神皇正統記をうけて、徳川政権下にもつとも端的明確に泰時を糾弾したのは山崎闇斎先生の学統をうけた人々であつた。崎門に於いて、北条がしばしばとりあげられ批判せられたことは、たとへば、「浅見安正先生学談」に
北条九代ミゴトニ治メテモ乱臣ゾ
また、
名分ヲ立テ、春秋ノ意デミレバ北条ノ式目ヤ、足利ガ今川ノ書は、チリモハイモナイ
などと見えることによつても明らかである。当代の人々ばかりでなく久しきにわたつて世人を瞞着した「北条の民政」は、こゝにはじめて 皇国の道義によつて粉砕せられたのであつた。この批判の語調のはげしさの理由は、もしわれわれにして皇民としての感覚を喪失せざる限り、たゞ年表を手にして
一二二一(承久三) 承久の役、後鳥羽・順徳・土御門上皇遷幸
一二三一(寛喜三) 上御門上皇阿波にて崩御、宝算三十七
一二三二(貞永元) 幕府式目五十一ヶ条を制定す
一二三九(延応元) 後鳥羽上皇隠岐に崩御、宝算六十
一二四二(仁治三) 北条泰時死
順徳上皇佐渡に崩御、宝算四十六
と読みあげるだけで十分了知できるであらう。
所謂「貞永式目の日」を 三上皇に於かせられては絶海の孤島にわびしくお過し遊されたのであるが、しかもこれほどの重大事を恐懼せず、慙愧することなくしで北条の民政をたゝへた時代がかつてあつたこと、否、それをたゝへる人々が現に史学界の「大家」として令名をほしいままにしてゐるのを思ふ時、それ等の人々の尊皇と民政を二元的に見る立場、不臣の行為すら「善政」によつて償はれるとする立場をきびしく批判した崎門学派の日本思想史上に占むる地位はおのづから明らかであらう〉
坪内隆彦「『東亜百年戦争』史観を発信せよ」(『伝統と革新』22号)
玉川博己氏「三浦重周の思想~とくに国体論を中心として」
 2016年3月に、三島由紀夫研究会事務局編『決死勤皇 生涯志士の人 三浦重周を語るシンポジウム』を贈呈していただいた。
2016年3月に、三島由紀夫研究会事務局編『決死勤皇 生涯志士の人 三浦重周を語るシンポジウム』を贈呈していただいた。
玉川博己氏(三島由紀夫研究会代表幹事)の基調講演録「三浦重周の思想~とくに国体論を中心として」は、三浦重周氏の国体思想のうち、「戦後、国体は維持されたのか」という問題意識、そして「国体と皇道の発展は国境を超えるのか」という問題意識の重要性を指摘している。玉川氏は、三浦氏が今泉定助の世界皇化の思想に注目していたことを指摘した上で、次のように語っている。
「このように三浦重周が理想とする皇道とは、決して排他的、独善的な偏狭思想ではなく、明治以来のアジア主義の伝統を受け継ぎつつ、日本の歴史・伝統・文化に根ざす天皇を中心とするわが国体の倫理性と普遍性をあまねく世界に宣布してゆこうというスケールの大きな考えに立脚するものです」
三浦氏の国体思想を改めて研究する必要があると痛感した。
坪内隆彦「幕末志士の国体観と死生観」
川面凡児『建国の精神』目次

川面凡児『建国の精神』(稜威会本部、大正7年)目次。神道的宇宙観において、今泉定助に対する川面の影響が窺われる。
(一) 発端
(二) 目録
(三) 天壌無窮の神勅と神籬磐境の神勅との表裏
(四) 神代の世界的活動と奈良朝以後の島国的蟄伏
(五) 日本民族性、国民性と宇宙観、天地観、世界観、原人観、霊魂観、処世観
(六) 我と彼とはその究明を異にする事
(七) 唯一不二の根本大本体と世界列国の言語名称解釈
(八) 宇宙根本信念と国家統一と民族の興廃
(九) 日本民族の宇宙万有観
(十) 天神中主太神と空間、対象、宇宙 続きを読む 川面凡児『建国の精神』目次


