反ジャーナリストの高橋清隆氏に「高橋清隆の文書館」(平成28年10月8日)で、拙著『GHQが恐れた崎門学』の書評をしていただいた。
 畏友の坪内隆彦氏が新著を発表された。山崎闇斎(あんさい)を祖とする崎門学(きもんがく)が、いかに明治維新の原動力となったかを、幕末の志士たちの生き様、いや死に様を通して明らかにしている。
畏友の坪内隆彦氏が新著を発表された。山崎闇斎(あんさい)を祖とする崎門学(きもんがく)が、いかに明治維新の原動力となったかを、幕末の志士たちの生き様、いや死に様を通して明らかにしている。
坪内氏は自身が編集長を務める『月刊日本』で、平成24年7月から「明日のサムライたちへ」と題する連載記事を書いた。明治維新とその後の昭和維新運動にも影響を与えた10の國體思想の重要書を紹介されたが、同書はそのうちの5冊を軸に再編収録している。
具体的には、浅見絅斎(あさみ・けいさい)の『靖献遺言(せいけんいげん)』、栗山潜鋒(せんぽう)の『保健大記(ほうけんたいき)』、山県大弐の『柳子新論』、蒲生君平(がもう・くんぺい)の『山陵志(さんりょうし)』、頼山陽の『日本外史』を指す。
「これらの書物なくして、明治維新はなかったと言っても過言ではないと考えています。これらの『聖典』には何が書かれていたのか、そして、志士たちの魂をいかに激しく揺さぶったのか、それを本書で解き明かしていきます」と始めている。
崎門学は、万世一系の天皇による親政を理想とする。闇斎は「徳を失った天子は倒していい」とする易姓革命論を否定する形で朱子学を受容し、さらに伊勢神道、吉田神道、忌部神道を吸収し、自ら垂加神道を樹立している。
闇斎は、皇政復古の志を出処進退によっても暗に示している。仕えていた会津藩主の保科正之が死去すると、会津藩の俸を辞し、亡くなるまで京の地を出なかった。弟子の浅見絅斎も「世は既に終身関東の地を踏まず、食を求めて大名に事(つか)へずと誓へり」と語っていた。 それにしても、武士の生き方は壮絶だ。収録の志士たちの最期も多分に漏れない。その1つとして、梅田雲浜(うんぴん)の例を挙げておく。小浜藩士の雲浜はペリー来航に危機感を抱き、藩主の酒井忠義(ただあき)に「藩政の得失と外寇防御」の上書を提出するも、怒りに触れて藩籍を奪われる。
雲浜は外国の打ち払いと、京都御所の警備を固めるため勤皇の志篤い十津川郷士の指導訓練に乗り出す一方、危険覚悟で条約反対と慶喜擁立、井伊直弼排斥を主張し、朝廷に入説。彼の行動は大きな成果を上げる。
しかし、危機感を抱いた井伊は弾圧に乗り出す。京都所司代に就いていた酒井忠義が雲浜逮捕に踏み切った。そうして拷問を受けながら節を曲げず、1年後に牢屋で生涯を閉じる。
雲浜は吉田松陰から「『靖献遺言』で身を固めた男」と呼ばれていた。この書には中国の忠孝義烈の志8人が紹介されているが、特に方孝孺(ほうこうじゅ)に影響を受けた可能性を坪内氏は指摘する。建文帝の側近として活躍していた方孝孺は、反乱を起こして権力を簒奪(さんだつ)した燕王・朱棣(しゅてい・永楽帝)に最後まで従わず、刀で口を裂かれ、獄門死している。
今の日本でも、国策逮捕と隠密殺人、それをごまかす偽報道は健在だと思っている。しかし、ほとんどの国会議員は死への恐れより、出世や欲得で本心に背く法案成立に従事しているように映る。議場の押しボタンロボットと化して。
天皇の「お言葉」を契機に皇室と政治の関係が再び問われている中、同書の出版に宿命を感じる。題名にある通り、GHQは崎門学やそれに続く水戸学の書籍流通を封じた。米国言いなりの政権が終わるかどうかは、捨て身の志士たちの生きざまを国民がどう捉えるかにかかっている。
「国体思想」カテゴリーアーカイブ
『GHQが恐れた崎門学』書評2(平成28年10月6日)
中田耕斎氏が拙著『GHQが恐れた崎門学』のアマゾン・レビュー(平成28年10月6日)を書いてくれた。
「親から子に、師匠から弟子に脈々と國體思想の大義は継承、発展され、ついに明治維新に至った。
本書はこれを証明するために維新志士を鼓舞した5冊の本を取り上げ、その本の内容ばかりではなく、周辺の情報を織り交ぜながら、大義の継承の歴史を描いている。
補論として書かれた原田伊織批判、大宅壮一批判も秀逸で、大義からではなく権力闘争と利害関係からしか歴史を見れない不毛さを論じている。」
『GHQが恐れた崎門学』書評1(平成28年9月29日)
宮崎正弘先生にメルマガ「宮崎正弘の国際ニュース・早読み」(平成28年9月29日)で、拙著『GHQが恐れた崎門学』の紹介をしていただいた。
いまの皇室典範論争はまったくの不毛
山崎闇斎から開始された崎門学が現代日本に蘇る
♪
坪内隆彦『GHQが恐れた崎門学』(展転社)
@@@@@@@@@@@@@@@@@
 いま、こういう正統な著作が世に問われるということが時代の変化。世論の激変を象徴していると言える。
いま、こういう正統な著作が世に問われるということが時代の変化。世論の激変を象徴していると言える。
想えばGHQが発禁図書として日本精神を鼓舞し、皇室伝統を尊ぶあらゆる思想書を日本人の目に触れさせないようにした。およそ七千余もの名著が日本の書庫から、書店から消えた。
完全に消滅してしまったと想われていた正気の書物は、時を経て、ちゃんと復活するものなのだ。
とりわけ忘却の彼方にあったのは水戸学の源流とも言える「崎門学」派の人々。錚々たる学者、知識人、維新行動家の列伝ともなって、本書は思想書でありながら、一般啓蒙書でもある。本書を丹念に読めば、いま論じられている皇室典範議論など不毛の論争、基本を抑えない浅学なひとたちが侃々諤々したところで、結論もまた不毛であろう。そもそも国会議員風情が皇室典範を云々するとは歴史の錯誤である。
さて本書で坪内氏は、明治維新を導いた国体思想の系列を現代風に追求しつつ、国体の本義に迫る。中心に置かれるのは次の五冊である。
浅見絅斎『靖献遺言』
栗山潜鋒『保建大記』
山県大弐『柳子新論』
蒲生君平『山陵志』
頼 山陽『日本外史』
一般的に維新回天の思想的原点として扱われてきた藤田東湖、会沢正志斉らは、崎門学の中継を担った学者としての位置づけがなされ、源流は山崎闇斎、その系統から輩出した山鹿素行、そして国学としての本居宣長、平田篤胤、賀茂真淵らと流れるわけだから、ちょっと出だしの毛色が違う。
山崎闇斎の崎門学の源流は北畠親房にまで遡及する。
七生報国、君は君たらずとも臣は臣足らざるべからずという忠君思想は北畠親房がはじめて体系化した。北畠は茨城に引きこもって著作に専念した。神皇正統記である。
数百年の歳月を経て、水戸学へ流れ込んだ。
浅見絅斎が著した『靖献遺言』は貞亭四年(1687)に書かれ、後に『勤王の志士の聖典』と呼ばれる書物、義烈英雄らの列伝を中国の英傑にもとめて徳川政府を暗喩し、その影響を受けたひとりが梅田雲濱だった。
雲濱は小浜藩士だったが、国防強化を説いて藩主の怒りに触れ、版籍を剥奪された巣浪人。柳川星厳、頼三樹三郎らと交わり天下国家のために奔走し始める。やがて安政の大獄で捕縛され、獄死した。
西郷隆盛は雲濱の獄死に際して、
「いまに生きながらえていたら、我々は執鞭の徒に過ぎない」と慨嘆した。
栗山潜鋒という学者は水戸光圀『大日本史』の編纂に関わった。今日まであまり名前が知られなかった。
栗山潜鋒の著作『保建大記』とは後西天皇の御子、尚人親王のご学友となった栗山が、後白河天皇の践祚から崩御までの38年間に皇室の衰微と武家の萌葱をもたらした戦国動乱の原因を遡及し考察したものだった。
長らく埋もれていたが、竹内式部が見いだし、浅見の『靖献遺言』とともに講義テキストに使って、志士の間に知られるようになったという。
ともかく維新前夜、草莽の志士らは、何を読んで何処に刺戟を受けて、国体明示のために立ち上がったのか。いのちをかけるほどの価値が、なぜそこにあるのかを、思想書を基軸に多くの志士の逸話をあつめて体系化した労作である。
頼山陽・三樹三郎墓参

 平成26年12月23日、頼山陽・三樹三郎墓参のため、円山公園(京都市東山区)の奥にある「長楽寺」を訪れた。ここには、鵜飼吉左衛門・幸吉ら水戸烈士の墓もある。
平成26年12月23日、頼山陽・三樹三郎墓参のため、円山公園(京都市東山区)の奥にある「長楽寺」を訪れた。ここには、鵜飼吉左衛門・幸吉ら水戸烈士の墓もある。
『日本外史』「楠氏論賛」の一節を読み返した。
〈楠氏あらずんば、三器ありと雖も、将た安くに託して、以て四方の望を繋がんや。笠置の夢兆、ここにおいて益々験あり。而るに南風競はず(南朝の気勢があがらない)。倶に傷き共に亡び、終古以てその労を恤むなし。悲しいかな。抑々正閏は殊なりと雖も、卒に一に帰し、能く鴻号を無窮に煕む。公をして知るあらしめば、亦た以て瞑すべし。而してその大節は巍然(高大なさま)として山河と並び存し、以て世道人心を万古の下に維持するに足る。これを姦雄(北条・足利)迭に起り、僅に数百年に伝ふる者に比すれば、その得失果して如何ぞや〉
下御霊神社御札─山崎闇斎の垂加霊社
「現行憲法は改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみ」─平泉澄先生「國體と憲法」②
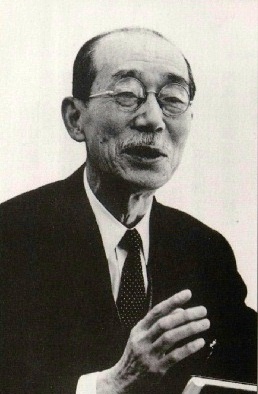 平泉澄先生は、昭和29年6月30日の講演で次のように述べている。
平泉澄先生は、昭和29年6月30日の講演で次のように述べている。
〈日本国を今日の混迷より救ふもの、それは何よりも先に日本の國體を明確にすることが必要であります。而して日本の國體を明確にしますためには、第一にマッカーサー憲法の破棄であります。第二には明治天皇の欽定憲法の復活であります。このことが行はれて、日本がアメリカの従属より独立し、天皇の威厳をとり戻し、天皇陛下の万歳を唱へつつ、祖国永遠の生命の中に喜んで自己一身の生命を捧げるときに、始めて日本は再び世界の大国として立ち、他国の尊敬をかち得るのであります。
憲法の改正はこれを考慮してよいと思ひます。然しながら改正といひますのは、欽定憲法に立ち戻って後の問題でありまして、マッカーサー憲法に関する限り、歴史の上よりこれを見ますならば、日本の國體の上よりこれを見るならば、改正の価値なし、ただ破棄の一途あるのみであります〉
明治憲法は天皇主権?─里見岸雄博士『天皇法の研究』
明治憲法は天皇主権を規定していたと考えるべきか。里見岸雄博士は『天皇法の研究』において、次のように書いている。
〈帝国憲法は現代一般に天皇主権であったと解されているようである。殊に驚くのは曽て大正、昭和前期に於て、天皇機関説を支持した多くの学者が、掌をひるがへすが如くにして、旧憲法は天皇主権であったと言ふ一事である。しかしこれは時流に媚び、若しくは時流に便乗して矛を逆しまにしたものであって帝国憲法第四条の法理を無視すること甚しきものといはねばならぬ。第四条は厳として、「天皇ハ国ノ元首」と明言する。これは、天皇は国の元首であるが国そのものではないといふ意味で天皇即国家の否定である。又従って、当然の法理として、天皇は主権者でない。主権の所有者でないといふことである。「統治権ヲ総攬」の「統治権」は、「国ノ統治権」の意味である事明々白々である。帝国憲法の用語としての「統治権」は私の詳説した通り決して妥当なものではないが、論理的には明快であって何等紛更を許す余地がない。ここに言ふ「統治権」は「国権」或は「主権」の意味であり、その帰属は天皇に非ずして国であることは理在絶言である。「統治権」は国に属し、「総攬」は天皇に属する。統治権は統治権、総攬は総攬で別箇の概念と見るべきである。「国ノ統治権ヲ天皇ガ総攬」されるのである。なぜ総攬されるかと言えば、「国ノ統治権」は近代憲法の主義に則り、三権分立されてゐるからである。分立しただけでは対立である。国家意思としては、それが統合されてゐなければならぬ。かかる意思の統合は自然人によって表現されざるを得ない。自然人たる天皇に於てのみかかる表現は可能なのであって、それを此の憲法の条規によって行ふといふのが帝国憲法である。少しも天皇主権の法理は存在しない〉
天皇政治の中に生きている民主主義(谷口雅春「生命体としての日本国家」)
 谷口雅春は「生命体としての日本国家」(『理想世界』昭和四十四年一月号)において、次のように書いている。
谷口雅春は「生命体としての日本国家」(『理想世界』昭和四十四年一月号)において、次のように書いている。
〈君民の利益が一致しているのが、天皇政治下の民主主義なのである。
そこで思い出されるのは、仁徳天皇が当時の日本国民が貧しくなっているのをみそなわせられて、三年間租税を免除し、皇居が朽ちて所々がぼろぼろになって雨漏りしても、それを補修し給うことさえ遠慮され、三年目に高殿に登り給うて眼下に街を見渡されると、国民の経済状態は復興して、炊煙濠々とたち騰って殷富の有様を示しているので、皇后さまを顧みて、「朕は富めり」と仰せられた。そして。
高き屋にのぼりて見れば煙たつ 民の竈は賑ひにけり
というお歌をお詠みになったというのである。天皇は、自己が貧しくとも、国民が裕かであれば、「朕は富めり」であらせられる。これが天皇政治の中に生きている民主主義なのである。これを民主政治下の代議士が、汚職をもって自分を富ませながら、そして自己の貰う歳費の値上げを全員一致で議決しながら、国民のたべる米の価格や、国民の足である交通料金その他の公共料金の値上げに賛成するのと比較してみるならば、いわゆる現代の民主政治は一種の特権階級政治であり、天皇政治こそかえって民主政治であることがわかるのである〉
『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)発行
 崎門学研究会の『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)が発行された。
崎門学研究会の『崎門学報』第7号(平成28年4月30日)が発行された。
今回も「靖献遺言を読む:文天祥」、「時論:核武装論」、「靖献遺言輪読会を終えて」など読み応えのある論稿が載っている。
『神皇正統記』は北条泰時を称賛しているのか?─親房論述の本意
 北畠親房は『神皇正統記』において、北条泰時について次のように書いている。
北畠親房は『神皇正統記』において、北条泰時について次のように書いている。
〈大方泰時、心正しく政すなほにして、人を育み、物に憍(おご)らず、公家の御事を思ひ、専ら本所の煩(わずらひ)をとどめしかば、風の前に塵なくして、天下即ち静まりき。かくて年を重ねし事、偏(ひとへ)に泰時が力とぞ申侍るめる。陪臣として久しく権を取る事は、和漢両朝に先例なし。其主たりし頼朝すら二世をば過ぎず。義時いかなる果報にか、計らざる家業を始めて兵馬の権をとれりし、様(ためし)希なる事にや。されども才徳は聞えず、又大名(たいめい)の下に誇る心やありけん、中二年計りぞありし、身まかりしかども、彼の泰時相継ぎて、徳政を先とし、法式を固くす。己が分を計るのみならず、親族ならびにあらゆる武士までも誡めて、高き官位を望む者なかりき。其政次第のままに衰へ終に亡びぬるは、天命の了(をは)る姿なり。七代までたもてるこそ彼が余薫(よくん)なれば、恨む所なしと云ひつべし。およそ保元平治よりこのかたの乱りがはしきに、頼朝と云ふ人もなく、泰時と云ふ者なからましかば、日本国の人民いかが成りなまし。此謂(いはれ)を能く知らぬ人は、故もなく王威の衰へ、武備の勝ちにけると思へるは、誤なり〉
果たしてこれは、親房が泰時を評価したと理解していいのだろうか。平泉澄先生は、『明治の源流』において、次のように述べている。
〈表面から之を読めば、いかにも泰時の人物徳操をほめたたへるやうに見えるであらう。然し正統記は、後醍醐天皇崩御の後、国難重畳の際に、わづか十二歳にして大統をつがせ給うた後村上天皇に、政治の御参考となり、君徳の御教養にお役立て申上げようとして、常陸の小田城に於いて著述して吉野へ御届け申上げた書物である。従ってそれは、一面最もすぐれたる歴史の名著であると共に、他面に於いては朝政訓誡の軌範であって、之を真に理解する為には、文字を表面に於いてのみ読まず、往々裏返しにして吟味する必要がある。
即ち正統記が頼朝や泰時をほめてゐるのは、朝廷に重大なる反省を要求してゐるのである。頼朝が幕府を開いた事を非難する前に、朝廷が武術を怠り、禍乱を鎮定する実力を失った事を歎かねばならぬ。泰時が勝利を得て政権を握った事を恨む前に、君徳四海をおほふ能はず、賊軍に加担する者の多かった事を反省しなければならぬ。是れが親房論述の本意である。それは良い訓誡ではあるが、直接泰時の行動に対する批判では無い〉
