平成三十年は「明治百五十年」といふことで、各地で様々な催しや出版物が企画される模様だ。その中で、山崎闇斎の学派が王政復古に果たした役割については充分な見直しがされたとはいへない。
管見の限り、明治維新の再検討については、昭和初期に「講座派対労農派」の日本資本主義の解釈をめぐる論争のほか、戦時下における幕末維新史の再評価、そして今から半世紀前の「明治百年」の際の出版企画など、これまでも数十年置きに繰り返されてきたと見られる。しかし時を経るにつれ、明治そのものが本当に遙かに遠くなるにつれ、一部の識者の働きかけに反し、国民一般への浸透については低迷の感が否めない。
改めていふまでもなく、明治期の歴史や思想を扱つた書物は、現在刊行されてゐるものだけでも汗牛充棟の勢ひで、その書誌を整理するだけでも容易なものではない。その中で、これまでの筆者の貧しい読書体験から、国学や水戸学、そして闇斎学派について言及があるものをいくつか紹介していきたい。
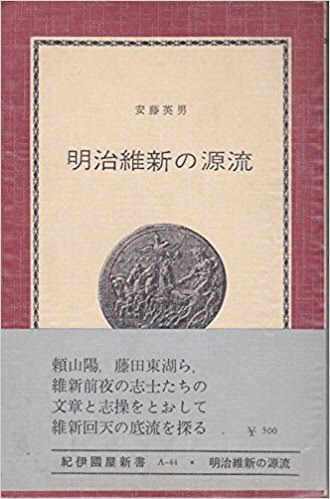
『明治維新の源流』は「明治百年」と呼ばれた翌年の昭和四十四年、紀伊國屋新書の一冊として刊行された。紀伊國屋新書は、当時同店出版部で嘱託をしてゐた評論家の村上一郎の企画によるもので、桶谷秀昭の初期評論『ジェイムス・ジョイス』や橋川文三の『ナ
ショナリズム』、宮川透の『日本精神史への序論』もこのシリーズから刊行されてゐる。
昭和五十六年に復刊された新装版の序文によると、当初は「漢詩鑑賞」といつたテーマで依頼されたさうだが、唯物史観全盛期だつた当時、「思想の力を軽視してはならない」といふ著者の意志により、人物の力を重視した記伝の体による近世日本史を上梓する運びになつたといふ。その辺り、昭和三十年代に龜井勝一郎が提起した「昭和史論争」との接点も感じられるが、当時の歴史学界で、人物の活躍よりも、如何に抽象的な「発展的法則」に比重が置かれてゐたかが窺へる。
著者の安藤英男は昭和二年生まれ。法政大学の経済学部卒業後、銀行に勤めながら、蒲生君平や頼山陽、雲井竜雄、河井継之助といつた江戸後期から幕末にかけての人物伝を著し、学位を取得。後に国士舘大学教授になる。平成四年に六十半ばで亡くなり、その存在は忘れ去られつつあるが、今でも寛政の三奇人や幕末志士の評伝などで、その著書が参考文献として掲げられることは少なくない。
はしがきにもある様に、とりわけ「維新変革の基本的精神が、国体論・名分論によって培われ、激成されたものであること」に、中国やフランスの〝革命〟や、室町幕府成立後の体制変換と大きく異なる所以が強調されてゐる。
中でも序説では、「国体論・名分論の勃興」とし、幕藩体制の秩序を維持した学問として、儒学(とりわけ朱子学)の果した役割に力点が置かれる。儒学の基本的な性格として著者が掲げてゐるのは、「人に内在する道徳性を引出して磨き上げ、これを、現実の社会生活の上に適用し、達成してゆこうとするもの」である。一般に「維新」といへば「倒幕」の運動と不可分であると考へられるが、本書では、既に幕藩体制分維持した儒学の中に、維新変革を導いた名分論の嚆矢を見出してゐるのである。
例へば林羅山とともに、朱子学に「官学」の地歩を与へた人物として、著者が注目してゐるのが、徳川家光の庶弟で、四代将軍・家綱の輔相となつた保科正之である。正之が吉川惟足から神道を学び、山崎闇斎を会津藩に招いて「家訓十五箇条」を起草したことは広く知られてゐるが、「日本書紀(やまとふみ) かへすがへすも くり返し 万代までも 絶えぬ道かな」といつた尊王の詠歌をものしてゐることを知る人は少ない。これも朱子学による大義名分論が不可分である。
それとともに、孔子の春秋左史伝に範を採り、史実に基づいて大義を証明しようとしたのが、水戸学の開祖・徳川光圀である。水戸学の根幹として、「日本の国体が、宝祚無窮・万世一系」であることから、必然「皇朝の正統論―尊王論」に向ふことに着目。「尊王から斥覇への、一里塚」といふ評価を下してゐる。
続いて「国学の系譜」として、光圀の知遇に応へて『万葉代匠記』を著した契沖、赤穂義士の討ち入りも賛助した国学の開拓者・荷田春満、「万葉集の研究を主軸に、国学の開発に一大紀元を劃出した」賀茂真淵、「古事記伝」を著し、「皇室の尊厳を天下に称揚した」本居宣長らの足跡が振り返られる。
ここで注目すべきなのは、宣長が「伊勢に来った竹内式部との交際を拒み、また、自己の撰した甲斐の酒折宮碑を、山県大弐の碑文と並べて建てることを拒んだほどの穏健派」であつた一方、晩年の蒲生君平とは、肝胆相照してゐた事実である。その点、「すこぶる微温の感も免れない」ものの、『玉くしげ』上梓当時は、松平定信が「賢宰相」として善政を布いてゐた時分にあたり、「宣長の朝幕両立の見も、当時に於ては至当」であったことを、著者は擁護してゐる。
同様に宣長の「歿後の門人」を自認した平田篤胤にも、「幕府に対する反抗の思想はなかった」。しかし天保七年に、唐国の王朝よりも本邦が秀でた所以を説いた『大扶桑国考』を著すと、さすがに林家の忌避に触れたといふ。
この点について著者は、「国典の研究が、かならず勤王思想に帰着するわけでもなければ、討幕運動につながるわけでも」ないことを認めてゐる。しかしながら、「時代がすすみ、幕府の諸制度に矛盾が生じ、社会秩序が動揺を来すようになると、併行して、いよいよ国学は本質を露呈し、国粋思想・排外思想を育み、斥覇・討幕の思想と渾然融合するにいたるのである」と総括してゐる。
続いて「山崎学の波紋」として採り上げられてゐるのが、宝暦・明和事件についてである。(本書では「崎門学」ではなく「山崎学」としてゐる。)
水戸学と山崎学の共通点について、著者は「いずれも朱子学と国学の化合」と捉へる。「大義名分の論、尊王斥覇の説、いずれも朱子学の眼目であったが、これに人々が目覚め、さらに国学の慕古思想・復古思想などが加味されるとき、いきおい、革新の傾向を喚き、爆発性を帯びる」といふ一節には、本来幕藩体制を支へた朱子学が、これまでの秩序に飽き足らぬ、新たな思想を生み出していく過程が、見事に集約されてゐる。
闇斎の朱子学について、ここでは、「朱子を尊敬しながらも、一般の儒者のように、決して唐土を精神的母国として崇拝せず、日本の儒者である誇りを自覚する点」に、その独自性を見出してゐる。そこから「日本こそ万国の中華たる中国である」といつた『文会筆録』の矜恃が生まれ、さらに「徳川将軍と雖も、まがうかたなき天皇の臣である」といふ闇斎学派の国体論が確立されていく。
とりわけ「尊王義烈の精神の結晶」といはれる浅見絅斎の名著『靖献遺言』は、その後約二百年間にわたり、式部・大弐に留まらず、藤森弘庵、春日潜庵を経て、吉田松陰・橋本左内、梅田雲浜らによつて「バイブル」として受け継がれていく経緯が説かれ、目を瞠るものがある。
その他「天明・寛政の時代精神」の中で、「朱子学の泰斗」として本書で採り上げられてゐるのは、柴野栗山・尾藤二洲・菱川秦嶺の他、意外にも松平定信である。定信は天明八年、老中首座として上京、参内の折、礼節を尽くして王室を貴んだことから評判を喚んだ。皇居罹災の折には、新に新内裏として仙洞御所を造営。そのことで光格天皇、後桜町天皇から御製を賜つた将軍・家斉は、感激のあまり手づから宸翰を模写し、定信に銘刀を添へて伝賜するほどだつたといふ。
第一章の「寛政の三奇人」では、林子平・高山彦九郎・蒲生君平の三奇人について、「尊皇思想と国防思想との抱合」を生んだ〝先駆者〟として位置づける。
第二章「頼山陽」では、『日本外史』を貫く基幹精神として、「朱子学の大義名分論、尊王論の日本版」と説く。山陽の史論に「兵馬の大権」が本来天皇にあること、またその詠史には「天皇親政」の理想が盛り込まれてゐることから、「幕府政治を維持する支柱として奨励された朱子学を、かえって現状否定の理論に盛り上げた」点に着目。その理論が「維新回天の倫理につながるものであった」ことを主張してゐる。

第三章では、藤田東湖が採り上げられ、「水戸藩が天下の人材を鼓動した尊皇攘夷のスローガン」が、東湖に胚胎し、その大看板が、「一転して討幕の一大用具に利用され、回天の事業が、同朋あい鬩ぐ内戦」を伴つたことを直視する。
終章の第四章は、吉田松陰で締めくくられる。父・杉百合之助の尊王の志に始まり、長州に早くから「尊王・護国の濃厚な感情」があり、村田清風がその趨勢を助長したこと。そして軍学師範の家元に育つた松陰が、さうした藩風を受け継いだことについて筆が割かれる。
とりわけ東北・北越の遊歴中、水戸に立ち寄り、会沢正志斎をはじめとする水戸学者たちと邂逅できたことが、松陰に大きな感化をもたらせてゐる。
プチャーチン、ペルリの来航を耳にするや海外雄飛の志を立て、国禁の罪で伝馬町獄から野山獄に移監。しかしかうした果敢な行動は、全国の有為の青年たちの心を動かすに至る。
蟄居の身でありながら松下村塾を経営し、二年半にも満たない歳月に輩出された少数の門下生から、明治維新後、国家有用の人材が生まれた経緯については改めて述べるまでもない。期待を託した長州も京都も意の如くならずと悟つた松陰は、〝草莽崛起〟を提案。獄中で正月を迎へた安政六年には、明確に討幕の思想にまで進展させてゐる。漸く長州が「一藩を挙げて猛然と動いた」のは、松陰が安政の大獄で没して後のことである。
本書で採り上げられた人物は、「維新の源流」を語る上では、ごく限られた存在にすぎない。しかしながら、本来幕藩体制の秩序を固めるために広まつた朱子学の大義名分論が、水戸学、国学、崎門学を経て、やがて尊王心に目覚めた志士たちによつて、維新回天の事業へと発展していく経緯が描かれ、それは歴史の変革のダイナミズムを探る上でも、今日尚色褪せない視座を与へてくれる。
