帝京大学の小山俊樹教授が、『五・一五事件 海軍青年将校たちの「昭和維新」』(中公新書)で、第42回サントリー学芸賞(思想・歴史部門)を見事に受賞された。
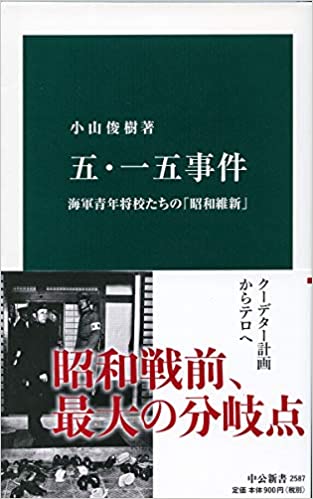
『大亜細亜』は、平成29年に小山教授が上梓された前作『評伝 森恪 日中対立の焦点』(ウェッジ)に関して、インタビューをさせていただいた(インタビュー・構成 小野耕資)。そこで「一九二〇~三〇年代に起きたことは、世代を超えて語り継がれていきます。とくにほとんどが刑死した二・二六事件と異なり、五・一五事件の主要な関係者は、戦中戦後も生きています。彼らにとって戦後とはどういう時代だったか。このことを考えながら、五・一五事件を描ければと思っています」と述べられていたことが印象深い。
以下、『大亜細亜』第6号(平成30年7月)に掲載した小山教授のインタビュー記事「西洋列強との協調と相克の近現代史」全文を紹介します。
帝京大学文学部史学科教授の小山俊樹先生は日本近現代史専攻で、昨年(平成二十九年)、『評伝 森恪 日中対立の焦点』を上梓された。森恪は戦前日本の大陸政策に関与した人物で、小山教授は森とアジア主義者との関わりにも言及している。そこで同書の内容を中心に、戦前のアジア主義運動史について、平成三十年六月六日にインタビューを行った。
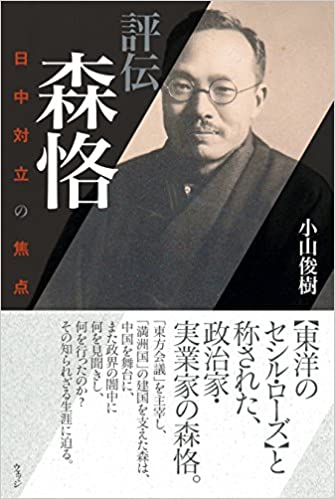
―─ 森恪に興味を持ったきっかけは、どういったものでしたか。
博士論文(『憲政常道と政党政治 戦前二大政党制の構想と挫折』)を執筆した際に、二大政党時代の政党政治研究がまだまだ薄いと感じました。そして論文では、森恪が当時の政界のキーマンとして度々登場するので、いずれは本腰を入れてまとめなければと考えていました。そこに、ウエッジ社編集部から中国関係の人物伝を依頼されたので、それではと挑戦することにした訳です。
一般には森の知名度も高くはなく、編集部にも意外な人選だったようです。森の本格的研究は乏しく、一般には松本清張などの影響で、大陸侵略の陰謀を練った怪しい人物というイメージが先行している状況でしょうか。また、四十九歳という短命で亡くなりますが、その劇的で濃密な生涯に、興味を持ったことも理由の一つです。
―─ 森は三井物産社員の時代に、突然孫文に出資したりしています。なぜ森はいきなりそのような大舞台に登場できたのでしょうか。
ひとつには、森が努力家であったことでしょう。中国語を磨き、アイディアを実践し、頭角を現すだけの行動力がありました。辛亥革命が起きた時、森はニューヨークから古巣の上海に呼び戻されますが、中国関係なら森だとの評価が、すでに三井上層部で定着していたのです。彼は期待に応えて、孫文ら革命派の信頼を得ていきます。
ただ革命派への出資は、後年の伝記で強調されるほど森単独の力で行えたわけではありません。森と孫文との直接交渉は、三井上層部(益田孝、山本条太郎ら)の意向や、支店長・上司先輩の支援があってのことで、森の役割はメッセンジャーであったと言えます。
―─ 三井物産は森の父の紹介で入ったのでしょうか。
そうですね。基本的には山本条太郎の縁故です。山本が大阪の三井物産にいたときに、森の父作太郎が大阪市会議長で、関係ができたようです。
―─ 東方会議では門戸開放の実現を目指しましたが、どういう背景があったのでしょうか。
まず森が東方会議で目指したものですが、仰る通り、この時点での森は、列強と協調して中国に「門戸開放」を迫る立場でした。その意味で、列強との「協調外交」を志向した田中義一首相と通じていました。
ただし、森の考える「協調」は、日本を含めた列国の権益を実力で守る場合に限られていました。当時、中国大陸は北伐の最中で、日英をはじめとする列国の居留民や資本は、大きな打撃を受けていました。そこで中国側からの無法な被害を、日英共同で防ぐという発想が現れます。これに対して、当時の幣原喜重郎外相(第一次若槻礼次郎内閣)は、イギリスとの提携を選ばず、中国に同情的な態度を崩しませんでした。そこで森は山本条太郎・松岡洋右らと中国を視察し、幣原外交打倒による、外交方針の転換を仕掛けるのです。幣原といえば「協調外交」と見られますが、言わばこのとき森は、イギリスとの「協調」のために、幣原「非協調」外交を攻撃したのです。
ただ、時が経つに従ってイギリスは、大陸への不干渉政策を重視するアメリカの立場に近づきます。反対に日本は大陸への積極的派兵によって、国民政府の反発を買い、列強からも警戒されました。その結果、日英協調も壊れてしまう。そこで森は、日本単独で大陸権益の擁護を図ろうと考えて、近い思考をもつ軍部へと接近するのです。
本にも書きましたが、森は列強との均衡を維持し、自由な商業活動を維持できる限り、列強との協調は一定程度必要だと考えていました。中国が不当な要求をしたときは、列強との協調による対抗が有効だからです。ただ森は大陸での経験から、列強に対するライバル視が強く、英米を競争相手、「商売敵」と見ていました。単に言うことを聞く「協調」ではなく、利用価値がなければ組み伏せる対象として、列強を見ていたということです。
アジア主義者は、欧米と協調しないでアジアに還ればいいと言いますが、森のように大陸への介入を主張した人は、二者択一ではなく、両者を結び付けて考えていました。中国からの不法な要求に対応できないのであれば、列強と協調する意味はない。ただそれは同時に両方を敵に回す戦略であり、戦前日本が実際に歩んだ道なので、決して安易な方法論ではありませんでした。
―─ 中国に対して森の評価は低いわけですが、それはなぜですか。
袁世凱をはじめ、当時の中国指導者層はイギリスと提携して日本の排除を進めました。そうした動きへの警戒心もあったはずです。ただ、彼が中国をすべて嫌っていたかというと、そうではありません。人間的な付き合いをすれば、印象が変わる面もあるでしょう。孫文と森は親密な関係を築きましたし、信頼の置けるビジネスパートナーとして認めれば、森は中国人でも密接に交流しました。
しかし森は、中国人の政治・経済・軍事その他の実力を、極めて低く見積もりました。一般論として、大陸に深入りすればするほど中国が嫌いになる、という状況はあるように思いますが、森もやはり滞在中の見聞を通して、そう考えるようになりました。そして、中国は列強が指導して初めてモノになる、日本の支配は中国のためでもある、という心理を固めます。そういう意味で、森の思考は素朴な日中連帯論とは違います。同じくアジアと関わる立場でも、満洲建国を否定した犬養毅等とは同床異夢の関係だったのでしょう。
―─ 五・一五事件には森関与説もありますが、ご著書ではその説を否定されていました。それについて教えていただけますか。
私はこの本を書きながら、政治史と運動史はまだ連関が足りない、と実感しました。政界の史料を眺めると、五・一五事件の森関与説が頻出して、なかには真に受ける研究者も出てきます。ところが国家主義運動の史料を見ると、全然そのようなことはないことがわかります。
森が接点を持っていたのは幕僚級の陸軍将校で、五・一五事件を起こした海軍青年将校とは接点がありません。北一輝とは関係がありましたが、北と関係の深い西田は、同事件で襲撃された側です。事件のとき森は内閣書記官長でしたが、同時に内務省を指揮して、血盟団などを取り締まる側でした。五・一五事件の計画が定まったのは五月に入ってからで、蹶起の当事者でさえも最終的な計画の段取りや日時は、直前まで分かりませんでした。森が事前に知るはずがありません。森が関与したとの噂は、殺された犬養側の親族、森を嫌った芳澤謙吉などが方々に流しました。よくある政治上の駆け引きとも言えます。
―─ 猶存社系の人たちとの関係はどうだったのでしょうか。
北一輝と三井財閥(池田成彬ら)との間をつないだのが、森であることは間違いありません。ただ大川周明との接点は出てきませんし、やはり血盟団や五・一五事件関係の人とは距離があったと思います。
─― 白鳥敏夫との関係はどうだったのでしょうか。
白鳥は、相当強い影響を森から受けています。満洲事変前後に西園寺が白鳥と会った後、親英米派であった白鳥の考えが一変していて、どうしたんだと感想を残しています。これは明らかに森の影響でした。白鳥は後年、重光葵や吉田茂などとは仲が悪くなりますが、下僚には顔がきき、広く影響を及ぼしています。詳細な研究が望まれる人物だと思います。
―─ いわゆる在野のアジア主義者との接点はあったのでしょうか。
あったことは間違いありません。たとえば宮崎滔天の没後、子の竜介に森が学費援助を申し出たが、その母が断った。森は後に竜介に「お前のおふくろは親爺よりえらいよ」と言ったエピソードもあります。頭山満や犬養毅とも、辛亥革命以来の交友があります。
―─ 森は最晩年には、アジアモンロー主義を唱えて、西洋の物質文明とたもとを分かち伝統的日本精神に立ち返れと述べるなど、思想的に深くなっていたように見えます。その変化はどういうものがあったのでしょうか。
満州事変以降の協調外交の破綻は、森にとっても痛恨であったと思います。ただ、そこで森はもはや日本独力でやるよりなく、それならば満洲建国を認めて、アメリカと戦争をするくらいでないと乗り切れないという考えを固めていきました。ただし戦争に突き進むというより、戦いの備えをした上で権利を認めさせよ、というのが森の主張でした。
最晩年の議会演説は、白鳥敏夫や鈴木貞一との合作でしたが、劇的な変化で、やはり思想的に深まったのだと思います。当時公人で「アジアに還れ」とまで言う人はいませんでした。協調外交の失敗、列強に対するライバル視、さらに中国観などが重なって、白鳥や鈴木ら外交官や軍人などと語らう間に、考えが固まっていったと私は見ています。
―─ 小山先生は昭和維新運動に参画した人の戦後の動きに関心を持たれておりますが、それはどのような関心によるものですか。
一九二〇~三〇年代に起きたことは、世代を超えて語り継がれていきます。とくにほとんどが刑死した二・二六事件と異なり、五・一五事件の主要な関係者は、戦中戦後も生きています。彼らにとって戦後とはどういう時代だったか。このことを考えながら、五・一五事件を描ければと思っています。 (インタビュー・構成 小野耕資)