
日清両国の君主の握手
「抑も康有為の光緒皇帝を輔弼して変法自強の大策を建つるや我日本の志士にして之れに満腔の同情を傾け此事業の成就を祈るもの少なからず、此等大策士の間には当時日本の明治天皇陛下九州御巡幸中なりしを幸ひ一方気脈を康有為に通じ光緒皇帝を促し遠く海を航して日本に行幸を請ひ奉り茲に日清両国の君主九州薩南の一角に於て固く其手を握り共に心を以て相許す所あらせ給はんには東亜大局の平和期して待つべきのみてふ計画あり、此議大に熟しつつありき、此大計画には清国には康有為始め其一味の人々日本にては時の伯爵大隈重信及び子爵品川弥二郎を始め義に勇める無名の志士之に参加するもの亦少からざりしなり、惜むべし乾坤一擲の快挙一朝にして画餅となる真に千載の恨事なり」
これは、明治三一(一八九八)年前後に盛り上がった日清連携論について、大隈重信の対中政策顧問の立場にあった青柳篤恒が、『極東外交史概観』において回想した一文である。永井算巳氏は、この青柳の回想から、日清志士の尋常ならざる交渉経緯が推測されると評価している。両国の志士たちは、日本は天皇を中心として、中国は皇帝を中心として、ともに君民同治の理想を求め、ともに手を携えて列強の東亜進出に対抗するというビジョンを描いていたのではあるまいか。
変法自強運動を主導した康有為は、一八五八年三月に広東省南海県で生まれた。幼くして、数百首の唐詩を暗誦するほど記憶力が良かったという。六歳にして、『大学』、『中庸』、『論語』、『朱注孝経』などを教えられた。一八七六年、一九歳のとき、郷里の大儒・朱九江(次琦)の礼山草堂に入門している。漢学派(実証主義的な考証学)の非政治性・非実践性に不満を感じていた朱九江は、孔子の真の姿に立ち返るべきだと唱えていた1。後に、康有為はこの朱九江の立場について、「漢宋の門戸を掃去して宗を孔子に記す」、「漢を舎て宋を釈て、孔子に源本し」と評している。 続きを読む 康有為─もう一つの日中提携論
「東亜同文書院」カテゴリーアーカイブ
西本省三と忠臣・鄭孝胥
 戦前の興亜論を再考する上で、孫文支持派と一線を画した清朝復辟論者の存在に注目する必要がある。その中心人物の一人が西本省三である。
戦前の興亜論を再考する上で、孫文支持派と一線を画した清朝復辟論者の存在に注目する必要がある。その中心人物の一人が西本省三である。
明治10(1877)年に熊本県菊池郡瀬田村で生まれた西本は、中学済々黌(現在の熊本県立済々黌高等学校)卒業後、東亜同文書院で教鞭をとった。
西本は、清朝遺臣の鄭孝胥と交流するとともに、同じく清朝遺臣の沈子培に師事し、清朝復辟論を唱えていた。辛亥革命後の大正2(1913)年には、鄭孝胥、宗方小太郎、島田数雄、佐原篤助らと上海に春申社を設立し、『上海』を創刊する。西本は同紙上で、清朝復辟を唱え、孫文の思想を「欧米直訳思想」と批判していた。昭和2(1927)年夏に西本は病のために郷里熊本に帰国、再び上海の地を踏むことなく翌28年5月に死去した。
一方、鄭孝胥は溥儀の忠臣として人生を全うした。1912年に溥儀は退位宣言をし、1924年には紫禁城を退去したが、鄭孝胥は忠臣として付き従った。鄭孝胥は1932年、満州国建国に伴い、初代国務院総理に就任した。
*写真は鄭孝胥
「日支提携の先鋒たらしめん」馬場鍬太郎(東亜同文書院第18期旅行記念誌序文、大正10年5月)
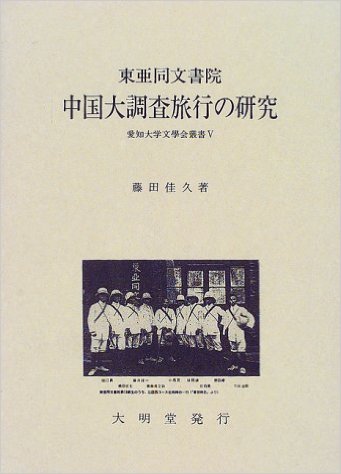 東亜同文書院生の卒業旅行とはいかなるものであったのか。彼らに期待されていたものは何だったのか。藤田佳久『東亜同文書院 中国大調査旅行の研究』(大明堂、2000年4月)には、書院教授・馬場鍬太郎が第18期旅行記念誌(大正10年5月)に寄せた序文が引かれている。
東亜同文書院生の卒業旅行とはいかなるものであったのか。彼らに期待されていたものは何だったのか。藤田佳久『東亜同文書院 中国大調査旅行の研究』(大明堂、2000年4月)には、書院教授・馬場鍬太郎が第18期旅行記念誌(大正10年5月)に寄せた序文が引かれている。
〈凡そ生を人生に享くる者其時と所を問はず人類文化発展の大業に参し、身に応じ、分に従ひて努力するの覚悟あるを要す。吾人が支那大陸の開発経営に資するに当たりても亦文明の潮流時勢の要求に順ひ、物質的及精神的両文化の円満なる発達を期待せざるべからず。然るに我が邦人の真に支那を解するもの極めて少なく、支那と言へば直ちに荒寥たる僻陬を連想し、或は一獲遺利を拾ふに適すと思意する者比々皆然り、之れ固より、不究者自身の罪たりと雖も一は亦我邦に於ける調査研究基幹の寂寞たりしに帰せずんばあらず。
惟ふに支那に関する邦人の研究は日支両国の関係上頗る古くより行はれ、殊に近時に至りて著しき高潮を呈し学者、政治家、実業家等職業階級を通じ相競ひて之が研究に遅れざらん事を勉むるに至れり、然れども其範囲未だ漢籍の外に出です、或は西人著書の抄訳により、その糟糠を甜むるに止まる。
千言満語口に日支親善を唱へ、唇歯輔車、日支共存を論ずるも其実の挙がらざる寧ろ当然なるべく、今や更に具体的日支親善案の論議を見るに至れり。
然るに支那研究の道程如何、固より一言にして尽し得ずと雖も親しく風俗、習慣、物情、民意の機微を究め人心の趨帰を察し支那は謎題なりとして不究の罪を糊塗せんとする従来の弊習を打破するにありて其第一着手としては須らく先ず地理の研究に起り、親しく其地の視察調査に志を要す。
松陰先生の所謂「地を離れて人なく、人を離れて事なし、人事を論ぜんと欲せば先ず地理を審かにせざるべからず」所以爰に存す、我が東亜同文書院夙に見る所あり、毎夏上級学生を十数班に分ちて禹城の南北を周游せしめ、親しく地理、人情、習俗の機微を究めて日支提携の先鋒たらしめんとし、よく支那事情研究の資料を蒐集して剰す所なし。
昨夏第十八期生を分つこと二十、三伏の溽熱を冒し、足跡本部十八省に遍ねく更に内蒙、東三省に及ぶ、昿漠険阻の地を過ぎ、艱苦欠乏の厄に耐へ、長途或は魂を驢騾の孤鞍に驚かし夜半夢を木舟の中に破り、旅宿孤燈の下に視察を随記し帰来編して紀行成る。
予書院に職を奉じ旅行計画の任にあること年あり毎夏各地を巡游するに当り親しく各班辛苦の実況を目撃し私かに感激の意に不堪、聊か感想を舒べて序に代ふ〉