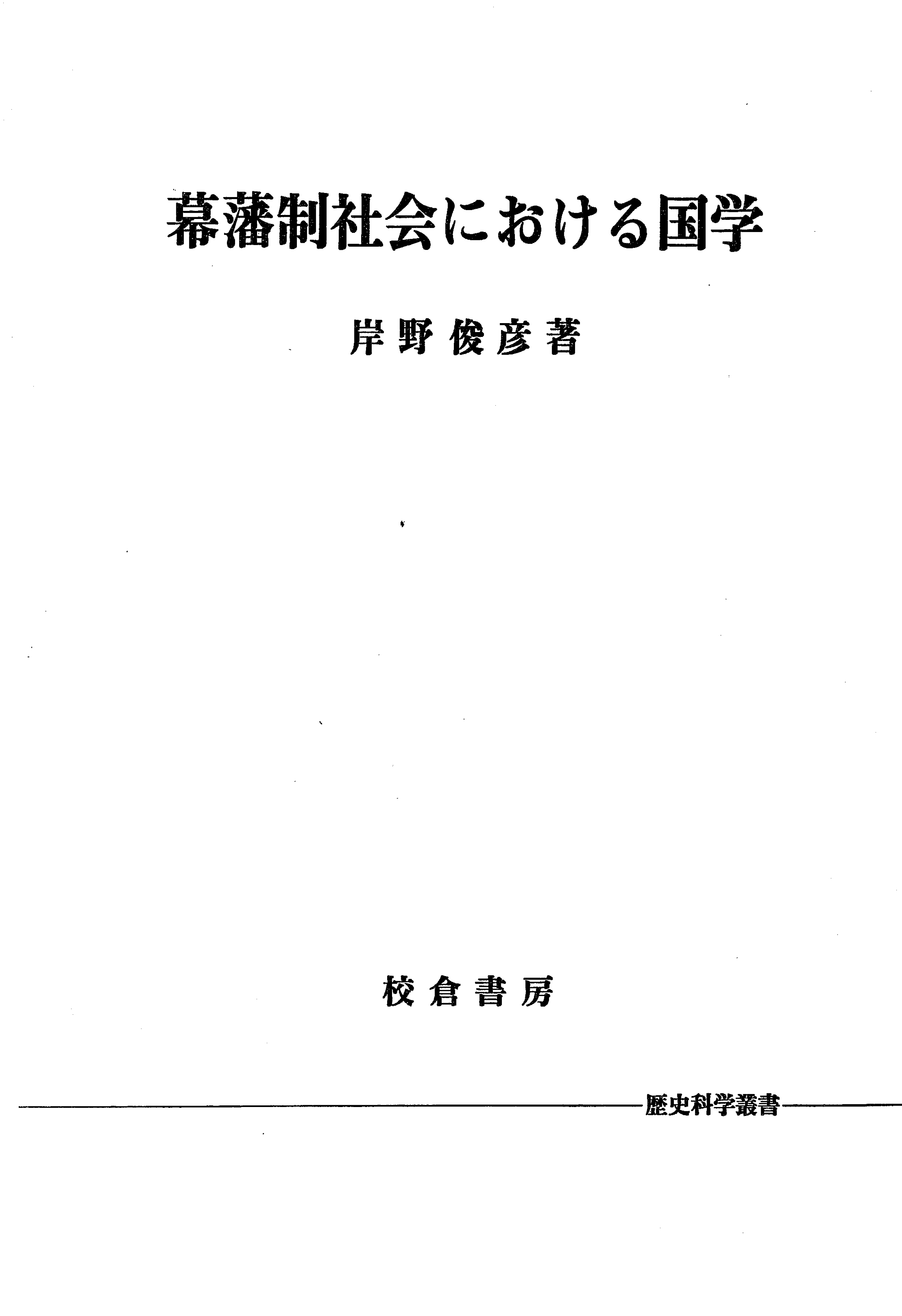
岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において、尾張藩の国学者たちは、「近世国学の開基は尾張初代藩主の徳川義直だ」と主張したと指摘している。
近世の国学の系譜は、通常、契沖・荷田春満・加茂真淵・本居宣長・平田篤胤を基軸として理解されている。
ところが、尾張藩の国学者たちは、義直が『類聚日本紀』『神祇宝典』などの撰述を行っていることを根拠として、近世国学の開基は義直だと主張したというのだ。
尾張藩では、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという問題関心が強まった。その理由は何か。岸野氏は、以下のように説明している。
〈義直自身についていえば、家康の子として尾張藩主となったが、尾張藩の成立の事情からいえば、家臣団の出自の雑多性と複合性や、支配領域が尾張国を超えた複合的性格を持っていること等の中での、尾張藩と尾張徳川家の統合の論理とイデオロギーが不可欠であったという事情があった。徳川家康の子としての、徳川系譜と事跡の確認は最も重要な問題であった。戦国期に遡れば、多様な戦国大名の家臣であった者を家臣団に組み込むためには、徳川系譜が清和源氏に繋がることもまた重要な問題であった。清和源氏と繋がれば、古代天皇の事跡の研究はい儒学的政治論の「王道」「治者道」を極めることと同列になる。儒学神道の方法がこれを結びつけたといえる。こうして、藩祖としての統合の原理を求めて著されたものであるだけに、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという、問題関心が惹起するのは当然であったといえる〉(十九、二十頁)
ただし、天明・寛政改革期には、尾張藩における国学派の地位はそれほど高くはなかった。この時期、義直著書の校合が主導したのも、儒者や垂加派だった。校合の担当者は、『初学文宗』『軍書合鑑』が細井平州、『神祇宝典』が河村秀根、『類聚日本紀』が稲葉通邦、『成功記』が岡田新川、『中臣獣抄』が吉見幸孝であった。
ところが、尾張藩における国学派の地位は上昇していった。その契機こそ、やがて十四代藩主に就く徳川慶勝とのむすびつきであった。岸野氏は、「尾張藩に仕えた国学者たちは、幕末維新期の尾張藩主徳川慶勝と結ぶことによって、藩祖尾張義直の国学的再評価を行い、藩政改革と国政変革に参加しようとしていた」と述べる(十二頁)。
「契沖」カテゴリーアーカイブ
尾張藩国学の先駆・田中道麿①─『養老町が生んだ国学者』

●一旦、歌の道を断念
田中道麿翁顕彰会・養老町教育委員会編・山口一易執筆『養老町が生んだ国学者 田中道麿さん』に基づいて、田中道麿の生涯を追う。まず、生い立ちから、桜天神で国学塾を開くまでの歩みについて整理しておく。
道麿は享保九(一七二四)年、美濃国多芸郡榛木(はりのき)村の農家で生まれた。道麿は、学派にとらわれない國體思想の学脈を築いた松平君山(一六九七年生まれ)より二十七歳年少であった。また、道麿は君山門下として知られる岡田新川(一七三七年生まれ)、磯谷滄洲(いそがいそうしゅう、同)より、十三歳年長であった。
道麿は物心つきはじめた頃から、大垣俵町の平流軒という本屋に小僧に出された。これをきっかけに、本好きになったのであろう。少年の頃に、伯父が与えた「節用集」を全部暗記してしまったという。「節用集」とは室町時代後期の国語辞書のことである。やがて、それらの教養書では飽き足らなくなり、近郷近在はもちろん、諸方に足を運んで書物を借りて読み、筆写していた。
道麿の弟子・加藤磯足が文化三(一八〇六)年に道麿の経歴や逸話を記した『しのぶぐさ』には、次のように書かれている。
〈農家の生まれですが幼年の頃より目にするもの耳にするものすべてに歌をつくられたとか、大へんすぐれた力を持った人でした。初めて歌を詠まれたのは九才のときといわれている〉、〈成長するにつれ近所はともかく少し遠方でも歌の本を所有している人があれば出かけて本を借りて写し取るなどして、ますます歌のみちに心を引かれていかれたが、みせてもらった書物はどれも古く六・七百年程の昔のもので何となくあやふやなことが多く、歌のみちに名高い人を訪ねて疑問の点などを質問しても、これは教えられない秘め事だとか、かんたんにあなたが調べ尽くせることではありませんと返され、はっきりと道筋を立てゝ納得のいく様に教えてくれる人はありませんでした。迷い迷ったあげく歌というのは何なのか…こんなことを勉強して何になるのだろうか…何もならないのではないか…と試行錯誤の上、二十八才のときから歌をつくることも書物を読むこともすっかり止めてしまった〉
このように道麿は、一旦歌の道を断念し、土木工事や屋根葺きの手伝いに従事していたようである。
●彦根の大菅中養父に師事
しかし、彼の生来の向学の志は再び燃え上った。良き師を求めて、彼は東海道土山宿の轎夫(かごかき)となり、駕籠を使う旅人から情報を集め始めたのである。そして、ついに道麿は、彦根に大菅中養父(おおすがなかやぶ)という人物がいることを知った。中養父は宝永七(一七一〇)年、彦根藩印具氏家老の家に生まれた。契沖の歌論を好み、賀茂真淵に師事して古典を研究した。
宝暦七(一七五七)年頃、道麿は早速彦根に赴き、中養父に弟子入りするのである。道麿を支援する者も現れた。道麿の向学の思いを知った彦根の豪商・納屋七右衛門が自宅に道麿を住まわせ、生活の面倒をみることになった。しかも、道麿のために必要な書物は全て買い揃えてやったのである。こうして道麿は、三年間何の心配もなく、学問に打込むことができた。
彦根での勉学の末、ようやく国学者として一本立ちする自信を固めた道麿は、彦根を去った。そして、最初は大阪で塾を開いたが、容易に受け入れられなかった。
そこで、道麿は名古屋に移ることにした。そして、狂歌の添削をきっかけにその存在を知られるようになっていく。
『しのぶぐさ』には、〈安永(一七七二~一七八〇)のはじめごろ狂歌(おどけた調子の歌)が流行した。あるとき狂歌集を見られて、その歌のよい、わるいや、今の慣習で昔からのしきたりと違っていることなどを指摘して一つの本にされた。それがあちこちに広がり、こんな人が居たんだと人々の話題にのぼるようになった。このようにして一人、二人、三人、四人と次々にひろがっていった。直接翁と会って歌のことを尋ねる人もでき、今まで聞いていたよりも身近かで親しみ易く上品でりっぱな人だと評判になった。そしてこの様にすぐれた力を持っている人を埋もれさせておいてはよくないと同じ気持ちの人々が集まり、今のつとめをやめて、もっと名前の知られた所に住んでもらって古典の勉強や古学の勉強の先生になってもらおうと迎えられることになった〉とある。
こうして、道麿は小桜町の桜天神の傍にあった霊岳院に住み、桜天神の社僧となった。そして詠歌の道、古学の講筵を開くことになったのである。