文政・天保期には、次第に国学派が尾張藩教学の足場を固めつつあった。これに対して、尾張崎門学派はどのように国学派と向き合おうとしていたのであろうか。
岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において以下のように書いている。
[前回から続く]〈宣長学が、古典注釈学としての学問の領域にとどまる限り、それは尾張垂加派からみても決して否定するものではなく、むしろ評価すべきものとみていることは確認しうると思う。だが、宣長の学問は、彼の神への熱い思いと密接不可分のものであった。尾張垂加派の宣長批判は、まさにこの点にかかわっており、宣長の「我国の学、神道めきたる事」は「いとあやしき事のみぞ多かる」という(高木秀條「いつまで草 古学弁」『天保会記』所収)。
ただ、宣長の神道に対しても全面否定するものではなかったことは、「宣長、大和魂を論じ出しよりして、我国漢学を宗とする者までも皇国皇統を推尊し、外国を賤しむるを知れり。其功、大なりといふべし」(深田正韶『正韶詠草一』など)と述べていることから理解することができる。高木秀條や深田正韶の少年期から青年期にかけて、名古屋を舞台に展開された宣長と徂徠学派の市川鶴鳴との『くず花』『末賀乃比礼』論争は、おそらく彼らの意識の中にあったと思われる。中国的価値に深くとらわれた儒者に対決する限り、宣長の神道論は、尾張垂加派にとっても十分に有用なものであった〉
では、尾張垂加派は宣長の神道論のどこを問題視したのだろうか。岸野氏は、①「古伝」そのものの持つイデオロギー性、②両者の神道の支持基盤、③「日本魂」の本質理解、④死後の霊魂の問題──の四点を挙げて、以下のように説いている。 続きを読む 尾張藩における崎門学派と国学派②
「平田篤胤」カテゴリーアーカイブ
尾張藩における崎門学派と国学派①
文政・天保期には、次第に国学派が尾張藩教学の足場を固めつつあった。これに対して、尾張崎門学派はどのように国学派と向き合おうとしていたのであろうか。
岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において以下のように書いている。
〈尾張藩教学に足場を固めつつあった本居門の学識は、尾張藩にとっても尾張垂加派にとっても認めざるをえないものであり、かつ有用であったことは、深田正韶自身が藩命による『尾張志』編纂の総裁として、校正植松茂岳、輯録中尾義稲を編纂スタッフに加え、その学識に依拠したことのうちにみてとることができる。この点、尾張垂加派が国学一般をどのようにみていたのか、以下の引用(高木秀條「いつまで草 古学弁」『天保会記』所収)によって確認しておこう。
「古学……其始は契沖阿闍梨なんどより出て、もとは歌学の助けとして万葉集をはじめ古言古辞の解しがたきをわきまへ、夫よりして古事記はことに古書にて古言古辞の証拠と為べき書なれば、専らに穿鑿してやゝ発明の事ども多く、契沖より以後、加茂の真淵なんどにいたり、いよいよくわしくなりて、先輩の心つかさる事ども迄もよく釈出して、書どもあまた著し後学のためによき便となる。大幸といふべし」
これは、高木秀條の理解であるが、契沖以後、宣長に至る国学の系譜と、その古典注釈学としての価値を正当に評価しており偏見はみられない。また、国学が漢文の影響の強い『日本書紀』よりも『古事記』を重視したことの意義についても、この限りでは冷静に理解しているといえる。このように学問領域に限定すれば、宣長に対しても「強記英才」と高い評価を与え、宣長の『古事記伝』もまた、「古言辞の解釈精密確実」と、その学問としての画期的意義を認めている。垂加派といえども、彼らの学識と文人としての良識は、学問としての合理性を持つ宣長学は理解の範囲内にあったことを確認しうるであろう。
だが、同じく国学とはいえ、平田学については極めて否定的であった。
「近頃、平田篤胤といへる者、もと宣長の門弟にて甚だ其流を信じ学びたるやうに聞えたれども、当時説く所、大に師説に悖りて、我ら如きの思ひもかけぬ珍奇の説をいひ出し(中略)かゝる事もいへばいはるゝ物かと思ふ計、奇々妙々の説ともなり、是また是非を論ずるに及ばず」
篤胤の学問方法の特徴は、古典の注釈という外貌は持つが、宣長のように漢文の潤色のない『古事記』を絶対化するものではなかった。彼は「真の古伝」というものを仮想し、自らの作りあげたイメージに合うものは『古事記』『日本書紀』に限らず、儒教・道教・仏教・キリスト教であろうが、すべて「真の古伝」の残影とみた。この立場から『日本書紀』を否定する宣長を篤胤は、「漢土に遺れる古文なるを、我が真の古伝に合へる説なる故に、御紀の巻首に先これらを載られたる物なるべし、然るを師のいたく悪まれたるは一偏なり」と批判をする。この方法は、子安宣邦もいうように、「古典に対して注釈者の位置にいるのではなく」、古典を「増殖する彼の観念のてだて」とするものであり、国学を古典注釈学の系譜の内に理解しようとする尾張垂加派にとって、まさに「思ひもかけぬ珍奇の説」であり、学問として認めうるものではなかった。平田篤胤が、一八三四年(天保五)十一月に尾張藩から扶持を打ち切られる背景には、幕府の動向や、名古屋での本居門の反発などが予測されるが、尾張垂加派のこのような平田学への対応もまた一要因として考慮する余地があると思われる〉(百四十九、百五十頁)
「近世国学の開基は尾張初代藩主の徳川義直だ」と主張した尾張藩の国学者
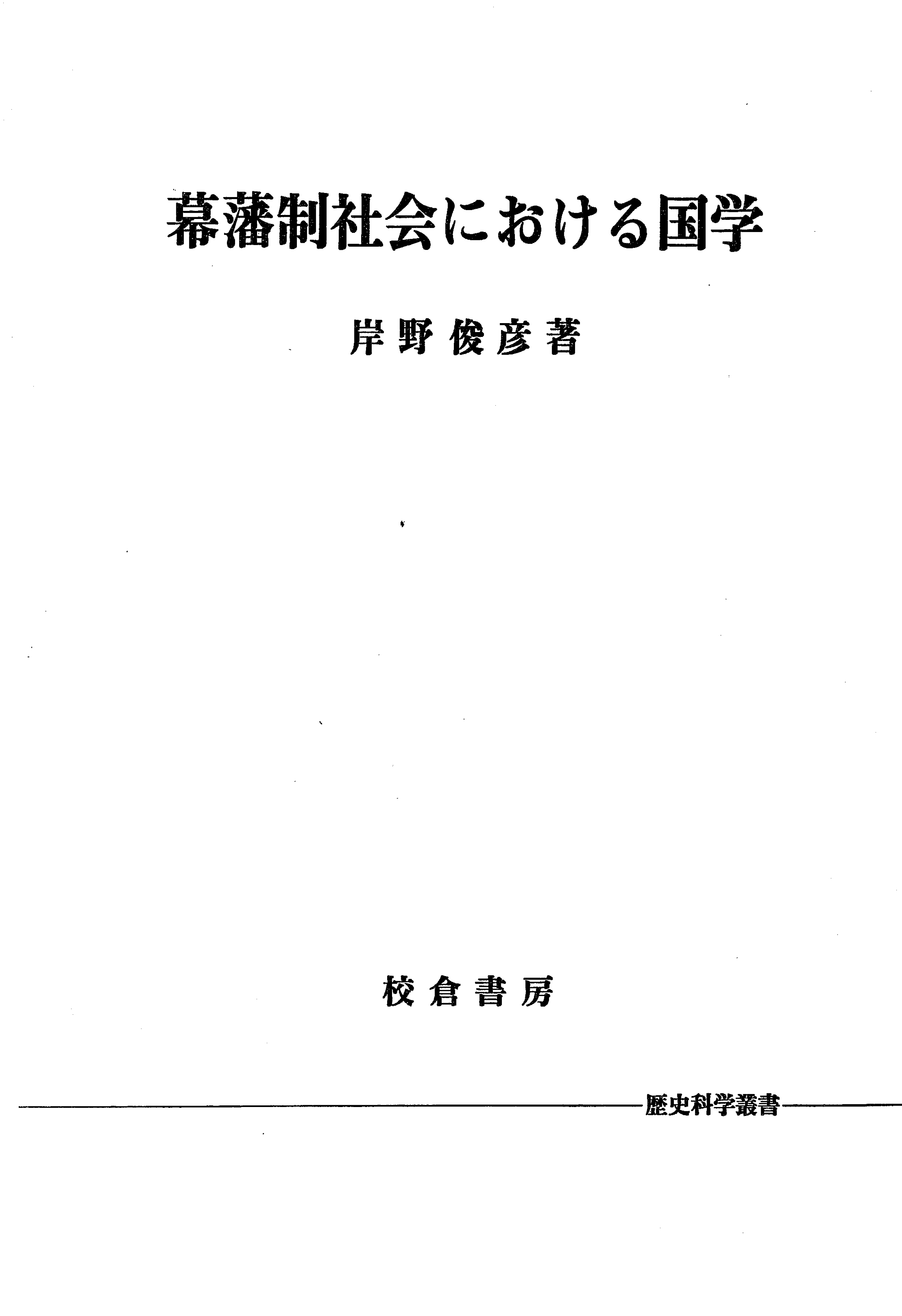
岸野俊彦氏は、『幕藩制社会における国学』(校倉書房、平成十年五月)において、尾張藩の国学者たちは、「近世国学の開基は尾張初代藩主の徳川義直だ」と主張したと指摘している。
近世の国学の系譜は、通常、契沖・荷田春満・加茂真淵・本居宣長・平田篤胤を基軸として理解されている。
ところが、尾張藩の国学者たちは、義直が『類聚日本紀』『神祇宝典』などの撰述を行っていることを根拠として、近世国学の開基は義直だと主張したというのだ。
尾張藩では、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという問題関心が強まった。その理由は何か。岸野氏は、以下のように説明している。
〈義直自身についていえば、家康の子として尾張藩主となったが、尾張藩の成立の事情からいえば、家臣団の出自の雑多性と複合性や、支配領域が尾張国を超えた複合的性格を持っていること等の中での、尾張藩と尾張徳川家の統合の論理とイデオロギーが不可欠であったという事情があった。徳川家康の子としての、徳川系譜と事跡の確認は最も重要な問題であった。戦国期に遡れば、多様な戦国大名の家臣であった者を家臣団に組み込むためには、徳川系譜が清和源氏に繋がることもまた重要な問題であった。清和源氏と繋がれば、古代天皇の事跡の研究はい儒学的政治論の「王道」「治者道」を極めることと同列になる。儒学神道の方法がこれを結びつけたといえる。こうして、藩祖としての統合の原理を求めて著されたものであるだけに、幕藩制の矛盾が激化するたびに、藩祖の著作に帰れという、問題関心が惹起するのは当然であったといえる〉(十九、二十頁)
ただし、天明・寛政改革期には、尾張藩における国学派の地位はそれほど高くはなかった。この時期、義直著書の校合が主導したのも、儒者や垂加派だった。校合の担当者は、『初学文宗』『軍書合鑑』が細井平州、『神祇宝典』が河村秀根、『類聚日本紀』が稲葉通邦、『成功記』が岡田新川、『中臣獣抄』が吉見幸孝であった。
ところが、尾張藩における国学派の地位は上昇していった。その契機こそ、やがて十四代藩主に就く徳川慶勝とのむすびつきであった。岸野氏は、「尾張藩に仕えた国学者たちは、幕末維新期の尾張藩主徳川慶勝と結ぶことによって、藩祖尾張義直の国学的再評価を行い、藩政改革と国政変革に参加しようとしていた」と述べる(十二頁)。
尾張藩の平田国学─林英夫編『図説 愛知県の歴史』
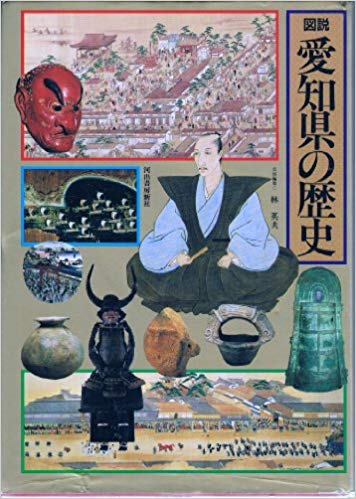 尾張藩の平田国学に関して、林英夫編『図説 愛知県の歴史』(河出書房新社)は、以下のように書いている。
尾張藩の平田国学に関して、林英夫編『図説 愛知県の歴史』(河出書房新社)は、以下のように書いている。
〈…尾張において広範に受容された本居学にくらべ、平田学はむしろ排斥された。篤胤は、小藩の備中松山藩に仕官していたが、より広い活動の場を求めて尾張藩に仕官することを強く望み、積極的な出願をくり返したが、ついに容れられなかった。
とくに、文化・文政期(一八〇四─三〇)以降、尾張での国学(本居学)の重鎮であった植松茂岳が、その著『天説弁』で平田学を徹底的に論難していることもその一因であろうが、儒教や仏教を強く排斥した平田学が、尾張の漢学者たちの反発をかったことも予想される。
結局、平田学の尾張における門人は数名にとどまり、むしろ平田学は、三河の農村指導者層のあいだに広く根をおろしていった〉