杉田定一は『評論新聞』の記者、『草莽事情』の編輯長を務めた。これらと同系統のメディアとして、『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等があった。以下、『遠山茂樹著作集 第3巻 自由民権運動とその思想』(岩波書店、1991年)にしたがって、各メディアの概要を整理しておく。
●『評論新聞』
一八七五(明治八)年四月二十日発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止を命ぜらる。編輯長として横瀬文彦・関新吾・小松原英太郎・東清七・中島富雄・高羽光則・田代荒次郎・鳥居正功・中山喜勢・高橋克、評者として山脇巍・田中直哉・中島勝義・満木清繁・岡本精一郎等がいた。発行所は集思社。
●『草莽事情』
一八七七(明治十年)一月十九日発刊。同年七月発行停止。編輯長杉田定一・高橋克、印刷人鳥居正功、共に評論新聞関係者である。発行所は集思社分局。
●『采風新聞』
一八七五(明治八)年十一月発刊。一八七六(明治九)年七月十日発行停止。編輯長矢野駿男。発行所は采風社。
●『草莽雑誌』
一八七六(明治九)年二月発刊。同年七月十日発行停止。編輯長は木庭繁・馬城章造、社長栗原亮一、発行所は自主社。
●『莽草雑誌』
一八七六(明治九)年八月発刊。同年九月発行禁止。社長は栗原亮一・波多野克己、編輯長は古庄簇一郎、発行所は自主社。
●『湖海新報』
一八七六(明治九)年三月発刊。同年七月十日発行禁止。編輯長は山田精一郎・肥後司馬・倉本半太郎・福間清之・今井毅、評者に田代荒次郎。これまた評論新聞社系統である。発行所は参同社。
「杉田定一」カテゴリーアーカイブ
自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
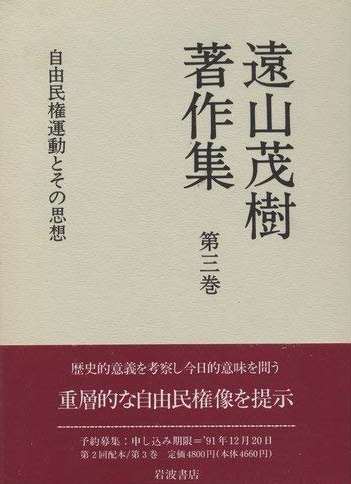 遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
〈立志社周辺の自由民権の壮士達、例えば杉田定一の場合を考えてみよう。彼は本来の武士出身ではない。杉田家は越前随一の大地主で、藩の用達を務めた豪農・豪商である。しかし彼をして自由の闘いに身を挺せしめた意識は、庶民としてのそれではなく、あくまでも志士の気概であった。「国事の為に死生を度外に置き、天下を取るか、首を取らるるかは当年の理想なりしなり……獄中閑日月の間、書を読みて或は英雄豪傑の偉業を追慕し、或は志士仁人の艱苦を回想し」と述懐している。彼は自己の思想の系譜を次の如く説明している。「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権と共に民権を重んずる明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった」と。すなわち尊王攘夷の帰結として、「内においては藩閥政治に反対し、外においては東洋の自由を主張した」闘いの実践がうち出されたのである。だからこそ西南の役勃発に際会し、「第二の維新を東北より起さん」とし、まず水戸に足を運んだ。何故水戸を第一に選んだか、明治維新の思想的根源である水戸学の発祥地であるからと、彼は説明している。もとより水戸では志をえず、転じて庄内に入った。蓋し庄内は幕末徳川氏に殉じて最後まで「義戦」した「純忠至誠の心」「尊王愛国の精神」を有した地、よって「東北諸藩を聯合し」薩長藩閥政府を打破せんというのが、彼の計画であったという。しかし庄内でも失意、三転土佐に赴き挙兵を勧説しようとし、そこで板垣に会い言論の闘いに翻意する。当時の自由民権論者の思想的遍歴を象徴するかのような行動であった。
杉田が民権派の壮士となる機縁をなしたものは、彼が『評論新聞』の記者となったことであるが、その『評論新聞』、さらに彼が編輯長となった『草莽事情』、これらと同系統の『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等──これらの新聞雑誌こそ、過激派民権壮士の拠点であり、それに掲載された論説は、士族的精神に支えられている最も封建的な、と同時にその故に最も戦闘的な自由民権思想の典型であった。 続きを読む 自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」─杉田定一の思想
杉田定一と愛国交親社②
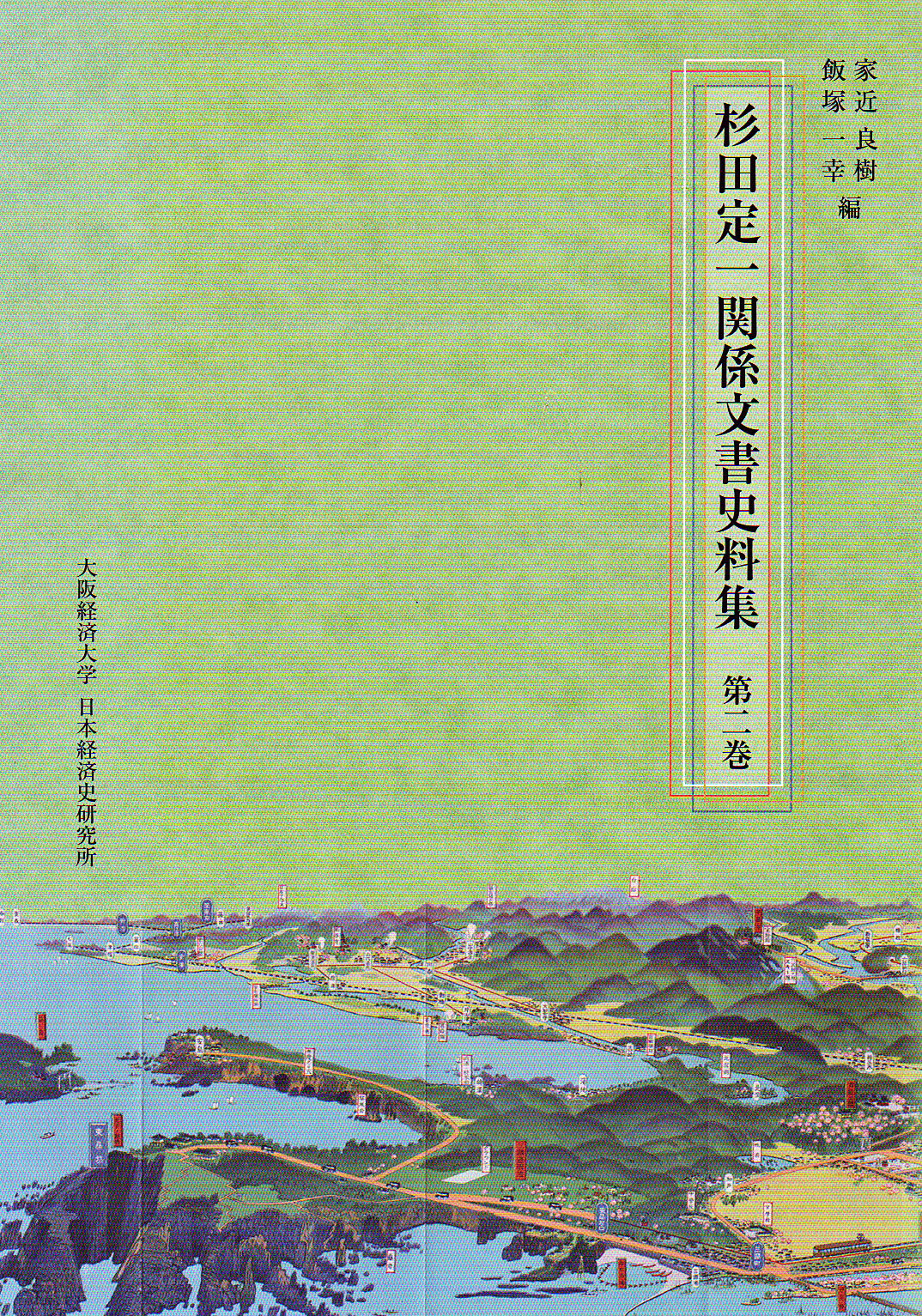 家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
〈北陸懇親会ノ義ニ付御照会ノ趣ハ社会ノ為メ慶賀ノ至ニ候、然ルニ小生事ハ盟兄御承知ノ通り上京ノ都合ニも相成リ、殊ニ二月下旬三月上旬迄ニハ高知ゟ島地正存来訪ノ筈ニ有之、過日来態々中来候趣も有之、又且ツ三月上旬ニハ我地方ノ党員ハ岡崎ニ会シ候手筈ニ客年十一月中予テ申合有之、旁遺憾ナカラ此段御承知被下度、但シ庄林ハ是非ニ相拝候様申入置候、且ツ外ニ村枩愛蔵氏ニハ多分出席仕リ度旨拙者迄申越居候間、尚相勧可申候、実ハ過日当懇親会ニも遠路之気嫌も無ク御出会被下候、交義上ニ於テモ是非出会可仕筈ナレ共、如何セン前陳ノ通リニテ生義ハ繰合都合相兼候、御推察ヲ乞、尚御来会諸君ニ可然御通声是祈ル
追白、天下ノ事ハ只タニ表面上ノミノ働ニテハ遂ニ目的ヲ達ス可カラザル事ハ歴史ノ裁判ニ於テ明カナリ、故ニ以来ハ別テ御注意、神出鬼没兎角○○ノ意外ニ出テ秘々密々御計画アレ、嗚呼御互ノ任も亦大ナルカナ、書意ヲ尽サス否ナ尽サヽルニアラス、尽スコト能ハサレハ也〉
愛国交親社と杉田定一
愛国交親社は、杉田定一とも関係を有していた。飯塚一幸氏は「自由党成立後の杉田定一」において、次のように書いている。
〈杉田と林包明はすでに(明治一五年)一〇月中には東京を出ており、一一月二日か三日には四日市から汽船に投じて三河国碧海郡上重原村の内藤魯一の許へと向かっていたのである。内藤は杉田・林よりも早く帰郷しており、その後の東京の模様について杉田・林より詳しく聞き取り打合せを行ったものと推察される。この路程で杉田は尾張の庄林一正にも会談した。杉田は、庄林が中心となって急激に農民の組織化に成功しつつあった愛国交親社に強い関心を抱き、同社社則の提供を依頼した。明治一五年七月、愛国交親社は指導組織の改編を行い、郡ごとに幹事長・副幹事長各一名の他、書記・出納係・剣術取締・機械係などを任命し、その下部組織として社員五〇名ごとに「組」を編成して幹事・同補助を置き、さらにその下部に末端組織として社員一〇名ごとに「伍」を編成して伍長を任命した。庄林は、恐らくこの際の改正社則を、杉田の依頼に応じて一一月二七日付の書簡に同封して送っている。残念ながら杉田定一関係文書中には社則は見当からないが、同年九月の「愛国交親社行列之図」が残されている。杉田は、南越自由党の発展を策すに当たり、愛国交親社の経験を何らかの形で生かそうと考えたのではないか。また、杉田と内藤魯一・庄林一正との接触は、板垣洋行問題後の自由党の会議において話題となった、愛知県での実力行使と関連性があるのかも知れない」
自由民権派と崎門学
 明治の自由民権運動の一部は、國體思想に根差していたのではないか。拙著『GHQが恐れた崎門学』で、「自由民権派と崎門学」の表題で以下のように書いたが、「久留米藩難事件で弾圧された古松簡二は自由民権思想を貫いた」と評価されている事実を知るにつけ、そうした思いが強まる。
明治の自由民権運動の一部は、國體思想に根差していたのではないか。拙著『GHQが恐れた崎門学』で、「自由民権派と崎門学」の表題で以下のように書いたが、「久留米藩難事件で弾圧された古松簡二は自由民権思想を貫いた」と評価されている事実を知るにつけ、そうした思いが強まる。
〈維新後、崎門学派が文明開化路線に抵抗する側の思想的基盤の一つとなったのは偶然ではありません。藩閥政治に反対する自由民権派の一部、また欧米列強への追随を批判する興亜陣営にも崎門の学は流れていたようです。例えば、西南戦争後、自由民権運動に奔走した杉田定一の回顧談には次のようにあります。
「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、(吉田)東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなった。後年板垣伯と共に大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権を尊ぶと共に民権を重んずる、明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのである」
熊本の宮崎四兄弟(八郎、民蔵、彌蔵、滔天)の長男八郎は自由民権運動に挺身しましたが、彼は十二歳の時から月田蒙斎の塾に入りました。八郎は、慶應元年に蒙斎の推薦で時習館へ入学、蒙斎門人の碩水のもとに遊学するようになりました。
一方、自由民権派の「向陽社」から出発し、やがて興亜陣営の中核を担う福岡の玄洋社にも、崎門学の影響が見られます。自らも玄洋社で育った中野正剛は『明治民権史論』で次のように書いています。
「当時相前後して設立せられし政社の中、其の最も知名のものを挙ぐれば熊本の相愛社、福岡の玄洋社、名古屋の羈立社、参河の交親社、雲州の尚志社、伊予の公立社、土佐の立志社、嶽洋社、合立社等あり。此等の各政社は或はルソーの民約篇を説き、或は浅見絅斎の靖献遺言を講じ、西洋より輸入せる民権自由の大主義を運用するに漢籍に発せる武士的忠愛の熱血を以てせんとし……」
男装の女医・高場乱は、頭山満ら後に玄洋社に集結する若者たちを育てましたが、乱の講義のうち特に熱を帯びたのが、『靖献遺言』だったといいます。乱の弟子たちも深く『靖献遺言』を理解していたと推測されます。大川周明は「高場女史の不在中に、翁(頭山満)が女史に代つて靖献遺言の講義を試み、塾生を感服させたこともあると言ふから、翁の漢学の素養が並々ならぬものなりしことを知り得る」と書いています。
乱の指導を受けた若者たちの中には、慶応元年の「乙丑の変」で弾圧された建部武彦の子息武部小四郎もいました。建部武彦らとともに「乙丑の変」の犠牲となった月形洗蔵の祖父、月形鷦窠は、寛政七(一七九五)年に京都に行き、崎門派の西依成斎に師事した人物であり、筑前勤王党に崎門の学が広がっていたことを窺わせます。乱は、『靖献遺言』講義によって、自らの手で勤皇の志士を生み出さんとしたのかもしれません。また、明治二十年に碩水門下となった益田祐之(古峯)は、頭山満を中心に刊行された『福陵新報』の記者として活躍しました。〉