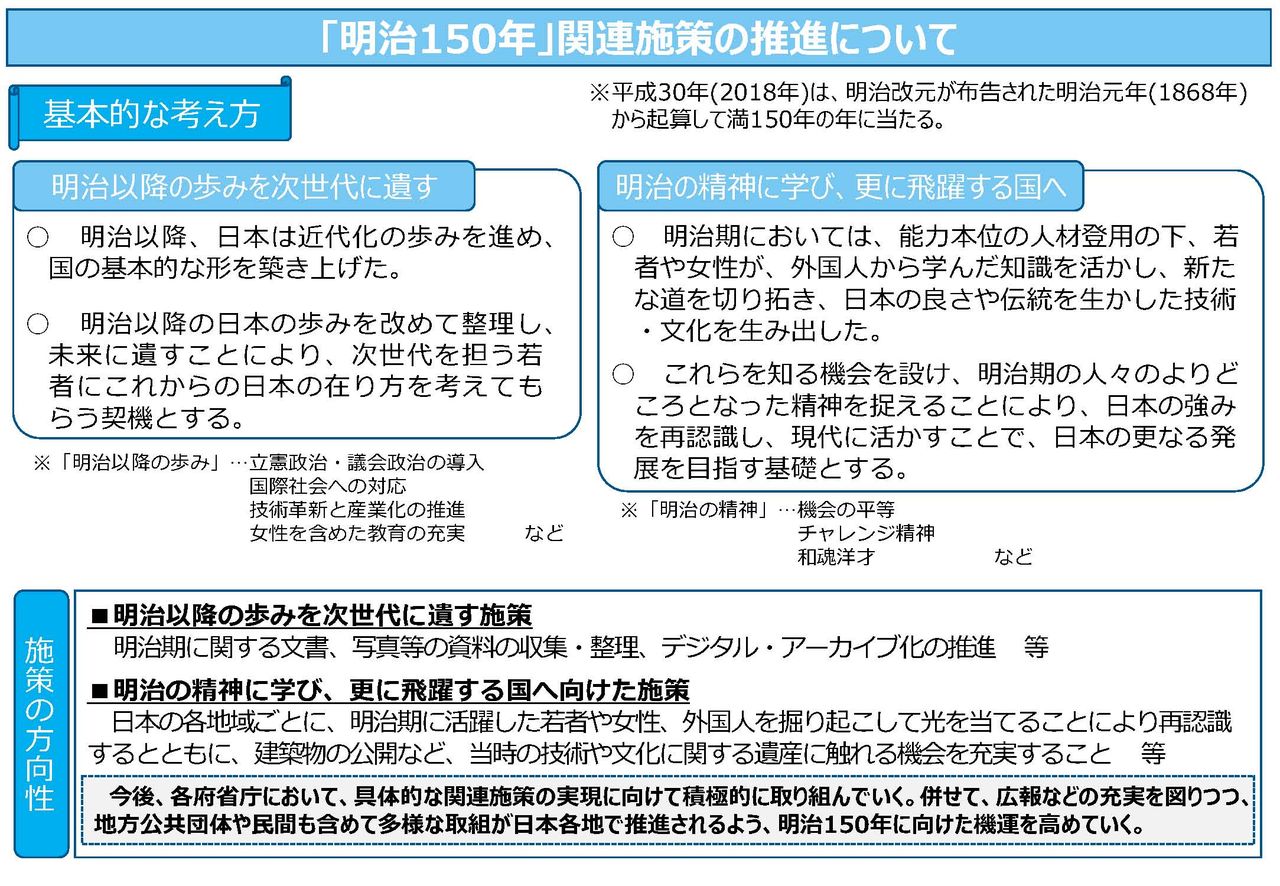愛媛県師友会機関紙「ひ」に掲載された拙稿「伝統と信仰」について本ブログに掲載する。
----
伝統と信仰
義に生きる
人は義によって動き、義によって生きる。人間の魂から出た言葉は、人の心に働きかけ、魂を揺さぶり、義を貫く生きざまにいざなう。
吉田松陰は、高杉晋作や久坂玄瑞らと対立したとき、「僕は忠義をなすつもり、諸友らは功業をなすつもり」と言った。松陰は政府を転覆し権力を握りたかったのではない。ただ己の魂に働きかける忠義に突き動かされたのである。
愛国の情は国粋への信仰の念があって初めて成立するものである。自らの発言は国粋の殿堂に新たな黄金の釘を打ち込む姿勢でいるかどうか、常に問い続けなければならないからだ。愛国は、ちっぽけな功名心や政府に追従する気持ちとは峻別されなければならない。先人からの賜り物である伝統は、自己決定をはるかに超越したところで一人一人の人生の規範となっている。
現代日本において、信じる力が絶望的に落ち込んでしまっている。われわれの日々の生活において、大いなるものに頭を垂れる機会は少なくなってしまっている。だが、大いなるものへの敬意と、自らの利害を超えた大義に参与したいという心は、本当に失われてしまってもよいのだろうか。
立極垂統
竹葉秀雄は『立極垂統』で、天之御中主神から今上天皇まで続く系図を「立極垂統日嗣の道」として示したうえで、「この系図を観ておれば、あらゆる悩みはみぞぎはらわれ、更に之を礼拝信仰すれば、宇宙の大生命がそそぎこまれて躍動歓喜し、諸神・諸仏・諸天嘉し加護し給う」という。それは神代から続くわが国の根幹への確信であり、それへの奉仕を人々の使命とするのである。
竹葉は『青年に告ぐ』で、「我自体が、神の自己顕現の相であるのであつて、欲望も神のものである」といい、「いちばん深い欲望を最もよく生かし、それぞれの欲望を正しく生かし、心の安んぜられる、天の声を聞いての行いをすることである」という。天の声を聞いて、それに基づく行いをすることこそが大欲であり、使命に生きる姿だとしたのである。現代人は資本主義的な自己利益の充足に馴れきって、精神の救済を後回しにしている。心ある人でさえ、その主張は単純な政策論議に限定されていて、その奥に潜む魂を問題としない。政府や市場は利害関係で人を誘導することはできるが、心まで支配することはできない。
個人の生命は有限である。しかし、悠久の大義のために全身全霊を尽くせば、その魂は永遠に語り継がれることになる。国家には、そういう信仰が不可欠である。政治経済にばかり関心を向けて、こうした信仰、文化の側面を軽視すれば、国家は単なる大衆の集合体となり、各人の溌剌とした生命力を発揮する場所ではなくなってしまう。
『青年に告ぐ』の安岡正篤による序文では、「我々が現在享楽してゐる科学技術による産業的繁栄に対して、それに調和し、それを修正するような、精神的・理性的・道徳的発達が今後行はれなければ、恐らくそれは正しい意味の革命的努力でなければ、文明の没落は救はれまい」と述べられている。共同体が解体され、露骨な競争社会となりカネと暴力に支配される世の中になる。そうした負の側面を修正するのは、精神の働きなのである。竹葉は、神代から垂直に降りてくる道にこそ、この精神の働きを見たのである。
安岡正篤は「口舌の徒」か
竹葉の師である安岡正篤は、戦後は無論、戦前においても「口舌の徒」という偏見で見られていた。だが安岡が終生問題にしていたのは道義と信仰であって、それを確信しなければあらゆる政策の実行も無駄になってしまうと考えていた。それは一部の人間にとっては、抽象理論をもてあそぶ「口舌の徒」にしか映らなかっただろう。しかし、一番大切なものをおざなりにしておいて「具体的」な政策を云々することこそ無駄なことと言わねばなるまい。
影山正治の『維新者の信條』に次のような一節がある。「維新者は、その本質に於て何よりも絶対なる国体信仰の把持者でなければならない。/如何に維新を論じやうとも、不動の国体信仰に徹せざるものは遂に維新者たることを得ない。/思想も理論も学も、破壊も建設も闘争も、政治も経済も文化も、すべてはこの信仰に根ざしてのみ考へられ、戦はれ、実現されなくてはならない。/国体は絶対に手段化さるべきではない。戦争遂行のための維新、資本主義否定のための維新、国民生活安定のための維新ではない。国体を明らかにするための維新、国体を実現するための維新であり、その結果として、戦争の遂行も可能となり、資本主義も否定され、国民生活も安定されて行くのだ。/維新とは単なる組織機構の変革ではない。神代復興であり、国体復帰である。この意味における世界の変革、価値の転換である。」(/は改行)
維新は世の革新である以上に己の原点回帰でなければならない。影山はどちらかと言えば排儒的な論客であり、儒学の素養をもとに発想していた安岡とは思想的背景が大きく異なる。だがこの二人は、共に道義と信仰の確立を目指した点で共通するものがある。
安岡は『東洋倫理概論』で「信仰と謂へば普通宗教の代名詞の様に解されて、道徳と対称せられるが、私はさう解さない。信は純一な生活であり、仰は理想の欣求である。其処には当然敬と懼とがなければならぬ」と述べたうえで、王陽明の、山中の賊より破りがたきは心中の賊だという逸話を述べ、さらに孔子の「信なくば立たず」の「信」をも、信仰と解するのである。安岡にとって信仰がいかに大きな問題であったかうかがいしれよう。
天の声を聞く
西郷隆盛の「敬天愛人」という言葉は、大いなるものへの畏れを抱くこともまた人間に備わった愛しむべき感情であり、共同体に裏打ちされた道徳の先に「天」があることを教える。
竹葉秀雄は『青年に告ぐ』で、「孔子も、釈迦も、キリストも、ソクラテスも、マホメットも、道元も、中江藤樹も、吉田松陰も皆その青年時代に、内奥の神の声を聞いて、その道に生きた人たちである」という。内奥の神の声は宗派を選ばない。どの先人も魂を揺さぶってやまない声に突き動かされたのである。
例えば孔子でいうと、白川静は『孔子伝』で、哲人を「伝統のもつ意味を追究し、発見し、そこから今このようにあることの根拠を問う。探究者であり、求道者であることをその本質とする」と定義したうえで、孔子を「述べて作らず、信じて古を好む」人であったとする。「述べて作らず」とは、天からの言葉を余すことなく記録し、伝統と信仰を後世に伝えようという精神である。
伝統とは人生のあらゆる規範としてはたらく。伝統とは言葉を中心として構成される慣習のことだ。先人が「神」と呼んだ人智を超えた何か、そして人間そのものへの関心を言語化したものが「伝統」なのではないだろうか。過去を振り返って追体験し、各人に内在するものになった時、伝統ははじめて生きるものとなる。日本人の精神生活に根付いた伝統を信じようとするとき、まず行うべきは先人の言葉を虚心に受け取ることであろう。八百万の神の国であるわが国は、あらゆる事物に神性が宿るのと同時に先人にも神性を感じてきた。即ち天の声を聞くということは、伝統を信じることと不可分になる。
哲学と求道は不可分のものである。思想とは単純な論理的正しさを問うだけのものではなく、人格の陶冶、社会の道義的進歩と結びつかなくてはならない。日本人の精神生活と信仰は切っても切れない関係にある。言葉一つとっても、日本人は言霊と呼び、言葉に魂が宿ると考えられてきた。人の心に宿るさまざまな感情の流れが言葉となって出てきた瞬間、天地をも動かし、神をも揺さぶる力を持つ。人は言葉によって、過去、未来、さまざまな人、ものとつながることができる。言葉こそ伝統であり、言葉こそ魂だ。してみれば人の魂が他の人の魂を揺さぶることができるのは、至極当然ではないだろうか。日本人の信仰とは、日本の伝統の上に咲く花である。
死者と生きる
明治時代の文明開化以降、信仰や伝統文化の影響力は小さくなる一方である。資本主義、ビジネス偏重の社会に抵抗する精神はほぼ見られなくなってしまった。現代人の生活は、より経済成長し、より消費し、より寿命を延ばした方が良いという物欲に常に煽り立てられている。われわれは否応なしにモノに塗れた生活に巻き込まれているが、そうした生活はどこか胡散臭い。なぜかと言えば、死と信仰の問題を置き忘れているからではないか。
平泉澄は『山彦』で次のように言う。「戦後社会の動搖、人心の不安、今に至つておさまらぬは、けだし過去との連鎖を絶ち、父祖の歴史を忘却した所に、その根本の原因があるのであらう。/およそ社会は、これを現在の相においてのみ見てはならぬ。死者もまたその構成分子であり、発言権を有するものである。それら先人の温情を体認して、初めて正しい道を歩むこともでき、歴史に参じてこそ、真に文化に貢献することもできるのである。」(/は改行)
わが国の土着的な信仰では、死者は遠いどこかに旅立ってしまうのではない。わが国土を離れず、故郷の山河や子孫の生業を見守っていると考える。お盆には死者が帰って来ると言われるが、生活に息づく信仰は死者の存在にあふれている。死者への弔事は死者に話しかけるような形で述べられる。死者の魂が天国や極楽と言った遠いどこかに行ってしまうと考えない世界観とも無縁ではないだろう。死者に囲まれ、見守られる生活には社会がある。死者を遠ざけてきた現代社会は、社会の代わりに市場が大きくなり、便利になる反面、どこか生活が窮屈なものになってきた。
「利」の時代から「義」の時代へ
戦後、敗戦のショックから、人間は義では動かず利害関係で動くものだという世界観のもと、「義」よりも「利」、「公」よりも「私」という風潮がはびこった。問題なのは、そうした「義」よりも「利」の思想がGHQのもたらした平和に甘んじる自己の罪の意識を巧みに隠したことである。戦後は共産主義的義に対して「利」と「現実」を説くいわゆる「保守」が登場したが、結局彼らがやったことは日本国憲法と日米同盟の戦後体制を残存させたことだけだった。真剣にこれらの打破、克服を目指すならば、日本人が歴史的に抱いた大義に今一度立ち返ることが必要だ。近代以降、政治は君主と人民の慈愛による関係ではなく、人間の顔を失った権力の作用と反作用の応酬となり、人々は政治や経済政策にますます依存することになった。命令する側とされる側の区別は封建制の撤廃によりなくなると思われていたが、実際は、権力の作用と反作用は抜きがたく社会に存在し続けることとなった。
伝統を先例と混同してはならない。人々に宿る魂に学び、揺さぶられる敬虔な気持ちを忘れた途端、伝統は先例に逆戻りする。先例は制度であり、伝統は心である。制度が表面上変わっても、心が変わっていなければ、それは変わっていないのと同じことである。伝統とは精神の連続性である。伝統は、いつも変化しているにもかかわらず決して全面的に崩れない、社会の羅針盤である。伝統を考えるということは、国家について考えるということだ。
日本人が日本の伝統、信仰や文化を知らないで、次代に伝えず生きていてよいのか。日本の美質を称え、欠点を改善していくことは日本人に課せられた使命ではないのか。日本史を知識的に学んだだけでは日本史が人格を構成するまでには至らない。日本人がこれまで考えてきた考え方、発想が自らの発想と分かちがたく結びついていることを自覚し、その中で生きていくことを自認して初めて、自己の思想は深まるのである。
あらゆる学問は国民、あるいは人類の幸福のため、叡智への敬意のために行われていた。それは公共性への深い信頼からなる行為に他ならない。だが、次第に学問は実証の名のもとに専門家の仕事となり、社会貢献を資本主義的、経済的価値にすり替えてしまった。近代思想の荒波の中で、人を魂から鼓舞するものが解体されていった。宗教もそうであるし、芸術、文学、音楽、そして学問もそうである。これらのものから人々が本当に理想とすべきものへの関心が薄れてきたように思われてならない。
学問は世界を認識する手段に過ぎないというのが近代科学的態度であろうが、ある人々にとっては、学問は全身を捧げるべき「道」であった。学ぶことそのものが人生を「生きる」ことに他ならないのだ。自分が学んだことと自分自身が不可分になる。そうした態度から人を魂から鼓舞するものが生まれてくるに違いない。学問は世のため人のために役立たなければならない。だがそれは金銭的価値や計量的成果に置き換えられるものではない。
おわりに
竹葉は『青年に告ぐ』の最後にこう記している。「私は、祖国の明日を思うとき、胸痛むのである。/その青年が、祖国を愛せず、この高貴な伝統を捨てて顧みず、純真を失うて、/何の祖国の明日があらう。畏るべき後生をもたざる民族は、ついに存在の価値なく、滅亡にいたるであらう。/いまや、世界が、二十五時の暗黒を告げ、機械と組織の中に、人間性を喪失せんとして、アジアに光を求めているこの時。/そして今度の戦いの後、日本は敗れたけれど、アジア・アフリカの諸民族が、つぎつぎに独立して、アジアの心を求めているこの時。/資本主義と共産主義の争いが、ともに唯物に立脚していて終わることなく、ついには人類は破滅にいたることを知つて、第三の出生すなわち心と物の一致、心を持つ人間が、純粋経験によつて物を格しく体認して知を致し、意を誠にして、心を正し、天下を平にする道、そこに人間性の尊重と発揮のおこなわれる、光りの世界を求めている時。/分化の極まりから総合統一へ、西洋から東洋へと、心の向けられている時。/エネルギーの根元である太陽エネルギーと、万物に宿る日の霊との、物質と精神との一致の世界、「ひの道」が、いまや明らかにされんとしているこの時。/日の国、日本の青年は、このままでよいであろうか。まず/自らの明徳を明らかにし、/国家の鎮護となり、/民族の伝統を、継承発展せしめ、/大和世界建設のために、/巨いなる「ひ」を、揚げねばならないのだ。/私は万禱して、青年に告げる。」(/は改行)
現代は利害関係から考える以外に世界を認識する手段を失いつつある。だが、反面、だからこそ伝統と信仰という大いなる価値について思いを致すことができる。伝統も信仰もどこか遠くにあるものではなく、自らの魂にすでに備わっている。あとはそれに気づくか否かであり、気づいたときにはもう大義を果たす大望が、自らを鼓舞してやまぬようになるだろう。それが人々に広まった時、真の維新は達成されるに違いない。